
松本哲也氏による演劇ユニット・小松台東の新作公演となる「ソファー」が5月10日より東京・下北沢のザ・スズナリにて上演される。公演を間近に控えた某日、静かな熱がこもる稽古場の様子をレポートする。
小松台東は2010年に劇団活動を開始し、全作品を主宰・松本氏の地元の方言である宮崎弁で上演。人間同士の交わりと心の機微を、丁寧かつユーモラスに描き続けている。「ソファー」は、家じまいを決めた実家に置かれている古びたソファーを軸に、久しぶりに顔を合わせた面々が消えゆく家族について語り合う物語となっており、松本氏が作・演出のほかキャストとしても出演する。
稽古場の中心に置かれているのは、4~5人が座れそうな茶色のコーナーソファー。なめらかそうな革張りの座面は座り心地がよさそうで、物語は、このソファーの周りで描かれていくことになる。見学したシーンは、過去の場面だった。
静かなリビングに現れた長女・仁美(山下真琴)が、ソファーの背もたれに跨るように寝そべる。そこに帰ってきた父・康之(佐藤達)は、不思議な体勢で寝る娘に声をかけるが、娘の反応はない。やがて母・佳子(江間直子)もソファーに現れて、眠る娘を傍らに夫婦の会話が繰り広げられる――。

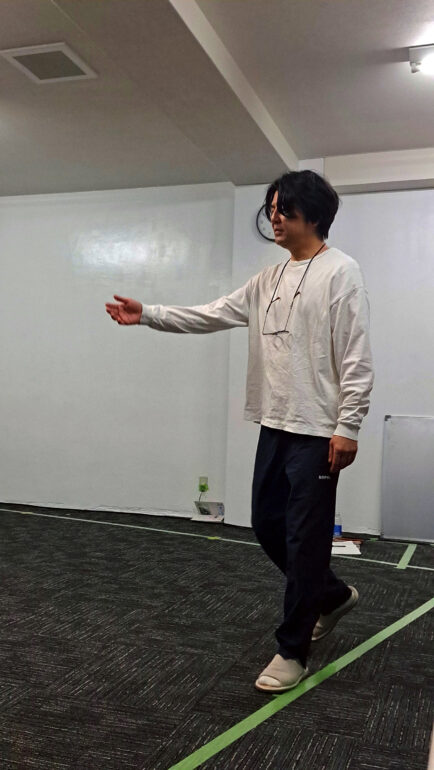
稽古も後半に差し掛かっているため、キャストもセリフや立ち回りはしっかり入っている様子。小松台東の特徴のひとつである宮崎弁は、その地域に馴染みはなくてもどこか懐かしさがあり、同時にまさにこんな人々がそこに存在しているような会話の生々しさも感じさせられた。
繰り広げられる会話は、本当に静かな、さらりと聞き流してしまいそうになる何気ない日常会話。そんな会話を、ニュアンスを細かく調整するように、言い回しや語気の強さについて松本氏から指示が入る。それは、まるで番号のわからない金庫のダイヤルを少しずつ回すような、僅かな調整だ。しかしながら、その些細な調整で、微妙な家族の関係性、言葉からにじみ出てくるような心情が見えてくるようだった。
表現をコントロールしながらも宮崎弁で話す苦労や難しさはあるようで、指示された部分を何度もそらんじる場面は時折見られた。ただ、繰り広げられる静かな会話の中に流れている、モヤモヤとした感情の渦がとてもやるせない。激しい言葉の応酬ではないのに、どこか心がざわつくような場面に仕上げられていった。
続いての稽古も過去の場面。深夜に母・佳子と佳子が働く店の客・桑原(瓜生和成)が家に来るシーンだ。酔っぱらって帰ってきた佳子と桑原に驚きつつも、仕方なく迎え入れる父・康之。桑原は地元では有名な菓子店の経営者のようで、ソファーに座って康之には緊張感もなく話しかけ、佳子と親密そうに言葉を交わす。どこか飄々としていて掴みどころがない桑原は、物怖じせず異質だ。そして酔った佳子は奔放に振舞い、康之は我が家であるにも関わらず縮こまる。
この場面では、家族の歪さが立ち上がってくるようなやりとりが続き、緊張感が漂う。中でも桑原は、康之の前であるにもかかわらず佳子との距離感が近く、見せつけているよう。そして佳子も康之を試すかのように大げさに振舞っているように見えた。この場面でも言葉のニュアンスや強さの調整はもちろん、酔った佳子がソファーに倒れ込む時の角度や足さばきまで、時には松本氏が実演して見せながら何度も確認を重ねていく。この緻密な積み重ねに、どんな小さな仕草にも、意味を持たせていると思い知らされる。一方で、桑原がひとりソファーに残されるシーンは非常にコミカルで、思わずクスっと来てしまった。


本作は、松本氏の実家にある古びたソファーから着想が得られていると明かされている。5人用だったそのソファーは分割式で、不要になったりダメになったりで少しずつ処分され、今では1人用になっているそう。そんなソファーに感謝の念を頂きつつ、創作されている。そんな想いもあってか、稽古の様子からはソファーとの関係性も繊細に描いていることがうかがえた。ソファーへのちょっとした触れ方もしっかりと演出を入れられており、本作の舞台の中ではソファーもキャストのひとりなのかもしれないと感じた。
稽古で拝見したシーンは過去を振り返るように夫婦の関係性が強く映し出されていたが、他の場面では、まさに”家が終わっていく”ことを目前にした、長女・仁美のほか長男・充彦(松本哲也)、次男・龍太(今村裕次郎)ら子どもたちや、仁美の夫・大輔(今里真)、次男の後妻・彩音(道本成美)の姿も描かれていく。彼らは、終わりゆく家に鎮座するソファーを前に、何を思い、語らうのか――。
また、公演では全日全公演、劇団員によるアフタートークや、松本氏と出演者のクロストーク、音響解説のアフターイベントなど、さまざまな企画も連日予定されている。より深く、小松台東の演劇に触れられる機会になるはずだ。
何気ない会話なのに、心がふるえて、ずっとやるせない。そんな時間となる予感が、静かに熱量を帯びる稽古場からビシビシと感じられる稽古だった。残りの時間でも、あらゆる可能性を模索し、宮崎弁に言葉以上のさまざまな想いを込めていくはず。それが舞台上でどう色づくのか、大いに期待したい。
取材・文:宮崎新之


