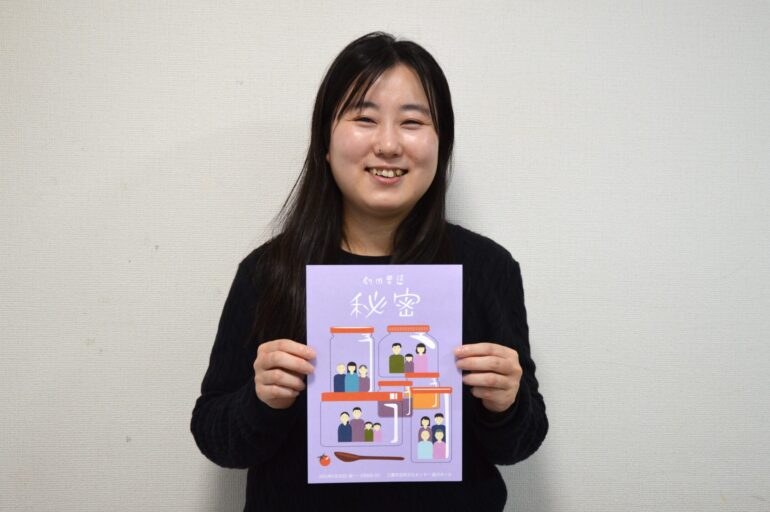
5月30日(金)より三鷹市芸術文化センター 星のホールにて劇団普通『秘密』が上演される。ある地方の、ある家族の、ある日常。一切の説明をそぎ落とした小さく静かな会話劇が伝える、手触りある生活の生々しさ。その類を見ぬ「リアリティ」に、近年ますます注目が高まっている。3年ぶりの再演となる『秘密』は、母親の入院を機に帰省した娘と父親を中心に、そこに生活する人々の姿が全編茨城弁の会話によってあぶり出されていく。リアルを追求した劇作の原動力やこれまでの歩み、キャストも新たに挑む本作の魅力、そして今後の展望…。“普通”では成立できない風景を舞台上に生み出す、劇団普通の “秘密”に迫るべく、作・演出を手がける劇作家・石黒麻衣に話を聞いた。
リアルな家族の風景、その劇作の原動力は?
―『秘密』は3年ぶりの再演です。昨年12月に再演された『病室』や過去作『写真』、『風景』などと同様に本作も「家族」の物語ですが、その執筆の経緯からお聞かせいただけますか?
数年前に家族(母親)が入院をしたことやそれを機に実家に帰省をしたことなど、自分が実際に体験した出来事からイメージを膨らませて執筆をしました。元々「リアルな会話劇をやりたい」という思いが強くあって、それが叶えられる題材として「家族」を選んでいるところが大きいかなと思っています。中でも親戚のコミュニティからの影響は強く、様々な仕事や状況を抱えている人々が一つのところにいる風景を見るのが小さい頃から好きだったんですよね。「大人の話に子どもは入っちゃダメ」という空気もあったので遠くから眺めていたのですが、そういう懐かしい断片的な記憶を振り返って書いている部分があります。
―子ども時代の記憶から着想を得る中で新たに気づくことなどはありますか?
セリフに書いてみて初めて、「あの時親戚のおばさんが黙っていたのはこういうことだったんだな」とかふと気づくことはありますね。場面を再現したくて書き進めるうちに、時を経て真意に触れるような感触があります。自分にとって身近なコミュニティを描くことによって、よりリアリティを追求した作品づくりができるのではないか。そんな思いから家族や親戚など、子どもの頃から知っている風景に着想を得ることが多いのだと思います。
―おっしゃる通り、劇団普通の作品は日常の極めてリアルな瞬間が生々しく描かれていて、自分もその場を追体験しているような感覚になります。あの独特の感触を立ち上げるにあたってはどんなプロセスがあるのでしょう?
日常のなんてことのないささやかな瞬間にリアリティを見出していて、その発見が創作の原動力になっていると感じます。例えば、人が普段の生活を送る上で頭の中で処理している情報量ってものすごく膨大なものだと思うんですよね。「この人の前ではこんな自分」、「あの人と一緒にいる時はこんな感じ」といった風に情報を精査して、話すことと話さないことを選び、いくつもの異なる対人関係や会話を築いている。それって実はすごいことなんじゃないかと思って、なんとか舞台を通じて再現したいという思いがあります。

―なるほど。やはり日常で感じたことを書き留めたりはされているんでしょうか?
全部というわけではないのですが、すぐ忘れちゃいそうなことはiPhoneのメモに書いたりはしています。でも、自分の感じたことや好き嫌いといった感情というよりは、会話や出来事といった単位なんですよね。自分の意識は入れずに、普段の会話をそのままちょこっと残す程度で…。そういう意味では映像的に受信している感触が近いです。その上で「リアルな会話」というものを考えた時に、聞いたことの返事がもらえないまま話が進むとか、突然全く意味のない言葉が挟まるとか、言葉にあらわれる情報が少ないとか、その3つが大きな特徴なのではないかと思ったんですよね。
―確かに親しければ親しいほど、言葉を尽くさないという側面はありますよね。家族はまさにその対象になる気がします。
そうなんです。近しい間柄の人との会話は情報を互いに知った上で話しているから、文字に起こすとすごく少なくなるんですよ。そんな風に一見足りないように見えるものこそがリアルな会話の要素なんじゃないかと考え、それを第三者であるお客さんに見せるにあたって、どのくらい調整したら見ていて楽しくかつリアルな会話にできるだろうっていうのを考えて実験を重ねてきました。
“普通”じゃ成立できない作風を築くまでの道程
―実験というと?
2019年に上演した『病室』に至るまでいろんなやり方を試したんです。シチュエーションだけを決めてほぼエチュードで作った芝居をやったり、調整を全くせず情報がほとんどカットされた状態でやってみたり、逆に今度は脚本を読んだだけで伝わる情報量の会話をやってみたり…。本当にいろんなパターンや方法にトライしましたね。そんなこんなを経て、「よし、このチューニングで行こう」と思って書いたのが『病室』でした。劇団を始める前から書きたかった題材ということもあり、その気持ちのままやってみたら、観客の皆さんからも反応を得られて…。それで、しばらくは他に書きたいこともあるし、この感じでやっていこうと思って今の作風に至りました。
―なるほど! 独自の作風を築くに至るまでに研究に研究を重ねた時期があったんですね。
お客さんの反応に教わったり、感覚を培ったりすることも多かったですね。「ここまで削ぎ落としちゃうと分からなくなっちゃうんだな」とか「これぐらいまでは大丈夫そうだ」とか…。中には感度がすごく鋭いお客さんもいらっしゃって、「これだけ削ってしまったからさすがにわからないだろう」と思っていた会話でも、文脈や背景からほぼ完璧に把握されている方なんかもいらっしゃって、びっくりしました(笑)。舞台に上げてみることで得る気づきも貴重なものでした。
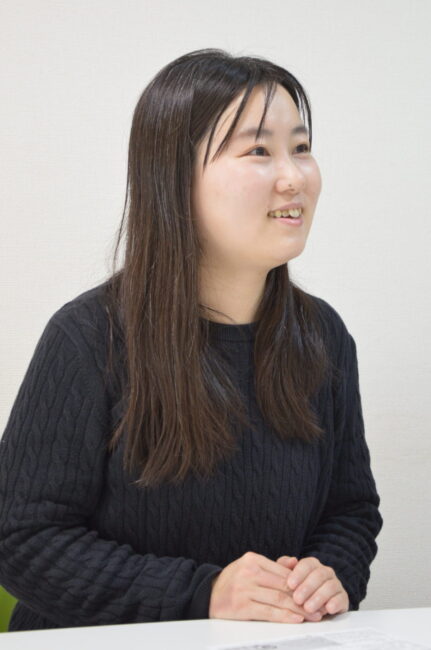
―こうしてお話を聞いていると、劇団普通の演劇はその名に反して全く普通じゃできないことを成立させているとつくづく感じるのですが、劇団名に込めた想いはどんなものだったのでしょう?
これはすごく単純な理由なんですけど、漢字4文字の劇団名に憧れていたんです(笑)。例えば、ナイロン100℃の前身の劇団健康とか大人計画とか…。だから4文字にすることは決まっていて、かつ誰でも読めて親しみのある言葉にしたいなと思って色々書き出しました。当時は企画公演的な流れで始めたこともあって、一緒にやっていたメンバーの女性とその中からどれにしようかを考えて、「劇団普通っていいよね」、「なんか普通がいいね」って。そんな風に決まりました。というのも、第一回公演が『宇宙がこわい!!』ってタイトルだったんですよ。2人とも普通の生活と宇宙という途方もないものが同時に存在していることが怖いなと思っていて。それで、劇団普通『宇宙がこわい!!』でスタートするの、怖くていいかもって(笑)。
―命名の秘話も全然普通じゃないですね(笑)。しかも、当時はまだ今のような全編茨城弁の家族劇ではなかったとか。
そうなんです。様々な創作を経て、旗上げ当初の頃に書いたものに回帰したことに気づきました。2人の企画をとして始めた時は台本を書いたこともなかったので、1年ぐらい台本を書いてお互いに見せ合う機会を設けていたんです。その中で私は姉妹の物語を書いたんですけど、それも言葉の少ない会話劇だったんですよね。標準語ではあるのですが、今の作風にだいぶ近い形のものを書いていました。それに気づいて、”実験”は自分の感性で書いていたものの構造を理解するために必要な過程でもあったのかもしれないと思っています。
普段の生活や人の姿を舞台上で再現するために
―劇団のこれまでの歩みと歴史が紐解かれるようなエピソードをありがとうございます。ここ数年は、上演を重ねる毎にますます注目が高まっていますが、今回の公演で新しく挑戦したいことなどはありますか?
『病室』を再演した際に、再演には再演の難しさとやりがいがあると感じました。今回もその経験を踏まえて、劇場や座組みの変化を活かしながら1から作る気持ちで挑みたいと思っています。俳優さんが変わることで新たな発見も生まれると思うので、初演を観て下さっている方も変化を楽しんでいただけるのではないかなと感じています。初演の王子小劇場での雰囲気とはまた一風違った空間になりそうなので、劇場と作品が起こす反応も楽しみです。演出面では、初演では父親と娘に照準を合わせていたのですが、再演ではその周囲にも焦点を当て、広がりを持った演出にしていきたいと考えています。
―具体的に言うと、どんなアプローチなのでしょう?
「普段の自分以上のことをやる」といった足し算も演劇の魅力だとは思うのですが、普段の日常では「表現をしよう」と思って生活はしていないし、外から見ている第三者に対してではなく、あくまで目の前にいる人に向かって何かしらのやりとりをしていると思うんですよね。劇団普通の演技体はそういった日常と地続きのもので、普段と同じことを舞台上で表現するためにはやはり引き算が重要になってくるので、俳優さんとともにそこを恐れずにやれたらいいなと思っています。日常の一幕がそうであるように、演劇もシーンによって人が入れ替わることで空気が変わる。その変化が大事な見せ場だと思って稽古に取り組んでいます。
―他に、これは劇団普通の稽古ならではだと思う特徴とかありますか?
稽古初めに絵しりとりをやっています。これがすごく面白くて、「分かりやすいリンゴなんて書いたらダメだ!」とあえて難解なものに挑むチャレンジャーもいれば、確実に伝わるものを丁寧に描く人もいたりして、それぞれの個性が出て盛り上がります(笑)。稽古場でのコミュニケーションにおいて心がけていることにも通じるのですが、正解が決まっているものは誰かの目を気にしてしまう心理が働いて楽しめなかったりするので、そういうことはやらないようにしています。純粋に表現ができること、想像力が膨らむことがいいなと思って、大富豪をしていた時期もありました。カードゲームも戦略に人柄が見えて面白いですし、しりとりにせよ、トランプにせよ、必ず1人1人に焦点が当たるのもいいなと思って…。ただ、結構盛り上がっちゃうので、稽古終盤になってくると。「今日は劇の稽古からやろう!」と本題に早めに入るようになっていきます(笑)。

「時の流れ」という変化を作品に託して
―稽古場の和やかな雰囲気が伝わるお話です。最後に、劇団普通が描く今後の展望をお聞かせいただけますか?
最初にお話したように、これまではリアリティを求めて、自分に身近な家族を描いてきたところがあったのですが、今後は自分から近づくことで身近だと感じるものを増やし、描けるものの幅を広げていきたいと思っています。茨城弁での上演も「このスタイルでずっとやっていこう」と決めて始めたものではなく、続けていたら一つの形になったところがあるので、標準語の戯曲の執筆や海外作品の演出なども、自分のスタイルを見つけてチャレンジできたらと思っています。
―石黒さんの劇作において今後どんな新たな変化が生まれるのか、とても楽しみになりました。
『秘密』は再演ですが、同じ作品の中にもここ数年を経た変化が忍ばされると思っています。とくにこの5年はコロナ禍を経て、人々の普段の生活が大きく変わっていくことを痛感した数年でした。「永久に変わらない」と思っていた日常が一瞬にして変わるという経験はとても大きく、大変なこともありましたが、変化に近づくことで可能性の扉が開いた側面もありました。1秒1秒過ぎていく日々に着目していきたいですし、そうした生活者としての積み重ねを今後も作品のリアリティとして出せたらいいなと思っています。
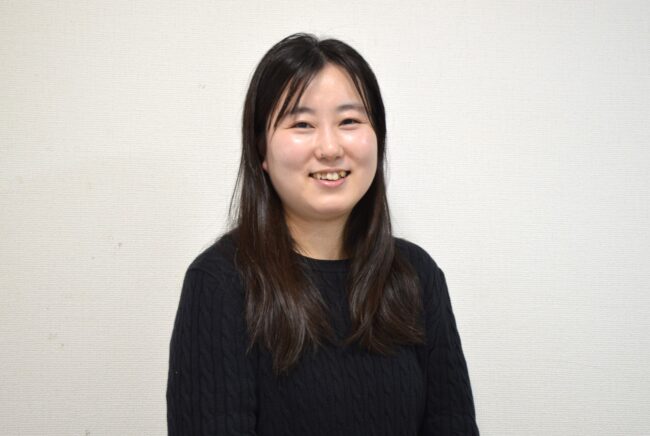
インタビュー・文/丘田ミイ子


