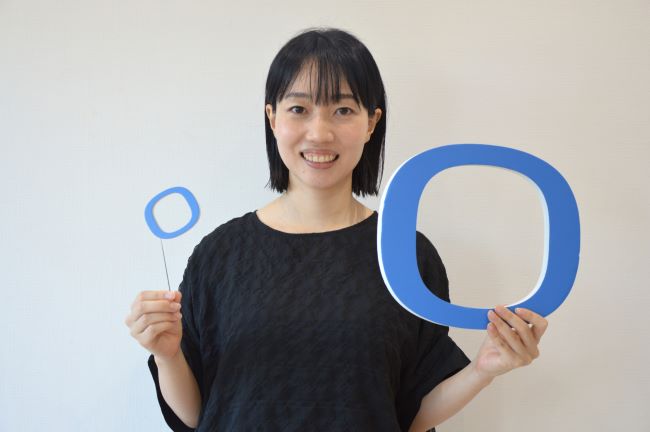
10月23日(木)より下北沢のザ・スズナリにて劇団アンパサンド『デンジャラス・ドア』が開幕する。2023年に爍綽とvol.1として上演され、その後ドラマ化もされた本作はアンパサンド・オフィス・ホラーの代表作にして劇団の代名詞的作品。
舞台はとある職場、「誰も触れていないのに勝手に閉まるドア」を巡って人々が取り返しのつかない事態へと巻き込まれていく様子が、緻密な人間描写に裏打ちされた笑いと恐怖、独特のドライブ感を以て描かれる。
日常のなんてことないひとコマが、些細な違和感が、やがて想像だにしない非日常へ…。劇団アンパサンドの本領が色濃く散りばめられた本作の誕生秘話、創作や上演のこだわりや再演だからこそ叶う見どころや魅力などについて、アンパサンド主宰で作・演出を手がける安藤奎に話を聞いた。
出発点は、日常に見出す“ホラー”な瞬間
――劇団アンパサンドの代表作の一つである『デンジャラス・ドア』、待望の再演です。改めて、本作の執筆の経緯や創作のきっかけからお聞かせいただけますか?
執筆当時の私は事務の職場で契約社員として働いていて、残業をしないと仕事が終わらないという状況が多々あったんです。働きたい気持ちもあるけど、早く帰って脚本を書きたいという気持ちもあって、とにかく時間がないと感じていました。でも、そうやって常に何かに追われながら働いていたからこそ感じることや、パッと思いつくアイデアも結構あって…。「舞台上でオフィスのドアが急に閉まっていくのがやりたい!」と思ったのもその一つでした。
――ドアが急に閉まったり、人が魚になったり、坂道に異次元の境界が現れたり…。ユニークな美術や小道具もアンパサンドの演劇の魅力の一つですよね。
元々、私自身が舞台上で物が動いたりするのを見るのが好きなんです。美術や小道具もふとした瞬間にパッと思いつくことが多いですね。「あのドアが急に閉まったらどうなるんだろう?」みたいな感じで…。そこからどんどん膨らませていったような感じでした。
――なんてことない日常風景から人々があれよあれよととんでもないことに巻き込まれていく…。笑いはもちろん、ホラーパニック的要素の面白さも魅力ですが、そこにはどんな背景があるのでしょうか?
実はホラー作品を昔から特別に好んでいたわけではないのですが、『デンジャラス・ドア』はホラーを書こうと思って取り組んだ最初の脚本でした。オフィスで働いていると、早く帰りたいのに周りに気を遣って帰れなかったり、「もう帰っていいよ」と声をかけられても「大丈夫です」と答えて残ってしまったりする。そういう場面で覚える居心地の悪さや、どうして自分はこうしてしまうんだろうという感覚が、自分の中では怖さに近いものとしてありました。そうした怯えのような気持ちとホラーの相性が良かったんだと思います。
――そうした日常やその会話への着眼点や、人々の気遣いやすれ違いの描き方を含め、アンパサンドの作品は人間の描写力がとても鮮やかですが、人物造形みたいなものはどのように作られているのでしょう?
人物像はキャストの方を見て、「この人がこういう雰囲気や喋り方、性格の役柄をやったら面白そうかも」という発想で書くことが多いですね。実際のご本人を観察してあてはめているわけではないので、いわゆるあてがきではないかもしれないのですが、自分の中で「この人がこうだったら面白いな、こんな様子を見てみたいな」っていう感じで書いています。
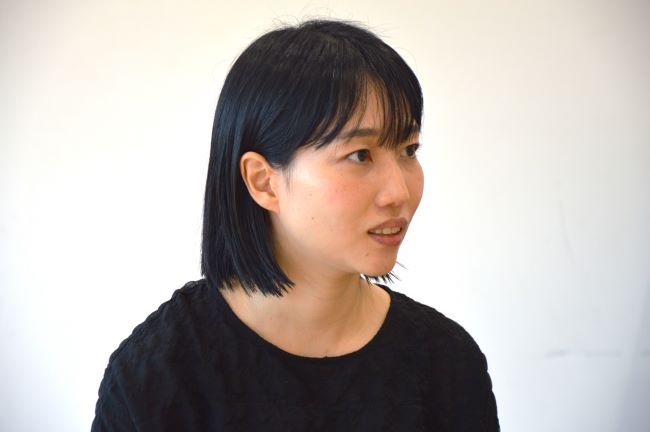
アンパサンド作品に通底する、極めて重要な3分
――『デンジャラス・ドア』は初演の反響を経て、その後ドラマ化もされました。映像と演劇の違いなど、それぞれで意識されたことがありましたらお聞かせ下さい。
ドラマでは監督もやらせてもらったのですが、ドラマの監督を務めるのは初めてだったので新鮮な経験でした。映像と演劇の違いで大きく感じたのは、映像では、画面に映ったものがそのまま真実になるということです。たとえばドアを映せば、それが「デンジャラス・ドア」そのものになる。一方で演劇はもっと抽象的で、同じドアを出したとしても観客の想像がそこに重なっていきます。だから映像では実物にこだわらざるを得ません。舞台は必ずしも本物である必要はなく、ある程度観客の想像力に委ねられる。その違いは大きいですね。
さらにドラマは稽古期間がなく、その分、撮影前の準備に多くの時間が注がれます。俳優が合流するのは撮影に入ってからで、そこから一気に短期間で撮影が終わる。そのスピード感も、舞台との大きな違いでした。
――たしかに、アプローチ自体が異なりますよね。演劇の創作においてはどんなことを大切にされていますか? アンパサンドの稽古場ならではの特徴があれば是非教えて下さい。
とにかくリズムを大事にしています。そのためにテンポを調整することも含めて、意識的に考えていますね。毎公演、「ここ、絶対に大事だ!」っていう瞬間があるんですよね。だいたいトータルで3分くらいのシーンなんですけど…。その3分を本番前にみんなで稽古してから舞台に立つ、というのがルーティーンになっている感じはあります。
――なるほど! その3分がどんなシーンかも含めて楽しみになります。
クライマックスというわけではないですが、全員が一緒にいるところです!

――ヒント、ありがとうございます(笑)。今回はアンパサンド初の再演でもありますが、クリエーションにおいて違いを感じる点はありますか?
いつもは書くところからのスタートなので、最初は台本完成させることで手一杯になってしまうのですが、今回は台本がすでにあるので心の余裕が全然違いますね。初演でちょっと引っかかっていた部分や、「変えてみてもいいかも」と思っていた部分を丁寧に調整できるところが再演ならではの創作の醍醐味だなと思います。あと、今回は新たに藤谷理子さんが出演してくださるので、セリフややりとりも一部変更しています。初演をご覧になった方も、その違いを含めて楽しんでいただけたらと思います。
こだわりで造形する人物と演劇の魅力
――私は個人的にアンパサンドの演劇に出てくる女性の個性がすごく好きで、ヘンテコで可笑しくて笑わされるのですが、みんなちゃんと自分の意地や正義を持っているというか…。安藤さんが女性を描く上で意識していることなどはあるのでしょうか?
これまでとくに意識していたわけではないのですが、最近ようやく言葉にできるようになったことがあって…。私は感情を拠りどころにするのがあまり得意ではなく、感情の揺れを前面に置くことがしづらいんです。だから、人物も感情より、行動や関係のズレにフォーカスして描くことが多い。結果として、そういう描き方がキャラクターの特徴につながっているのかもしれません。
――なるほど! 私は結構役の感情に振り回されるのですが、言われてみたら、アンパサンドの演劇を観ている時は、展開には圧倒されつつも精神は安定して観られている気がします。
もう少し補足すると、特定の役に深く感情移入して書くこともないんですよね。これは脚本上のこだわりというより、自分の人間的な性質がそのまま反映されているんだと思います。感情移入を得意にして、それを強みにしている作家さんもいて、そういう人を見ると羨ましいなと思うこともあります。でも、きっと小説を一人称で書くか三人称で書くかのような、スタイルの違いに近いんだろうなと思っています。
とはいえ、自分の人間的な部分や日頃の感覚は、登場人物に反映されていると思います。作品も人物も「こだわりがある方が面白い」と思っているので。

――安藤さんの一つの作家性を紐解くような、貴重なお話でした。今回は、初のザ・スズナリでの公演でもありますが、その上で何か意識していること、挑戦したいことはありますか?
そうなんです。しかも、劇団アンパサンドは、下北沢での上演自体が初めてなんです。スズナリは「いつかここでやりたい」と思っていた、憧れの劇場だったのでやっぱり嬉しいですね。劇場の特徴を活かしつつ、客席のどこから見ても全体が見やすいように舞台を少し高くしたりの工夫もできたらいいなと思っています。スズナリは、客席を詰めればこれまでの公演より、多くのお客さんが入るんですよね。ただ、私自身がぎゅうぎゅうに詰まっている客席の状態が苦手というのもあって、ぎゅうぎゅうだと感じないくらいの客席にしたいと思っています。それは個人の感覚に寄りますので、ぎゅうぎゅうだと感じたらすみません!
――アンパサンドならではの“こだわり”が滲むインタビューありがとうございました。これまでの作品群はどれも鮮烈で、昨年上演された『歩かなくても棒に当たる』では岸田國士戯曲賞も受賞されました。最後に、そんな安藤さんの劇作家史やアンパサンドという劇団史にとって本作がどんな作品であるかをお聞かせ下さい。
『デンジャラス・ドア』は、無理せず自分の好きなように書けた作品で、アンパサンドらしさが色濃く出ていると思います。
この前、再演するにあたって台本を見返したのですが、自分の書くものには『デンジャラス・ドア』の要素がめちゃくちゃあるなって感じたんですよね。それくらい劇団を象徴するような一作です。今回、初めてアンパサンドをご覧になる方にも楽しんでいただけたら嬉しいです。
インタビュー・文/丘田ミイ子


