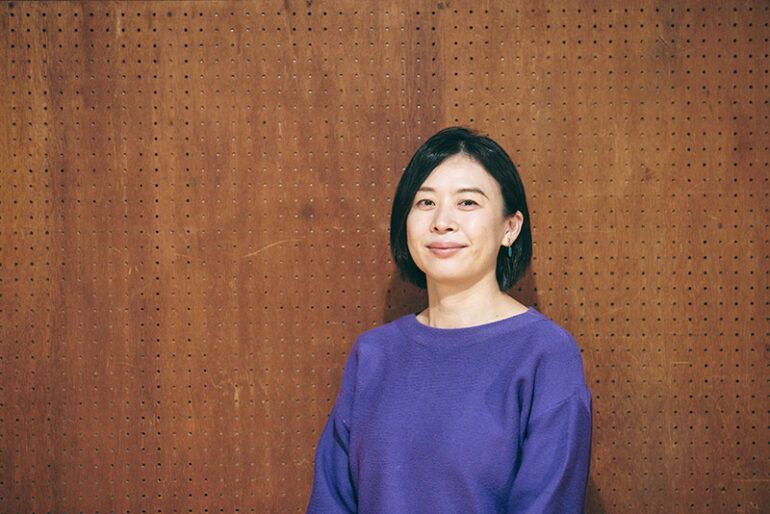
11月24日(木)より西荻窪・遊空間 がざびぃにて、ブス会*『The VOICE』が上演される。約2年ぶりとなる新作公演のテーマは都市計画道路で、その問題の中心に位置する劇場での上演にも注目が集まっている。去る6月には杉並区長選挙に立候補した岸本聡子氏(現・杉並区長)に密着したドキュメンタリー『○月○日、区長になる女。』の撮影・編集・監督を手がけ、話題を呼んだブス会*主宰のペヤンヌマキ。「物語」ではなく「声の集積」を地図に、これまでにはない手法での創作を目指す本公演はブス会*にとっても、ペヤンヌマキにとっても新境地と言えるのではないだろうか。タイトル通り、街の人々へのインタビューを元に、その“声”をひろうところから演劇へと繋げていく、地域密着・接続の伝承型音楽劇。自身の暮らしに起きた問題を創作の糸口に新たな試みへと挑むペヤンヌマキに話を聞いた。
――日々の暮らしやそこに起きる問題への眼差しとご自身の創作活動が接続していくような作品になりそうですが、この企画が動き出すに至った経緯からお聞かせいただけますか?
これまでのブス会*作品も、常に「自分ごと」から物語を着想してはいたのですが、今回はまさに自分の暮らしの半径10メートル内で起こっている道路問題がきっかけでした。自分が長年住んできた場所が都市開発によって立退の危機にあることを知って、それを機に地域の方々との交流が生まれ、市民活動にも参加をするようになって……。これまで知らなかったことが浮き彫りになるような感覚がありました。
――これまでなかった地域との交流が生まれたことで、暮らしも大きく変わったのだとか?
大学進学を機に長崎から上京したのですが、自分にとっての東京は「仕事をする場所」というイメージで、これまでは近所付き合いなんて考えたこともなかったんです。20年同じ街に住んでいても、隣に誰が住んでいるかもわからない状態。そんな生活が当たり前になっていた中でコロナもあって、これまでにない孤独を感じていたんですけど、今回の道路問題をきっかけに本当に多くの交流が生まれたんですよね。こういった運動がないと、近所の方と一致団結する機会ってなかなかないと思うのですが、その中で人の温かさに触れたことで暮らしそのものも大きく変わりました。夕飯のおかずをお裾分けしていただくなんてこともあるんですけど、そういった交流や繋がりに心強さも感じました。災害などの不測の事態が起きた時にも歩いていける場所に知り合いがたくさん住んでいる。近所付き合いが煩わしくて都会にきたような側面もあったとは思うのですが、歳のせいもあるのか、今の暮らしは本当に有難いものだと感じます。
――市民運動が一つのきっかけだったとのことですが、そこで出会った方々はどんなことをされていたのでしょうか?
環境問題に取り組む人もいれば、児童館の廃止に反対運動をする人もいて、自分が知らなかっただけで、これまでも地域各地でそれぞれのテーマ毎に市民活動をしてきた人が多くいたんだと感じました。それらの活動が、前回の区長選挙をきっかけに一つに繋がったような感じがあって……。そこに入っていかなければ、知り得なかったような情報やさまざまな声が次々聞こえてきたんですよね。この街はとても緑が豊かで、自分がここを離れないことの一つの理由になっているとも感じますし、その自然を守りたいという気持ちも強くあります。
――チラシにも、全面に大きな木のイラストが描かれていて、そこに鳥や蝶や人が共に在る様子がとても印象的でした
善福寺川でバードウォッチングしていたら、「鳥がかわいい」というだけで隣にいる人と会話が生まれるんですよ(笑)。そんなさりげない交流も好きだったけど、市民運動を機に近所の人と交流して初めて分かったのは、自分と同じく皆さんが本当にこの土地を愛しているということ、その想いの強さでした。そんな気持ちを共有できるのは嬉しいし、心強いし、一緒に守りたいと思いますよね。
――まさにそういう方々の声をひろって、集めて、演劇にしていくというのが本公演の新たな取り組みだとは思うのですが、ペヤンヌさんご自身の作家性やブス会*のカラーとの両立といった面ではどんな苦労ややりがいがありますか?
ブス会*のテイストとの両立っていうのは、あまり考えすぎなくてもいいのかなと思っていて……。これまでの作品もそうだったんですけど、「自分ごと」としてやっていけば、自ずとそういったものになっていくんじゃないかなと思っています。ただ、ドキュメンタリー要素を演劇に盛り込んでいく作業はすごくデリケートなものなので、葛藤は常にありますね。実際にいる人の声や言葉を演劇にする上で、誰かを傷つけることになってしまわないか、という部分については私自身も演じる俳優も人一倍敏感に取り組んでいるところです。即興でやりたいけれど、決めなくてはいけないことも多い。物語や台本を元にしないという方法自体が初めての取り組みなので、新しいことに挑む時ならではの“産みの苦しみ”を日々痛感しています。
――街の方々の声を元にする上でインタビューもたくさんされていると思うのですが、その中で感じたことはどんなことでしたか?
実際にその人に会って話を聞くことで、表情や佇まいなどから得る情報がこんなに色濃くあるんだと感じました。これは、文字のインタビューを読む時には得られない体感だと感じますし、聞き手によって、話してくれる内容や濃さも変わってくるんですよね。俳優と一緒にインタビューに行った時には、その場で俳優が感じたことを稽古場で共有してもらったりもしています。
――声の元になる人と、その声を代弁する人がいる。そういった形式は、俳優さんにとっても新たな稽古・創作の形なのではないかと想像します
俳優の眼差しや思いやそれを元に切り取った情報は、実際に演劇にしていく中でも大いに抽出されていくと思うので、その個性はすごく面白く、頼もしいと感じています。これまでは、私が感じたものを物語にして、台本として俳優に提示して解釈してもらう、という作業だったけど、それだけでは得られない演じ手の気持ちや考えに触れることができる。そういったことを普段の稽古よりも深く話せているとも感じます。

――都市計画道路沿いに位置する「遊空間 がざびぃ」での上演。この場所で観るという行為も含めて、暮らしが演劇へと、そして演劇が暮らしへと接続していくような体感がありますよね
ドキュメンタリーの上映会もここでやらせていただいたのですが、すごく居心地の良い空間なんですよね。床も壁も手作りの木に囲まれていて、ここで稽古をした時はなんだか風通しがいいというか、いつもの稽古場で流れているものとは違う空気が流れている場所だと感じました。この場所でやる意味っていうのは、すごく大きい。ここがなくなってしまう未来があるかもしれないと考えると、純粋に悲しいし、嫌だなと思います。
――近年のブス会*はわりと大きめの劇場で上演されることが多かったのですが、こういった空間で上演することには前々から展望があったのでしょうか?
大掛かりなものではなく、シンプルに身近にあるものを使ってできる演劇をやりたいという気持ちは前々からありました。規模が大きくなるほど、予算も時間もかかるし、制約ももちろん出てくる。そういった公演にももちろん意味があるとは思っているのですが、創作という観点においては「今やってみたいことを試してみよう」といった感覚でもっと身近に演劇ができたらいいなと感じていたんです。演劇はお客さんに劇場に来てもらって成り立つものなので、どこでやるかということはすごく重要だと常々感じています。劇場との共振というか、この内容だったらここがいいなとか、そういった場との融合が必ずあるんですよね。それでいうと、今回は「この場所でやりたい」という気持ちがまず強かった。そんな思いから発想した企画だとも思っています。
――今回は、向島ゆり子さんの生演奏も見どころの一つですよね。「伝承型音楽劇」と銘打たれていますが、本作を音楽劇でいこうと決めたきっかけはどんなものだったのでしょうか?
向島さんの音楽がとにかく素敵なので、「この空間で向島さんの生演奏を聴きたい」というのがまず純粋な気持ちでした。街に暮らす人の生の声をコラージュしていくと考えた時に、生演奏がマッチするのではないかと感じたことも大きかったですね。向島さんは稽古場に毎日来てくださって、その場のフィーリングやシーンに呼応して音をアレンジして下さっているので、音楽を通して即興の良さを教わっているような感覚にもなります。言葉が溢れるシーンが多い演劇なので、ふと音楽だけになったり、そこに風景が重なるような瞬間があったり、音楽で魅せるパートも作れたらいいなと考えています。ミュージカルともまた違う、新たな可能性を感じています。
――題材への想いや上演に向ける意気込みが伝わるお話の数々でした。最後に、今回の新たな試みを通して感じている、ブス会*やペヤンヌさんご自身の今後のビジョンついてお聞かせ下さい
元を辿れば、私の創作はいつも人に話を聞いたり交流することから端を発していて、言ってみれば、「ドキュメンタリー」が原点なんです。自分の知らなかったことを誰かの声によって知ることができること、その人生を生きてきた人からしか溢れないような言葉。そういったものにすごく惹かれるんですよね。それは、フィクションとして物語を描く時も同じ。これまで会った人から聞いた言葉が頭や心に残っていて、そこからシーンを着想するようなことが多いんです。だから、私が作る作品やブス会*の作風が今後どうなっていくかは、自分の人生にかかっている。この先どんな暮らしや出会いを辿るかによって、演劇も全く違う景色になると思います。今回改めて痛感したのは、私は「自分ごと」として捉えられないものは描き切れないということ。だからこそ、脚本家とか演出家とか、映像か演劇かとかは分けて考えず、「これをやるにはこの方法がいいんじゃないか」って、その都度思いついたものをやっていくスタイルがいいんじゃないかなって。最近はそんな風にも考えています。
取材・文/丘田ミイ子
写真/吉松伸太郎


