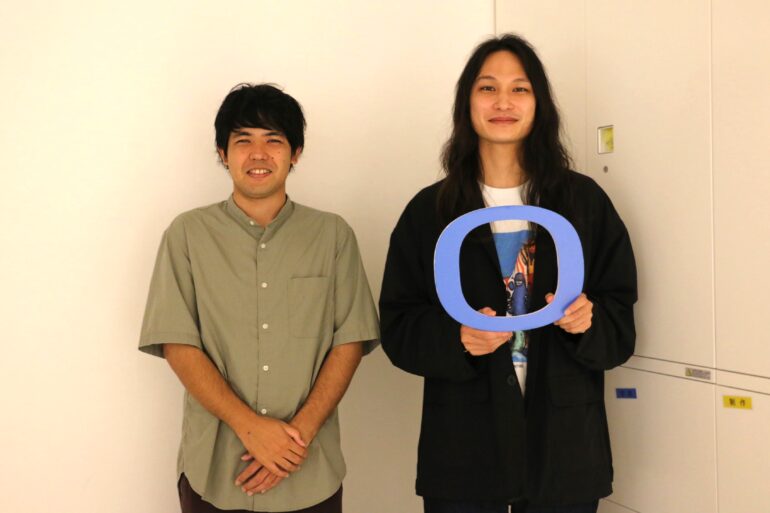
日本の「梅田芸術劇場」とロンドンの「チャリングクロス劇場」が協働する日英プロジェクトにて、脚本家・兼島拓也と演出家・河井朗が初タッグを組み、新作『刺青/TATTOOER』を上演する。
原作の谷崎潤一郎『刺青』は、評判の若手刺青師(ほりものし)である清吉が、長年の願いである「美女の肌に己の魂を彫り込む」機会が訪れて――という物語。本作はそこに着想を得た兼島拓也による書き下ろし新作となる。
英国公演に先がけ東京・アトリエ春風舎で9月20日(金)に開幕する本作について、稽古場にて脚本の兼島拓也、演出の河井朗に話を聞いた。この記事は前後編の【前編】。
谷崎の『刺青』を描くのか、谷崎から『刺青』を描くのか
――本作は谷崎潤一郎の短編小説『刺青』をもとにした作品をつくる、というところから始まったそうですが、どのようにして立ち上げていかれたのでしょうか?
兼島 まずプロデューサーから「『刺青』をもとにした作品をつくりたい」と脚本を依頼されました。最初のミーティングでは、日本とロンドンで上演するうえで、谷崎潤一郎の『刺青』という作品がどれだけ受容されるのか、現代で描いてどれだけリアリティがあるのか、という話になりました。プロデューサーがロンドンで実際に活躍しているタトゥーアーティストの方にインタビューした内容をお聞きしたら、ロンドンにおいてタトゥーは、エンパワメント(力を与えるもの)として受容されている側面があるらしく、この作品でその側面を出すことはできないか、ということが出発点になりました。でも原作を読むとやはりジトッとしていて、「これ、どうしよう……」って(笑)。そこから、どの方向性だったらいけるだろうかと話し合いましたよね。
河井 タトゥーに関して、ロンドンではそういう受容のされ方をされているけど、日本ではそうでもない、というところがあって。実際、銭湯やプールで「刺青が入っている人は入れない」というルールがあったりしますし。横浜の文身歴史資料館(世界の刺青文化の資料などが揃う博物館)でも少し話を聞いたのですが、日本の刺青って着物で隠れるところに彫られるんです。つまり、チラッと見えるのが粋である、という文脈。でもロンドンの人たちはどちらかというとファッションとしての感覚のほうが強くて、見えるところに彫るしポジティブに受け止めている。そこから考えると、日本とロンドンで作品の受容のされ方が全く違うものになるんじゃないか、ということをお話しして。じゃあどうやったら両方の国で上演できるか。そして谷崎潤一郎が持つ“性の消費”みたいな文脈をどう扱えば、現代の日本で、そしてロンドンで受容されるのか。そういう話を初期段階では話しましたね。
――そこからどういう方向に向かっていかれたのですか?
兼島 ひとつ結論を最初に言うと、「ケア」の文脈として読み替えられないだろうか、と考えました。ただそれって谷崎が一番嫌がることだとも思ったんですね。谷崎自身がそういう読まれ方をするとはきっと考えていない。むしろ女性の身体やサディスティックな部分は谷崎自身の欲望として書いているから、それが「ケア」に接続されるのは多分いやだろうなと。一方、ひと口に「ケア」と言っても、現代ではケアの文脈における言説が豊かになってきていて、それを単純化してこの作品に入れ込んでもいびつになってしまいそうでした。それで、じゃあ『刺青』だけでなく、谷崎作品全体から探ってみるのはどうかと考えました。それによって谷崎のテキストによる谷崎批判みたいなことが可能になるなと、作品を読んでいくうちに見えてきたので。それがやれれば、谷崎っぽさも残りつつ、『刺青』で描かれている“密室で自分の欲望のためだけに刺青を押し付ける”みたいなところも相対化できるんじゃないかと思いました。そこから今回の脚本になっていったという感じです。原作は10ページちょっとのすごく短い作品なので、入れ込めることやできることは限られているんですけど、その中での登場人物のキャラクターや立ち位置の変化はけっこう大胆に書いたかなと思います。
――そこはじゃあ、兼島さん一人というよりは、河井さんとお二人で話していかれたのでしょうか?
河井 あともう一人、ドラマトゥルクの蒼乃まを(出演者でもある)の三人で話していきました。蒼乃さんはミーティングの中で『フランケンシュタイン』(イギリスの小説家メアリー・シェリー著)や川端康成の『眠れる美女』を出してきて、当時の女性像やその時代の作家が描く女性というものをピックアップし、どうすればケアの文脈に落とし込めるかということを話しましたね。
――『刺青』だけでいく、というわけじゃなかったのですね。
河井 まず前提として、谷崎潤一郎の『刺青』を描くのか、“谷崎潤一郎”というものから『刺青』を描くのかで話が変わるよねと考えました。それで「“谷崎”を描くことが僕たちは重要なんじゃないか」という話をしました。そのうえで、さっき兼島さんが言ってくれたみたいに、今回は『刺青』だけでなく、谷崎の書いた『春琴抄』(1933年)、『瘋癲老人日記』(’62年)、『痴人の愛』(’25年)、『細雪』(’36年)なんかもピックアップしました。すべてがテキストに入ったわけではないですけど、脚本には『瘋癲老人日記』に出てくる台詞もありますよね。
兼島 はい、けっこう入れ込んでます。どのキャラクターも谷崎の作品をもとにしたものです。谷崎は、あのジトッとした感じがうけているという側面もあると思うんです。人には言えない欲望が凝縮されていたり、読むことで自覚していなかった欲望が触発されたり。そこに谷崎の普遍性があると思います。でもそれを演劇にするとなった時に、そのままやることがいいのか。この作品を日本だけじゃなくロンドンに持ってく時に、もちろんそのまま忠実にやればエキゾチックさやオリエンタリズムという消費のされ方でできると思うんですけど、それを今やることにどれだけの意義が見出せるのかとか、そういうところも関わってくるので。だったら「谷崎を描きながら現代性も入れる」という考えのもと、ケアの文脈や「現代の問題」をそこに見る、みたいなことがやれそうだと思いました。そしたら問題点は通底していることがだんだんわかってきて、「書ける」と思いました。
河井 けっこう長い期間頭を抱えていたけど、そこからは早かったですよね。
兼島 結局ぶつかる問題はずっと一緒、みたいな感じでしたからね。でもさっきのことがわかってからは2~3週間で書けましたね。
河井 余談ですが、谷崎の作品ってロマンポルノ的に映画化されることもけっこうあるんですけど、僕は谷崎の持つ艶めかしさって視覚的な表現の艶めかしさじゃないと思っているんです。あの文体にある。だからそれをちょっとエッチな感じでつくるのは、それこそまた消費につながるんじゃないかと考えました。それをやっちゃったら、2024年に谷崎を描くこと自体が失敗になるなと思いました。

「考える」という行為を、人の間で生み出している
――河井さんはご自身が主宰を務める「ルサンチカ」で、三好十郎の『殺意(ストリップショウ)』や太田省吾の『更地』など、昔の時代に書かれた戯曲を演出してこられています。谷崎の作品も昔書かれたものですが、戯曲の向き合い方は違いますか?
河井 僕は(戯曲の)テキストを「記録」として扱うことがなにかしら可能なんじゃないかと思っていくつかの取り組みをやってきたのですが、僕がこれまで上演した既成戯曲の作家の方は大体みなさんお亡くなりになっていて、生きている人とこうやってつくるのって実は初めてなんです。つまり、つくる過程でこんなふうにコミュニケーションを取ることができなかった。だから「記録として考える」という考え方で演出してきたんですね。その点で言うと、「谷崎」はいったん記録として扱えるのですが、そこに兼島さんという現在進行形の人がいて、綿密な打ち合わせをしながらやっていることは、今までの僕のやり方とは全く違うものになっています。テキストの中身に関しても、昔の戯曲って大体モノローグ(独白)ばっかなんですけど、兼島さんのテキストってそんなにモノローグがなくて、ダイアローグ(会話、対話)ベースで進むんですね。それも僕としては新しいトライです。
――兼島さんは、河井さんとのやり取りにどんなおもしろさを感じましたか?
兼島 朗さん(河井)とまをさん(蒼乃)はこれまでもタッグを組んでこられたおふたりで、ずっと「こうだよね」「そうなんじゃない」「あれはどうなの」みたいなことを話しながら考えるんです。僕は純粋にその感じがすごくいいなと思って見ていました。「考える」という行為を脳内だけでなく、二人の間でやりとりしたり生み出したりしている。僕はどちらかというとずっと一人で悶々とつくってきたので。もちろん、朗さんもまをさんも各々で考えていると思うんですけど、対話でそれが成立しているのを見ると、すごくひらけている感じというか、軽やかな感じというか、いろいろなところに行けそうな感じがありました。この感じは「いいな」だし「羨ましいな」でもあります。すごく魅力的に映りました。
――今回はそこに兼島さんも加わったわけですが、いかがでしたか?
兼島 話していく中で、蒼乃さんの文学やいろいろなことへの知識の深さをすごく感じました。提案やアイデアを投げかければ、蒼乃さんがいろいろ出してきてくれるんだということがだんだんわかってきたので、けっこう無造作に「ただの思いつきなんですけど、こんなのどうですか」とかぼんぼん言う、ということをだんだんやるようになりましたよね。
河井 逆に僕と蒼乃さんも不躾にどんどん言ってただけなんですけれどね。兼島さんが「こういうのどうだろう」と言ったことに対しても、僕は演出的な感覚で「こうなるんじゃないか」って話して、蒼乃さんはテキスト的な文脈で「こうなるんじゃないか」という話をして、三人でドッキングしていた感じです。でも兼島さんもすごい情報量なんです。いろんなことを蓄えているというか……でもそれは蓄えようとして蓄えているわけじゃないとは思うんだけれども、現代の社会に対してなにかしらの問題意識を抱えていて、どうやったらそれが解消できるかということを多分すごく考えている方だなと感じています。それを演劇を使ってクリアにしようとしているのかはまだわからないけど。そんなことはないのかな。
兼島 そうですね。演劇自体でなにかってことは、まだ僕もあまりわからない部分があります。
河井 そうですよね。でも人としてそれをやっている。社会に対して自分がどう立ち向かうか、どう居合わせることができるかをしっかり考えている方だなと思います。あと兼島さんは本を読むのが好きですよね。僕は作品に対して必要な本とかは集中的に読むんですけど、そうじゃない日はゲームしてたりとかするので。
兼島 僕はきっと、読むより買うのが好きなんです。なんか「これ読まないな」とか思いながら買うんですよ(笑)。本を手に入れることが好き。読むことはその次くらい。
河井 そこは一緒だった(笑)。買ってるけど読んでない。兼島さんが教えてくれた本も家にあったんです。ただ読んでない。だから「あれをちゃんと読んでいたら、兼島さんのこの話もわかったんだろうな」と思うことが今回たくさんありました(笑)。
――ちなみに兼島さんが買う本はどんなジャンルですか?
兼島 文学より学術的なものが多いかもしれないです。人文学的な、社会学とか哲学とか。あと福祉の仕事をずっとしていたので、社会福祉の本とかも多い気がしますね。

(後編につづきます)
取材・文:中川實穗


