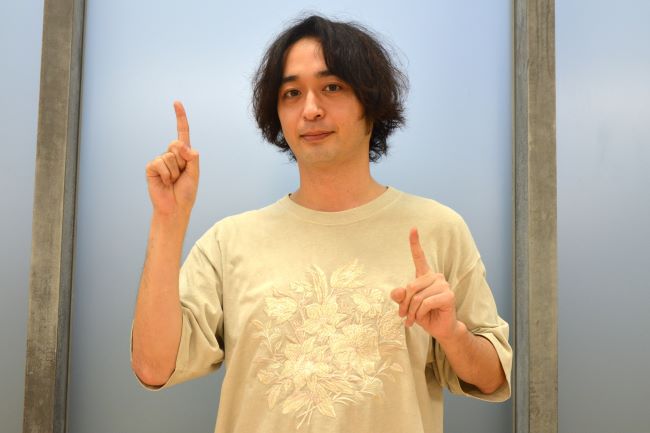
9月4日(木)より下北沢亭にてコンプソンズ大宮企画『猿のハイライト』が開幕する。
本企画はコンプソンズのメンバーであり、俳優の大宮二郎がコントの作・演出を手がける番外公演シリーズで『短編集、石棺』、『映画のパロディ』に続く第三弾目。キャストは大宮のほか、宝保里実、榊原美鳳、佐藤有里子、佐野剛、東野良平、吉田ヤギの7名で、大宮と共演歴のある実力と個性を兼ね備えた俳優陣が集結した。
コンプソンズをはじめ、優しい劇団、やみ・あがりシアター、セビロデクンフーズ、劇団スポーツと劇団内外様々な公演で活躍を見せる大宮であるが、そのユニークな存在感はコントの世界でも顕在。さりげなくも鋭い着眼点が随所に散りばめられた独特の世界観、ズームのイン&アウトや緩急を極めた笑い…。今回はそんな作家としての魅力に迫るべく初インタビューを敢行。これまでの歩み、劇団でコント公演をやる意味、『猿のハイライト』の見どころなどについて大宮二郎に話を聞いた。
お笑いの世界に惹かれ、芸人を目指して
―大宮企画も3作目となりました。今回は初インタビューということで、これまでも遡りつつ、大宮企画やコントの魅力をお伺いできたらと思います。大宮さんはコンプソンズをはじめ様々な劇団の公演でも俳優として活躍されていますが、作家活動においてはどんな歩みがあったのでしょう?
コンプソンズのコント公演で台本を書くことはあったのですが、実はそれ以前の大学在学中からちょこちょこ作・演出をやることがあったんです。コンプソンズのメンバーでもある細井じゅんが当時やっていたコントユニットに参加して書いたり…。というのも、僕は元々お笑い芸人になりたかったんですよ。なので、コントを書く流れは自然というか、むしろそっちの自分の方が先という感じでした。
―コンプソンズ内で個人企画を立てる動きが出るまでにはどんな経緯があったのでしょうか?
2020年頃のコロナ禍に劇団内でちょこちょこzoomミーティングをしていたんです。その中で「しばらくは大きなことができないだろうからミニマムな公演を積み重ねていこう」という流れになって…。そこで最初に手を挙げたのは宝保(里実)さんだったんですけど、コロナ禍以前から金子(鈴幸)からも「大宮が書いて何か企画をやったら?」と何度か言われていた経緯もあって、『短編集、石棺』を宝保企画より1ヶ月前に上演することにしたんですよ。「宝保さんに先越されるわけにはいかないぞ!」と思って、無理矢理先手を打って食い込んだ感じでした(笑)。
―2021〜2022年は大宮企画、宝保企画、星野企画が相次いで上演され、細井さんや鈴木さんも短編を書いたりと、コンプソンズメンバー各々の底力を改めて見せられた思いがしました。そこで大宮さんが選んだのが演劇ではなく、コント公演だった。大宮さんはお笑い芸人になりたかったとのことですが、そこにはどんなきっかけがあったのでしょう?
父親が元々大学の落研に入っていて、家でもずっと落語やお笑いを見ているような人だったんです。その影響で幼少期から日常的に『爆笑オンエアバトル』などのお笑い番組を見て育って…。あと、僕は北海道函館市出身なのですが、地元にこれといった娯楽がなく、レンタルビデオショップでお笑い芸人のDVDを借りて観ることしか楽しみがない状況だったんです。不便だったけど、そこで今の自分自身が醸造されたという感覚はすごくあるんですよね。比較的ナンセンスな笑い、飛躍があるボケ型のコントが好きで、中でも当時夢中になったのがシティボーイズ。あと、今でも折に触れては「影響を受けているなあ」と実感するのは三木聡監督作品の笑いですね。

―三木聡監督はコンプソンズ公演のアフタートークに登壇されていましたね。
そうなんです。でも、あまりに影響を受けすぎていて、目の前にしたら何も喋れなかったんですよね。僕にとって三木監督はそのくらいの存在です。
猿は出てこない『猿のハイライト』?!
―私が初めて大宮さんの作・演出作品を拝見したのはコンプソンズ#9『イン・ザ・ナイトプール』で上演された短編『東京』で、自劇団をモデルにしつつ突拍子もない世界に導かれる読後感がすごく心に残っています。あれはコントという認識では書かれてはいなかったですか?
これを言ったら元も子もない感じになっちゃうのですが、演劇とコントの差って基本的には長さだと思っていて、そう思うと、『東京』は自分の作品の中では長いかな、という実感がありますね。でも、個人的には「笑い」が最終目的地になっていれば何でもコントと言っていい、とも思っていて…。『イン・ザ・ナイトプール』の時に驚いたのは、自分が書いた作品が「コンプソンズっぽい」と言われたことでした。どう書いても金子が書く本公演とは違うものになると思うので、コンプソンズ公演との差別化なども特に考えてなかったのですが、そういう感想が寄せられたのは新鮮でしたね。劇団をテーマにした作品だったからかもしれないですが…。
―たしかにあれはコンプソンズをメタ的に描いた作品だったからそう感じたのかもしれませんよね。前回の『映画のパロディ』ではまた全然違う面白さを感じました。
大宮企画では10分弱程度のコントを何本かやって、最後に全員が出演する少し長めのコントをやる、というのがフォーマットになっています。ただ、他の作品より長くて全員が出るからと言って最後の作品に集大成感があるわけではない、というのも一つの特徴ですね(笑)。
―日常のふとした瞬間、気付けそうで気付けない、ありそうでない瞬間が笑いに昇華されていく様がすごく面白かったです。やはり日常的な気づきを書き込むメモやネタ帳とかってあるんですか?
一応スマホのメモ帳にあるのですが、時間が経って見たら何のことか分からない箇条書きなんですよ(笑)。『猿のハイライト』というタイトルもネタ帳にあった言葉で、2020年くらいのメモだったんですけど、身に覚えもなければ、なんで書いたのかも全く分からなくて…。怖いですよね。猿にハイライトなんてないのに!(笑)。そんなこんな「5年前の自分にどういうつもりだったのが聞きたい」と思いつつ、「でも、なんとなくタイトル感のある語感だな」と思って、真相が謎に包まれたまま決まりました。前回が『映画のパロディ』だったので、シリーズ感も出るタイトルだなと思って…。ネタに関してはある程度みんなが知っているもの、共通認識のところから引っ張ってきてずらす、という手法が伝わりやすくて面白いと思っています。なので、日常の中でも絶妙なラインの共通認識を探していくことが多いです。例えば、「外国の人は魚を生で食べることに驚く」とか…。そこからいかにずらせていけるか。そういうことを考えるのが好きなんですよね。前回は全く映画のパロディをしなかったですし、『短編集、石棺』でも別にそれに絡んだことは何もなかったし、今回も猿は出てきません。意味は観る方に見つけてもらえたらと思います!

―たしかに! そう言われてみれば、『東京』も東京の話じゃなかったですね。でも、なんでだろう、すごく“東京”を感じたんですよね。
そういう感触はちょっと意識しているかもしれません。観終わった時に「そうか、猿のハイライトか」と妙に納得してもらえるというか、そんな読後感みたいなものは目指していますね。過去2回ではコントとコントの幕開に僕と直前のコントに出演していた俳優が楽屋落ち的にちょっと短い会話をして場を繋ぐ、みたいな構成だったんですけど、今回それをやめてまた別の挑戦をしようと思っていますので、シリーズを見て下さっている方も是非注目してもらえたらと思います。
「劇団のコント公演舐められがち問題」に物申す!
―今回もユーモアセンス抜群の、素敵なキャストの皆さんが集結されています。キャスティングの決め手は?
今回は過去に共演をしたことがある俳優さんに集まってもらいました。脚本や稽古への取り組み方にシンパシーやリスペクトを抱ける人。「こんな風にやってくれるだろうな」というイメージが見えると同時に「きっとそれを越えたアプローチを生み出せるだろうな」という人達。大宮企画に出てくれる俳優さんはそういう方ばかりなのですごく心強いです。本も基本的には当て書きで、オーディションではなく「この人に出てほしい」という人に声をかけるスタイルなので、キャストが決まった段階からネタ帳をひっくり返して書き始める感じです。「この人たちと一緒にコントをやるんだ!」とワクワクすると同時に、「演劇やった方が良さそう?」っていう気持ちにもついなってしまうような面々です。みんな芝居がちゃんとできる手練れの方々ばかりなので。でも、演劇やりそうでも演劇はやらない。そこでコントをやる。それも大宮企画の魅力なのかなと思います。
―大宮さんが大宮企画をやる理由、主体的にコント公演を続けることの背景にはどんな思いがあるのでしょうか?
2025年にコンプソンズの本公演がない中で「大宮企画はやらないの?」、「いつやるの?」と周りの人たちが結構聞いてきてくれたんですよね。純粋に嬉しかったですし、「聞いてもらえている間はとりあえず続けよう」と思いました。自分主導で進めなくてはいけない公演は大変ですが、やって損はないし、何より楽しいんですよね。あと、コント公演だからお客さんの層も少し変わり、俳優さんの個性を知ってもらえるきっかけでもあるし、演劇作品では気づけなかった魅力を届けられるチャンスでもある。自分も俳優として活動している分、「俳優のアピールの場でありたい」っていう気持ちも結構あります。あと、やっぱりコントが好きなんですよ。世間的に見た時に劇団のコント公演っていいイメージが持たれないこともあるのですが、そこをちょっとどうにかしたいという思いもありますね。
―他劇団のコント公演を観た時に思うことが色々あると。
観客として観た時に「自分だったらこうするけどな」と感じることはもちろんあります。でも、それ以上に、ちゃんとお笑いのコントをやっている団体が「劇団のコントだ」とネットなどで揶揄されているのを見た時に居た堪れない気持ちになるんですよね。僕は金子鈴幸と蓮見翔が今一番面白い劇作家だと思っているのですが、演劇はもちろん、すごく面白いコントをやっていると思うんです。でも、劇団がやっていると、どうしてもお笑いと切り離されて揶揄されてしまう。そういう風潮に対するカウンターじゃないですけど、世間に対する一つのアプローチというか、妙な正義感もありつつやっている部分がありますね。

―大宮企画を続ける意味、その根幹に少し触れられたような気がしました。最後の大宮企画の今後の展望をお聞かせください。
僕自身は短いコントが何本か観られる構成がいろんなことができて好きなんですけど、
「劇団のコント公演が舐められる問題」について考えた時に、今後はちょっと長めのコントを書く必要が出てくるかなとは思っていますね。それこそ『東京』は40分程の尺でしたけど、やっていることはコントの笑いだったと思うんです。なので、そういう長めの作品をリーチのきっかけにするだとか、そういうことを考えなければいけない段階に来ているかもしれないな、とは思いますね。いずれにしても、新作『猿のハイライト』は今までシリーズでやってきたことが濃縮されていると思いますし、「大宮企画を知ってもらうなら今!」っていう公演になりそうです。かなりの自信作に仕上がりつつあるので、ぜひ楽しんでもらえたらと思います。
インタビュー・文/丘田ミイ子

