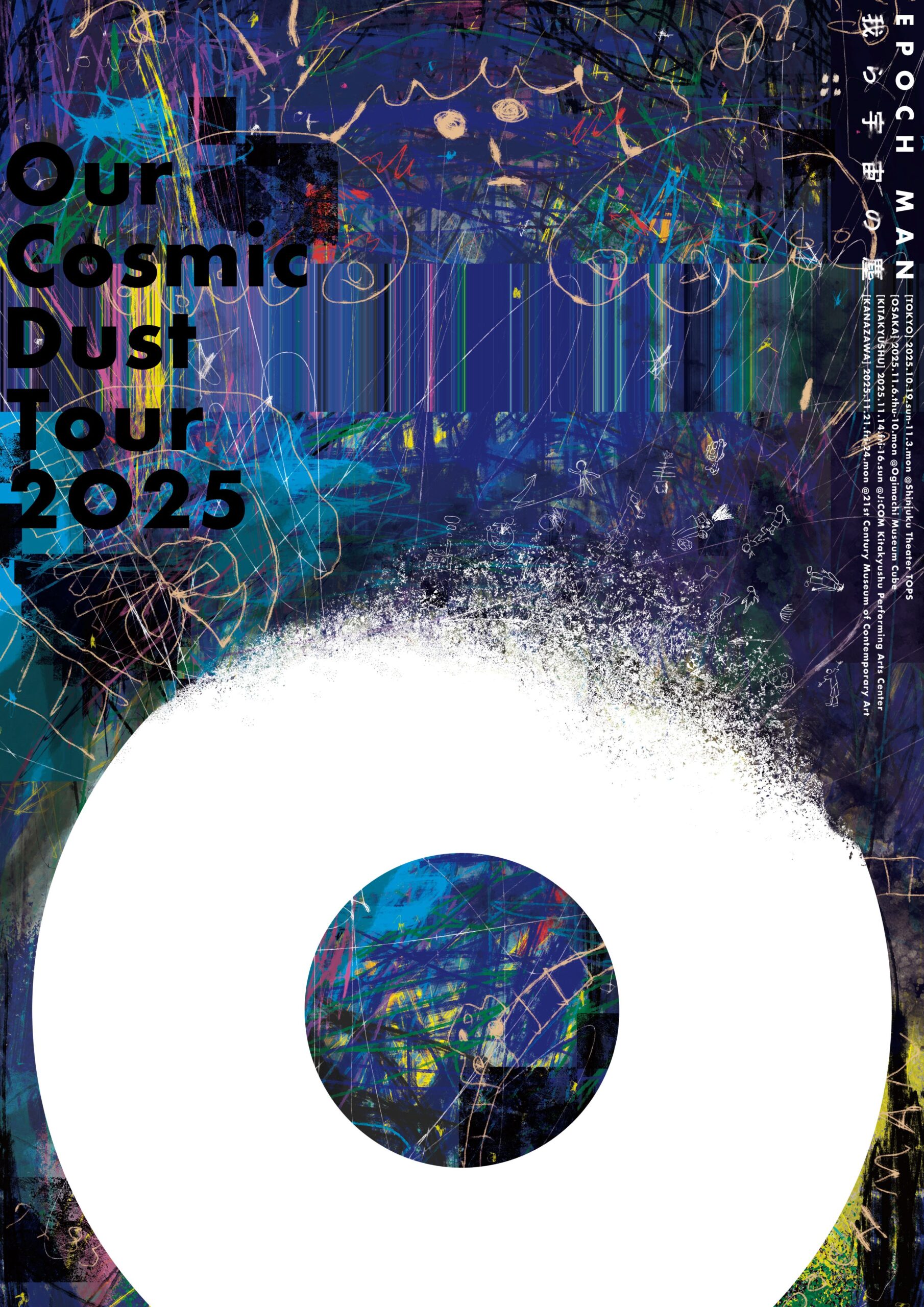EPOCH MAN『我ら宇宙の塵』は第31回読売演劇大賞「優秀作品賞」「優秀演出家賞」「最優秀女優賞」の三部門を受賞。ロンドン版として英語に翻訳し現地キャストで上演すると「長く記憶に残る、新鮮で心温まる作品」(The Review Hub/★★★★★)、「素晴らしい演劇。星々の中で独自の地位に値する」(Theatre & Tonic/★★★★★)など英国演劇メディアから高い評価を得た。初演から2年の時を経て、オリジナルキャストによる再演が決定、まもなく新宿シアタートップスで幕が開く。
人は死んだら、なぜ星になると言われるのか。EPOCH MAN『我ら宇宙の塵』は、小沢道成のそんな素朴な疑問から生まれた物語だ。
その謎を解くヒントを見つけるため、話を聞いたのが、天文学者の阿部新助さん。宇宙の専門家は、「人は死んだら、なぜ星になるのか」という問いになんと答えるのか。宇宙の神秘を愛する二人による思索と対話をお届けする。
宇宙の歴史は終わりと始まりの繰り返しなんです
小沢 まずはこの質問から始めたいんですけど。僕は小さい頃、人は死んだら星になるんだよと言われた記憶があるんですね。それがこの物語を書く発端にもなっていて。阿部さんは、なぜ人は死ぬと星になると言われるようになったと思いますか。
阿部 実はそこは科学的な見地から、ある程度説明できるんですね。そして、事前に脚本を読ませていただきましたが、小沢さんが書かれたことはおおむねその通りなんです。
小沢 合ってるんだ!(笑)
阿部 付け加えるとするなら、人は死んだら星になります。ただ、その星というのは、僕らが普段見上げる夜空の星とは違った意味も持っているんです。
小沢 ネタバレになっちゃうので詳しくは説明できないのですが、今、阿部さんがおっしゃっていることがどういうことかは、作品を観ていただいたらよくわかると思います。なので、気になった方はぜひ劇場へ来てください!
阿部 そもそもですが、宇宙の歴史は終わりと始まりの繰り返しなんです。
小沢 根本的な質問になってしまって恐縮なんですけど、宇宙はどうやって誕生したんでしょうか。
阿部 おそらく聞いたことがあると思うのですが、ビッグバン――簡単に言うと大きな爆発によって宇宙は誕生しました。私たちの間では“最初の3分間”という言い方をしていて。ビッグバン直後の3分の間に水素やヘリウム、リチウムという軽い元素が形成された。それが今から約138億年前のことです。我々の体の60%は水ですが、水には水素が含まれている。その全ては、約138億年前、宇宙が生まれたときの水素が含まれているんです。
小沢 すごい。自分の体に、約138億年前に生まれたものが含まれているなんて。
阿部 そこから、これはまだいつということがはっきりしていないんですが、星が誕生した。本当にざっくり説明すると、宇宙に漂う塵やガスが自らの重力によって集まり、星になる。しかし、さっきも言った通り、まだ宇宙には水素やヘリウム、リチウムといった軽い元素しか存在しません。じゃあ、どうやって我々の体に含まれる鉄分やカルシウムといった元素が誕生したのか。ここで出てくるのが、超新星爆発です。
小沢 超新星爆発というのは、あれですよね。星が終わりを迎えるときに起こる大爆発。
阿部 はい。この超新星爆発によって、宇宙空間に炭素や窒素、酸素、あるいは鉄といった、我々の体をつくっている物質が生まれて宇宙空間にばら撒かれた。
小沢 なるほど。
阿部 そうした物質がまた重力によって集まり、何億年という時間をかけて大きくなって、新たな星となる。ちなみに太陽ができたのは、約46億年前。約138億年の宇宙の歴史は3つの世代に分類されていて、水素をはじめとする軽い元素しか存在しなかった時代を第1世代、超新星により最初の重い元素を獲得したのが第2世代、更なる超新星により複雑な元素組成から誕生した私たちの太陽を第3世代と呼んでいます。
小沢 つまり、命を終えた星が爆発して、そのかけらが再び集まって、また新しい命をつくるということですか。
阿部 そうですね。だから終わりではなく始まりなんです。

地球上の生命は、宇宙からやってきた
小沢 そもそも私たちの命はどうやって生まれたんでしょう。
阿部 地球上のほぼ全ての生命体が持っているDNAは、アデニン、グアニン、チミン、シトシン、略してAGTCという4種類の塩基から構成されているのですが、これがどこから来たのかが最近わかったんですよ。
小沢 どこからですか。
阿部 宇宙です。はやぶさ2という小惑星探査機をご存じですか。
小沢 はい。
阿部 僕は「はやぶさ初号機」から開発メンバーとして関わっていたのですが、この後継機である「はやぶさ2」が小惑星リュウグウから持ち帰ってきたサンプルの中に、アデニン、グアニン、チミン、シトシンを含む20種類以上のアミノ酸が見つかったんです。つまり、生命に必要な原材料は、既に小惑星に存在していた。小惑星から隕石として地球に降り注いだこれらの物質が、地球の生命の起源となった可能性が高いと考えられるわけです。
小沢 僕はてっきり地球上の物質は宇宙へ出ていかないし、隕石のようなすごい勢いをもつものでなければ、宇宙からも地球に入ってこられないと思っていたんですけど、そうじゃないということですね。
阿部 そうですね。常に宇宙から地球に物が降っているし、地球も宇宙に物を出している。そこには何もバリアはありません。
小沢 じゃあ、今も目に見えないだけで宇宙から何かが降っているということですか。
阿部 実は1日に100トンくらいの物質が宇宙から降ってきているのです。
小沢 え! それは目に見える石みたいなものではなくて?
阿部 100トンのうちほとんどは、大きさが0.1ミリメートル以下で、人間の目には見えない暗い流れ星になっています。100トンのうち、3割くらいは地球の表面に落ちていて。今、小沢さんの肩に乗っていたりする(笑)。
小沢 えー。そう考えると、なんかロマンティック(笑)。
阿部 我々はそれを宇宙の塵と書いて、宇宙塵(うちゅうじん)と呼んでいます。
宇宙人とコンタクトできないのは、文明レベルが足りなから
小沢 すごいバカかもしれない質問してもいいですか。宇宙人っていると思います?
阿部 ありきたりの答えを言うなら、我々も宇宙人ですよね(笑)。
小沢 ということですね(笑)。
阿部 我々がこうして存在するということは、他にも存在するということです。
小沢 僕もそう思います。というか、いないなんておこがましいと思っちゃう(笑)。
阿部 じゃあなぜ出会えないのかというと、我々の文明レベルがまだその領域に達していないからだと思っています。宇宙の歴史を1年365日に置き換えると、ホモサピエンスが生まれたのは、除夜の鐘が鳴り終わる午後11時50分頃。宇宙の長い歴史から見れば、人類なんて生まれたばかりの赤子です。宇宙に存在する生命体は、きっと我々より遥かに文明レベルが高い。赤ちゃんが大人と話せないのと同じで、いくら我々がコンタクトをとろうとしても、まだ文明レベルが足りないから交信できないんです。逆に知性を持った他の宇宙人たちは、我々の存在をちゃんと認識しているでしょうね。
小沢 わかってるんですか。
阿部 わかってるし、ずっと見てると思います。いつか我々も文明レベルを同等まで発展させることができたら、宇宙人と会えるかもしれない。つまり、我々次第ですよね。自分たちで戦争を起こしたり環境破壊を続けていたら、いずれ人類は滅ぶ。そうすると、永久に宇宙人に会うことはできない。今、その瀬戸際に立たされているんだと思います。
小沢 今回台本を書くにあたって宇宙のことをいろいろ調べたら、毎秒ワイン500本分のアルコールを放出する星があるという話が出てきて。こんな星があるんだってびっくりしました。
阿部 それは、お酒であるエタノールを放出する彗星が電波観測で分かったというニュースですね。また、長野県の野辺山にある口径45mの電波望遠鏡で観測したところ、星間分子雲という星のもとになるガスと塵があって、そこからメタノール、エタノールなどのアルコールだけでなく、ホルムアルデヒドとか、ギ酸とか、いろんな有機分子が検出されています。
小沢 他にも、たとえばケーキでできてる星とか、砂糖だけでできてる星とか、そういう変わった星ってありますか。
阿部 わかりやすいものでいえば、ダイヤモンドとか? ユレイライトと呼ばれる隕石にはダイヤモンドが含まれていました。あとは鉄でできた小惑星があって、直径220キロぐらいの小惑星なんですけど、今、NASAの探査機が向かっているところで、2029年到着予定です。
小沢 今ですか。
阿部 まさに今です。すでに地球上の鉄資源は枯渇しつつあります。将来、こうした鉱物資源を宇宙から採集してくるということもあるかもしれません。

月は、地球と天体の衝突で飛び散ったかけらでできた
小沢 あと、これも台本に書いたことなので、もし間違っていたらもう顔が真っ青になってしまうんですけど、月は地球に大きな隕石がぶつかって、そのかけらが集まってできたものだというのは本当ですか。
阿部 ジャイアント・インパクト説といって、約45億年前にできたばかりの原始地球に火星とほぼ同じ大きさの天体が斜めに衝突した破片が集まって月は生まれたと言われています。ただ、月の誕生に関しては、近年のスパコンの発達とともにいろんな説が出てきて、ちょっと混沌としている状況なんですね。はっきり言えることは、約45億年前、地球が生まれて間もなく月も生まれた。生まれた直後の地球と月の距離は2万キロくらい。地球は約5時間で自転していたと言われています。
小沢 今は24時間で1回転ですよね。どうしてそんなに違うんですか。
阿部 フィギュアスケートの選手が高速スピンをするときって手をまっすぐ上に伸ばしますよね。あの手を横に広げると、どんどん回転のスピードが遅くなる。腕を横に伸ばした分だけ角運動量が減少するからです。この手の位置が月の位置だと思ってください。今、地球と月の距離は約38万キロ。45億年前から36万キロも広がった分、回転速度が落ちているんです。だから、今は24時間で1回自転するようになった。
小沢 今も月はどんどん離れていってるんですか。
阿部 1年間で3.8cmずつ月が地球から離れていってます。
小沢 寂しくなりますね。
阿部 ただ、太陽系が消滅するのは50億年後。それまでの間に月が地球からいなくなることはないです。月と地球は最期まで運命を共にすることになるでしょうね。
小沢 いい言葉ですね。月と地球は運命を共にする、か。
阿部 逆に言うと、月がいないと地球の自転はこんなに安定しない。月がいたおかげで地球に生命が誕生して生き延びたたとも言えますね。
移住できそうなのは月? それとも火星?
小沢 今回、宇宙のことを調べるまでは、星って浮いているもんだと思っていたんです。でも本当はそうじゃなくて、引力で引き合ってるということなんですよね。
阿部 そうです。すべて引力です。物体というのはみんな引力を持っていて。我々人間も力が微弱だからくっつくことはないだけで、例外ではありません。物体が重ければ重いほど引力は強まる。太陽系の惑星が太陽の周りを回っているのも、巨大な太陽の引力に引きつけられているからなんです。
小沢 月が地球のかけらからできたのなら、環境も似てるんでしょうか。それこそ月にも水があったり。
阿部 月に水はあると言われています。
小沢 そうなんですか。それは初耳でした。
阿部 加水分解すると水になるようなものが鉱物には含まれていて。それを鉱物水と言いますが、月にある水もこの鉱物水と呼ばれるものです。ただ、月には大気がありません。大気のないところで氷の塊を置くと、水になる前に一瞬で蒸発してしまう。
小沢 どうして月には大気がないんですか。
阿部 これもやっぱり引力です。月は小さいから引力が弱い。そのため、空気が捕獲できず、全部宇宙に逃げてしまうんです。
小沢 ここでも引力が関係してくるんですね。じゃあ、今後住めるとしたら火星とか?
阿部 火星は大気圧が地球の数百分の一なんです。地球でいえば高度数10キロの成層圏の大気圧と同じくらいですね。だから、常に宇宙服を着てないと人は生きていくことができません。ただ、火星の地表の中からメタンの氷が発見されており、このことからかつて火星は地球に近い環境だったと考えられます。もし、地球のような環境に戻すことができたら、人間が住める可能性は出てくるでしょうね。なんと言っても、地球から行きやすいですし。
小沢 行きやすいって面白いですね。僕たちからすると、東京から大阪に行くみたいな感覚ですか。
阿部 片道半年です。
小沢 そう聞くと、確かに「行ける」と思っちゃった(笑)。

我々は、宇宙にぽかんと浮かぶ孤独な星ではない
小沢 今日は面白いお話をたくさんありがとうございました。なんだか講義を受けさせてもらっているみたいで、もっとずっと聞いていたかったです。
阿部 僕からお伝えしたいのは、宇宙と地球はつながっているということ。最初にお話しした通り、毎日宇宙から地球に物質が降り注いでいるし、その逆も然りで。地球には火山がありますが、火山が噴火したときのエネルギーは地球上で唯一、地球脱出速度を超える力を持っているんですね。月や火星に小惑星がぶつかって弾き飛ばされたカケラが隕石となって地球に落ちてくるように、噴火によって地球を脱出した物質も月や火星に到達しているはず。太陽系が生まれた46億年前から、これから先も、ずっと宇宙と地球はつながり続ける。我々は、宇宙にぽかんと浮かぶ孤独な星ではないのです。
小沢 僕は星の終わりは始まりなんだというお話に勇気づけられました。いつか地球の命が終わって爆発して、全部が塵になっても、また新しい物質とつながって、星となって、そこで命が生まれる可能性もあるかもしれない。僕たちの命は、この宇宙の中で永遠に営みを繰り返す物質の一つなんですよね。
阿部 まさにその通りです。質量保存の法則がある通り、物質の量やエネルギーの量は保存される。広い視野で考えれば、失われることはないんです。
小沢 面白いですね。人間を物質だと考えると、僕の前にはお父さんやお母さんがいて、その前にはおじいちゃんやおばあちゃんがいる。そうやって何世代にも渡って層がミルフィーユみたいに重なることで地球が膨らんでいるんだと思うと、ちょっと感動します。
阿部 おっしゃる通り、我々人類のすごいところは蓄積できるところなんですよね。過去の記憶を記録として残していける。だから、たとえ僕という物質は消えても、僕の残した記憶は消えずに永遠に残り続ける。
小沢 素敵です。人間は忘れてしまう生き物ですけど、昔の人たちが残してくれた記録が塵となって積もっていくことで、今の僕たちがある。そう考えると、やっぱり全部つながっているんだなと思いました。この物語に出てくるのは、宇宙に興味のある小学生の男の子です。彼は、どんなふうに世界を見つめ、命について考えたか。宇宙に興味のある方だったら、演劇は観たことがなくても楽しんでいただけると思います。ぜひ宇宙に旅をしにいくような気持ちで劇場に遊びに来てください。
取材・文:横川良明
写真:一色健人
阿部 新助
日本大学理工学部航空宇宙工学科 教授
流星・隕石・小惑星・彗星・月・スペースデブリなどが主な研究対象の天文学者。NASA・しし座流星群国際航空機観測ミッションやJAXA・小惑星探査ミッション「はやぶさ」などに参加。チェコ、台湾、ハワイの天文台で計7年間の経験を経て、2013年に日本大学に着任。1999•2006年 NASA航空機観測ミッション表彰、2010年 文部科学大臣表彰「はやぶさ感謝状」、2012年 国際天文学連合により小惑星Shinsukeabe命名、2024年 内閣府宇宙開発利用大賞受賞。趣味は、SNS発信(@Avellsky)、天体観測、ジョギング、ドライブ、隕石収集。座右の銘:「活到老学到老;学問に終わりはなく生きている限り学び続ける」