
京極夏彦の人気小説「百鬼夜行シリーズ」の中でも、特に最高傑作と言われている名作「魍魎の匣」。映画やコミック、アニメなどさまざまな形で展開しているこの作品が、EXILE/EXILE THE SECONDの橘ケンチをはじめ、内田朝陽、高橋良輔、北園涼、高橋健介、紫吹淳、西岡德馬ら錚々たる面々で舞台化される。原作小説は1000ページを超え、まるで辞書ほどの厚さもある超大作。それを演劇でどのように表現していくのだろうか。この日、全員衣裳を身に着けての初めての通し稽古が行われると聞きつけ、緊張感みなぎる稽古場を取材させてもらった。
「魍魎の匣」は、現在長編が9作品発表されている「百鬼夜行シリーズ」の2作目。
昭和20年代末の日本を舞台に、古本屋を営む“京極堂”こと中禅寺秋彦(橘ケンチ)が謎めいた事件を解き明かしていくストーリーだが、民俗学、論理学、妖怪などあらゆる分野の蘊蓄が散りばめられており、一見雑談に思えるようなやりとりも思わぬ糸口になることもある。複雑怪奇で幻想的な原作の空気をどのように舞台に満たしていくのだろうか。
着流しの橘をはじめ、役衣裳に身を包んだキャストが稽古場に揃ってくると、その雰囲気の片鱗が見えてきたようで期待が高まる。通し稽古の前には、暗転個所の変更などの連絡事項がスタッフより伝えられた。台本などにも変更が重ねられ、緻密に作品世界を作り上げられていることがうかがえる。キャストらはストレッチや発声をしたり、談笑したりと和やかで笑顔も見えたが、同時に通し稽古に向けた緊張感も漂っていた。
物語は電車で向かい合う男2人の会話から始まる。何やら怪しげな箱を抱えた男・久保(吉川純広)と、その箱に興味を示す男・関口(高橋良輔)。箱の中から「ほう」という少女の声を聞き、箱の中を見せてもらった関口は久保に羨望の気持ちを抱いてしまう――。関口の短いモノローグだが、箱の持つ何とも言えない魅力を観る者に印象付ける。
場面は変わって、今度は事件の当事者となってしまう女学生の加菜子(井上音生)と頼子(平川結月)の関係性が示される。互いを互いの生まれ変わりだと男のような口ぶりで語る加菜子、そのことに惹きつけられる頼子。口うるさい頼子の母・君枝(坂井香奈美)の言葉は頼子には煩わしく、加菜子の言葉が頼子の拠りどころとなっていた。そして、2人が出かけようとした駅のホームで、加菜子は頼子の目の前で電車に轢かれてしまう。

加菜子は一命をとりとめた。たまたま現場に居合わせた刑事の木場(内田朝陽)は、病院で頼子に状況を尋ねる。木場はいかにも荒くれ刑事といった面持ちで、病院に現れた加菜子の関係者にも威圧的だ。病院に駆け付けたのは、増岡(津田幹土)と名乗る男と雨宮(田口涼)という加菜子の保護者、そして母親の陽子(紫吹淳)。立場を明かさない増岡、名字の違う保護者、そして陽子は元女優と、加菜子には何やら複雑な事情が見えてくる。母親の陽子は、応急処置を済ませたら懇意にしている美馬坂近代医学研究所に転院させると告げた。
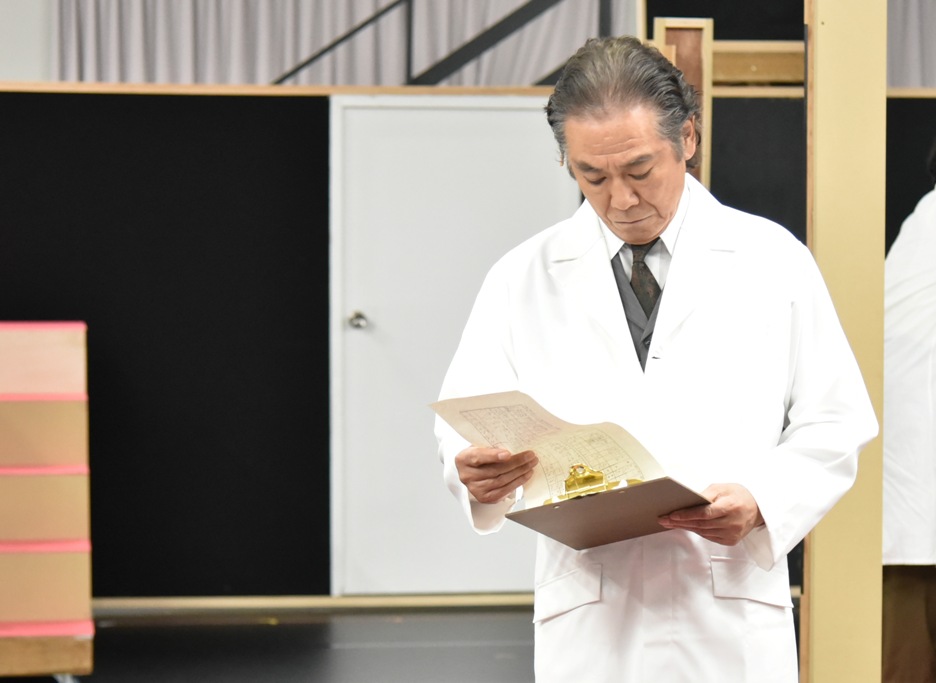
研究所に運ばれた加菜子は、医師の美馬坂(西岡德馬)や須崎(倉沢学)らによって治療が続けられていた。そんな加菜子を久しぶりに見舞う頼子。そこには木場や雨宮、陽子らもいた。頼子に何か語ろうとする加菜子だが、うまく聞き取れない。そして須崎が診察の準備をしていた時、加菜子が忽然とベッドから姿を消す。騒然となる中、須崎が混乱の最中に殺されてしまう。

紫吹演じる陽子の気品ある振る舞いや、西岡演じる美馬坂の曲者感のある態度は、ひと目で役柄の雰囲気が伝わってきてさすがのひと言。舞台上に設けられた可動式の小舞台がいろいろな場面で活用され、2人の少女にまつわる細々としたエピソードを一気に見せていく。小舞台で空間が視覚的に分かれているからこそ、頼子の家、駅のホームなどの目まぐるしい状況変化もわかりやすく、一気に作品世界にのめり込める印象だ。

続いては、冒頭でも登場した久保と関口が出版社で出会う場面だ。久保は新人賞をとった小説家で、同じ小説家である関口に話しかけるが「崩れた文体はわざとですか?」「計算でなければ素人の私小説」と不遜な態度を見せる。そのことを、関口が最近巷をにぎわせているバラバラ殺人を追っている記者の鳥口(高橋健介)に話していると、京極堂の妹・敦子(加藤里保菜)も現れる。敦子もまた、雑誌記者で事件を追っていた。バラバラ殺人の現場である相模湖を歩くうち、3人はまるで箱のような建物に迷いつく。そこに木場の怒鳴り声が響いた。そこは、美馬坂近代医学研究所だったのだ。

そして関口と鳥口が、京極堂こと、中禅寺秋彦(橘ケンチ)にバラバラ殺人についての見解を聞くために、古書店を訪れる。京極堂は着流しで、後ろ姿で舞台上に現れる。鳥口たちが何かを尋ねる前に、バラバラ事件が早期解決しそうにないこと、迷い込んでたどり着いた妙な建物を調べない方が良いと次々に言い含める。驚く鳥口に、京極堂は君のことならまだわかる、と鳥口本人が忘れていたような幼い頃に遊んだ場所まで言い当てるのだった。

待ちに待って登場した京極堂は、実に色気のある振る舞い。セリフも清流が流れるようになめらかで心地よく、どこか人を納得させる独特のトーンがある。決して派手な動きや言い回しをしているわけではないのだが、どこか雅やかな色気が感じられる。
ここまでで、さまざまなピースが観客に提示され、スムーズに小気味よいテンポで物語が展開していく。鬱々とした事件や謎が渦巻いていく中で、鳥口の能天気さや木場の勢いが舞台上を活性化しているように感じられた。

別々の事件が絡まり始める場面でも、小舞台がうまく活用され、別々の場所のエピソードが同時多発的に進行しているさまがダイレクトに伝わってくる。京極堂は動かずとも、あらゆる情報が京極堂に集まってくるさまも実に心地よく、いろいろな人物のセリフから京極堂という男がどのような人間なのかが伝わってくるようだった。
そして、物語が後半に進んでくると、幾重にも重ねられた謎や絡まり合ったエピソードとエピソードが京極堂の言葉によってめくり取られ、解かれていく。それによって、隠されていた愛憎や知るべきではなかった真実、底知れぬ狂気などが明るみに引き出されてしまう。

終盤、京極堂が渦中の中心に乗り込み、言葉で“憑物落とし”をしていく様は、痛快ではあるが異様でもある。触れてしまったものは狂気に駆られ、怯えてしまったものは立ちすくむ。魍魎が形として見えているわけではないが、実体のない魍魎がまさにそこにうごめいているような感覚に陥ってしまうはずだ。

衣裳を身に着けているとはいえ、稽古場でのセリフの応酬だけでこれほどの迫力であれば、実際の舞台と照明の中ではどれほどのものになるのか期待が膨らまざるを得ない。
真実と狂気が渦巻くこの物語の全容を、ぜひその目で確かめ、その体で魍魎に触れて頂きたい。
取材・文/宮崎新之
撮影/大黒屋 Ryan 尚保


