
音楽家・haruka nakamuraの楽曲「every day」から着想を経て、冨士原直也がソーシャル・ネットワーキング サービスのmixiで発表した短編シナリオを原作に、手塚悟が監督を務めた映画「Every Day」。恋人たちのいつもと変わらぬ、けれどもかけがえのない1週間の物語が、今回は朗読劇として上演される。メインキャストは、林遣都×瀧本美織、相葉裕樹×北原里英、赤澤遼太郎×瑞季の3組が日替わりで担当。脚本演出は、「箱庭円舞曲」を旗揚げした古川貴義が務め、音楽は、haruka nakamuraが映画のために書き下ろした楽曲を西寿菜によるピアノの生演奏でお届けする。今回は、相葉に本作の魅力や公演への意気込みを聞いた。
――最初に台本を読んだときはどんな感想を持ちましたか?
「(台本を読んで)生と死という、誰にでも身近にある普遍的なテーマが描かれていて、胸に迫るものがありました。ファンタジーな設定ではあるんですが、他人事とは思えないなと。それと同時に、死が身近だとは分かりつつも、ついつい怠惰な心で日々を過ごしてしまうので、改めて平凡な日常こそが儚くて価値があるものなんだということを噛み締めながら読みました。それから、ラストシーンには驚きました。お客さまも腑には落ちると思いますが、まさかこうなるとは。前情報が何もない状態で台本を読ませていただいたので、意外な展開に感じましたし、とにかく涙が止まりませんでした。」
――映画では、交通事故で昏睡状態の恋人が目の前に現れるというファンタジックな設定でありながらも、非常にリアルな日常を描いていました。朗読劇では、そのリアルな日常を描く難しさがあるように思いますが、それについてはいかがですか?
「日常シーンが多い台本だと思いますが、そうした当たり前のシーンで紡いでいくからこそ、リアリティーが出て、身近に感じやすいんだと思います。もちろん、おっしゃるように、それを朗読として、どう表現していくのかということは、考えなければいけないと思います。稽古をしてみるとまた変わるとは思いますが、台本を読ませていただいた感じですと、そうした日常の中にも笑いやジョークが入っているので、そういう意味では、お客さまも物語に入りやすくはあるのかなとは思います。」
――確かに、「こういう人いるよね」とか「こんなことあるよね」と笑える場面も多くありました。
「そうなんです、「こういうおじさんいるよね」って(笑)。」

――相葉さんが演じる三井については、どんな印象がありますか?
「どこにでもいる青年だと思います。自信がなく、オドオドしていて、不器用で。だけど、憎めないところもある、普通のサラリーマンです。そんな女性慣れもしていない三井が、なんとか告白をして、突然幸せを手に入れますが、特別なことをするでもなく、ただ日常を送っていきます。本当は、その日常はいつなくなってしまってもおかしくないものなのに、その日々はずっと続くものだと、甘えてしまうんですよね。突然、彼女が事故に遭い、ずっと続くと思っていた日常が目の前から消えてしまって、かけがえのないものだったと気づく。どうすればいいんだと分からなくなっているうちに、再び彼女が目の前に現れるのですが、彼の気持ちは痛いほど分かりました。」
――三井は、誰もが共感しやすい役柄ですよね。
「共感できる方は多いと思います。みんな、失敗して後悔して傷つきながらも、前を向いて生きていると思います。その当たり前に続く日々を、特別だと感じてもらえるか。それをどうお届けできるかが、この作品の大切なポイントだと思います。死に向き合う時間が増えた時代だからこそ、皆さまにきっと届くんじゃないかなと僕は思っています。」
――今回、恋人役でタッグを組む北原さんとの共演は、どんなところが楽しみですか?
「初共演なので、北原さんとどのようなカップルが誕生するのかはやってみないとわからないところはありますが、その瞬間、瞬間を大事にお芝居したいです。朗読劇ということで、稽古期間も短いと思いますが、短いからこそ、濃密な稽古ができたらと思いますし、北原さんがどんなものを持ってきてくださるのか、僕が何を北原さんにプレゼンできるのか、僕自身も楽しみにしています。」
――3組が日替わりで出演するというのも楽しみです。相葉さんが先日まで出演されていたミュージカル「ダブル・トラブル」もチームによって全く違う色合いの作品になっていました。
「演者が変われば、空気感も変わるでしょうし、全く別物になると思うので、その違いも楽しんでいただけたら嬉しいです。ペアが変わると全く違うというのは、演じている僕も「ダブル・トラブル」の時に感じました。(「ダブル・トラブル」では)ペアによって会話のテンポもミザンス(舞台上での位置)もアドリブで出てくる言葉も変わるので、その時のライブ感を大事に演じました。今回は、朗読劇なので、また「ダブル・トラブル」とは違うと思いますが、その時に生まれた感情を大切にしてお届けできたらと思います。」
――相葉さんはこれまで、ミュージカルだけでなく、ストレートプレイや声優など幅広くお仕事されていますが、それぞれ演じる上で違いを感じていますか?
「表現方法はもちろん、それぞれ違います。ただ、根本的な“演じる”という部分は変わりません。それに、その作品がどんな題材を扱っているのかによっても変わってくると思います。ファンタジーなのか、普遍的なテーマなのかでも大きく違います。」
――では、朗読劇ならではの面白さや難しさは?
「お芝居をするということに関しては一緒だと思いますが、お互いに顔を見合わせてお芝居をするわけではなく、椅子に座って、台本を持って、台本に目を向けて演じるというのは、特殊な構造です。なので、朗読劇は、お客さまがその“空間”に慣れる時間が必要だと僕は思います。ミュージカルやストレートプレを見慣れていると、やっぱり台本を持って、前を向いて喋る姿には引っ掛かるところがどうしてもある。でも、「朗読劇」というルールを理解できれば、(観客をその世界観に)引き込むことができます。そういう意味では、朗読劇ではいかにお客さまを引き込むかが大事だと思っています。それが朗読劇ならではの難しさでもあり、面白さでもあるのかなと感じています。」

――主人公の三井は、当たり前の日常が突然起きた恋人の事故によって、当たり前ではなかったことに気づきます。「当たり前だと思っていなかったことが、本当は尊いものだと気づく」というのは、コロナ禍の今、ぴったりなテーマだと思いますが、相葉さんもコロナ禍で「当たり前が当たり前ではない」と感じたことはありましたか?
「最初の緊急事態宣言の時には、仕事どころか家から出ることも控えるという状況でしたので、その時は誰しもが考えたことだと思います。それに、今も陽性反応が一人でも出たら舞台は中止となってしまいますが、そうした状況でも僕たちは演劇を届け続けようと努力しています。「当たり前のことが当たり前にできないんだ」と感じるだけでなく、「当たり前だと思っていたことは当たり前じゃなかった」ということを改めて実感しましたし、自分が健康でいること自体が幸せなことなんだと感じていました。」
――演劇界にとっては、非常に難しい状況ですが、一方で、そうしたコロナ禍がきっかけで、舞台映像が配信される機会も増え、良い面もありましたよね。
「配信サービスはすごく増えたように思います。僕自身もファンクラブの方に向けて配信をしたりと伝える手段は増えましたね。」
――では、この作品を通して、お客さまにどんなことを伝えたいですか?
「毎日が平穏に過ぎていくと、退屈を感じたり、面白みがないと思ってしまうことはあると思いますが、そのありふれた日常の中に幸せがあるということを再認識する時間になればいいなと思います。観劇して、家に帰った時、家族や友人や恋人に会った時に、少しでも景色が変わっていたら嬉しいです。」
――ちなみに相葉さんの「ありふれた日常の中にある幸せ」って?
「何でしょうね…仕事をしている時ももちろんですが、あとはお風呂やサウナに入っている時かな。サウナに入って、水風呂に入って、外気浴をしてという一連の流れをすると、命の洗濯をしているような感覚になります。仕事で疲れて帰ってきた時や嫌なことがあった時は、お風呂に入ったり、サウナに入ることでリフレッシュできますし、「幸せだな」と感じて、明日の活力にもなるのでサウナは今、大好きです。」
――サウナで「整う」と言いますしね。
「整っている気になっているだけかもしれないですが(笑)、でも体はすごく軽く感じます。最近は、「サウナドリンク」と呼ばれるものがあって、僕、「アイスボックス」に「オロナミンC」を注いだ「オロックス」という飲み物が大好きなんですよ。サウナから出て、「オロックス」を飲む瞬間は、めちゃくちゃ幸せです。」
――最後に、改めて本作の上演を楽しみにされている方にメッセージを。
「きっと多くの方が、大切な人や友人、家族が、隣にいることが当たり前だとどこかで勘違いしてしまっているところがあると思いますが、それはいつ消えてもおかしくないのだと改めて感じていただけたらと思います。それを実感できたら、きっと日常の景色が変わると思います。僕自身、この作品を読んで、日常の大切さを再認識しました。この作品を観ることできっとこれから先の過ごし方や感じ方も変わってくると思いますので、噛み締めて味わっていただけたらと思います。」
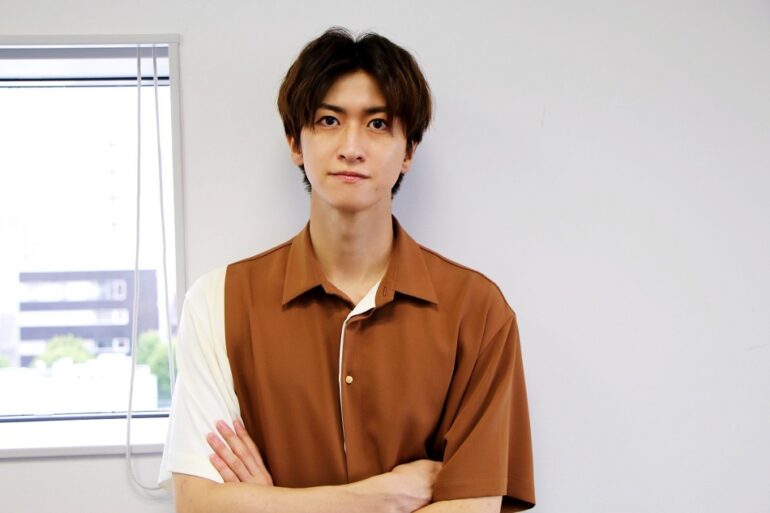
取材・文/嶋田真己


