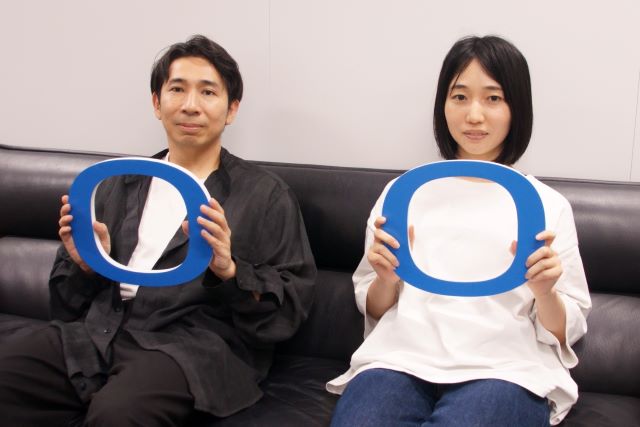
2022年の立ち上げから『サムバディ』、『ホリディ』、『モーニング』と全公演前売りが完売、日常生活や人物へのニッチな眼差しを突破口に独特の劇世界と笑いで観客を魅了する画餅。『されど止まらず』や『地上の骨』(第68回岸田國士戯曲賞最終候補作品)など、人々の営みに生じたズレがやがて予測不能な事態に発展するオフィス劇にファンが急増中の劇団アンパサンド。上演の度にタイムラインを騒つかせる二つの注目カンパニーの創作スタイルとは?それぞれの主宰で作・演出を手がける神谷圭介(画餅)と安藤奎(劇団アンパサンド)に劇作の方法や互いの印象、上演を控える新作『ウィークエンド』(画餅)、『呪信(じゅしん)』(劇団アンパサンド)の構想などについて話を聞いた。
同じ日にテアトロコントに登場!そしてその後に…。
――お二人はこれまでご交流はあったのでしょうか?
神谷 最初は僕がアンパサンドの公演を観に行ったんじゃなかったかな。
安藤 それで、その次の『サイは投げられた』という公演でアフタートークゲストで登壇していただいたんですよね。その時初めて色々とお話させてもらって。
神谷 僕が最初に観た作品のタイトルはなんだったっけ?
安藤 うーんと…なんだっけ…(笑)。たしか何でもいけるようなタイトルだったんですよ。
神谷 なるほど、内容とそんなにリンクしていないんですね。
安藤 むしろなんでもリンクできる、何の作品にもリンクしているようなタイトルだったのですが、なんだったっけ!
――調べたら、たしかにアンパサンドの演劇を表現するような一言で笑ってしまいました。(読者のみなさんも是非ホームページで調べてみてください!)その公演で神谷さんが初めてアンパサンドの演劇を観た時の感想は?
神谷 ちょうど画餅の第一回公演を始める前だったんです。1ヶ月前とかだったかな。めちゃくちゃ面白くていろいろ発見をもらった記憶があります。「もっとこういう会話だけで楽しくしたいな」とか…。それ以降もなぜか画餅の公演やる前にアンパサンドを観る、みたいなサイクルがあり、毎回楽しく拝見しています。
安藤 私は画餅の公演を毎回配信で拝見しています。配信でもすごく臨場感があるから。
神谷 アフタートークでもそんな話をしましたよね。画餅は映像の作品にしていくことを目的に始めたのですが、アンパサンドの演劇も映像での面白さをパッケージできそうな会話劇だなと思って、そんなことを勝手におすすめした記憶があります(笑)。あ、待って。違う。初めて会ったのはそれこそテアトロコントですね。僕がテニスコートで出た時にアンパサンドさんもいたんですよ。思い出した!
安藤 そうだ、そうでしたね!その時はたしか自分の出番が控えていたのでテニスコートのステージが見られなかったんですよ。
神谷 僕も自分の番が終わったら出なきゃいけなくて、楽屋で挨拶だけさせてもらったんですよ。それで次の公演を観に行ったんです!あ、もう一個思い出した。テアトロコントの後、謎のズーム会議に参加しましたよね、僕たち。
安藤 神谷さん、そのこと今思い出したんですね。私はずっと覚えていたけど、「神谷さんはなかったことにしているのかもしれない」と思って、この10分くらい黙って話を聞いていました。
神谷 あははは、闇に葬ったのかと思ったんですね!いやいや、今思い出しました。元々はいとうせいこうさんから「Zoomでコントの会議がしたい」、「若手の人も入れたい」っていうリクエストがあって、それでテアトロコントの小西さんが推薦してくださったんです。最初は何のどんな会はわからず、とにかく喋らなきゃと思っていたのですが、僕以上に訳がわからないまま巻き込まれた状態になっていたのが安藤さんだった(笑)。どうします?この話、やっぱり闇に葬ります?
安藤 葬らなくて大丈夫です!(笑)

画餅とアンパサンド、そのルーツと強みとは?
――オンラインとオフラインの両面から交友の紆余曲折が伺えました(笑)。改めて、お互いの作品や作風などでお聞きしてみたいことなどはありますか?
神谷 アンパサンドの今の作風がどういうルーツでできたんだろう、っていうことは観る度に気にはなっていました。すごく面白いですし、この安藤さん独特の感じはどうやってできあがったんだろうって思いつつ、突然聞くには聞きづらい質問だとも思って…。安藤さんはナカゴーとかは観ていたんですか?
安藤 観ていましたし、ナカゴーさんには出させてもらったこともあって。
神谷 全然似ているわけじゃないんだけど、何かしらの影響があるのかないのかは気になっていました。
安藤 めちゃめちゃあると思います。ナカゴー、城山羊の会、五反田団。影響を受けた演劇を挙げるなら、主にこの三つだと思います。
神谷 そう聞いたら、確かに栄養素という意味では納得。納得はするんだけど、アンパサンドはその3つを合わせた感じでもないし、3つのどれでもないし、その感じがとても面白いですよね。
安藤 うれしいです。影響は受けてきたんですけど、発想自体をもらっているわけではないのだと思います。
神谷 ですよね。多分、その栄養素をもらっている劇作家って結構いると思うんですよ。でも多分こう(アンパサンドのように)はならない。そこが面白いですよね。僕も数少ない演劇からしか影響を受けていないけど、内一つは五反田団です。それ以外の演劇には全く影響受けてないっていうことでもあるんですけど。
安藤 画餅を映像で見て感じているのは、本当に1個のジャンルとして成立しているっていう感覚。映画でもないし演劇でもないけど、その両方でもあるような感じが新しくて面白いなと思って…。演劇ってあんまり新しいことに挑戦しないジャンルという印象があるのですが、神谷さんはそこに真っ向から向かっていく。そこがかっこいいなって。ビジュアルの打ち出し方も斬新!
神谷 ビジュアル撮影は七五三だと思っているんですよ。みんながいいように写真撮ってもらう儀式というか…。俳優さんにとっては、それが画餅に出た甲斐の一つになったらいいなとも思っています。僕が美術系出身だから、友人知人に演劇の畑にはあんまりいないタイプのデザインやスタイリングをやっている人がいるんです。その人たちに声をかけて全力でやってもらっています。
安藤 あんな素敵なビジュアルにしてもらえたら、みんな出たいってなるじゃないですか。だから、「神谷さん、うまいことやったなあ」と思いました。あんなおしゃれなメイク・ファッション・写真撮って欲しいなあって。みんながそう思う気持ちに付け込んで…!(笑)。
神谷 あははは! でも、そういうことが自分の一つの売りになる、していきたいとは思っていますね。例えば、金山寿甲さん主宰の東葛スポーツには、ラップという普段俳優がやらないようなことをあえてステージでやるっていうカッコ良さがあると思うんですよ。それと同じように僕が提供できるのは、ああいうビジュアルを入り口にすることだったり、俳優さんの芝居の力を借りながら「笑い」でできることを探ったり、映像にこだわったり…。そういうことなんですよね。そして、そのあたりがうまくいくことで、自分はもちろん俳優さんにもなるべく何らかの得があったらいいなとは思っています。ビジュアルと言えば、アンパサンドのチラシのイラストは安藤さんが描かれているんですよね?
安藤 そうです。ただ、私の場合は、お金がないから自分で書いただけなので、お金持ちになったら他の人に頼みたいと思っています(笑)。と言いつつ、おしゃれ感覚がないというか、衣装もなんですけど、見た目において「こうしたい!」っていう強い希望があんまりないんですよね。
神谷 そうなんだ。でも、ちゃんとまとまっているようなイメージが勝手にありますけどね。
安藤 「これがいい!」っていうのはないんだけど、「これがいや!」っていうのはめちゃくちゃ多いんですよ。
神谷 すごくよくわかります、その微妙なニュアンス。創作スタイルにも通じる話なのかもしれないのですが、安藤さんと僕が共通しているなって勝手ながら感じるのは、「笑わせようって思っているって思われないようにしよう」という感じ(笑)。感覚っていうか、性格の問題だとも思うのですが、笑いに対しての付き合い方というか距離感というか、そこにシンパシーがあるなと勝手に思っているんですけど…。
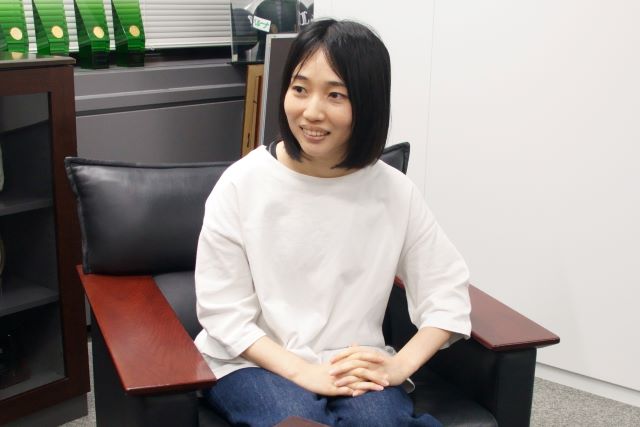
書き方に宿るそれぞれの作家性、「笑い」へのスタンス
――お二人とも自身のカンパニーのみならず外部のコント公演や芸人さんの公演からも書き下ろしオファーが絶えないイメージがあります。カラーは違うのですが、いずれもの作品に通底する会話の可笑しみにはすごく笑わせられているので、創作における「笑い」については是非伺いたく思っていました
神谷 もちろん「笑ってもらいたい」とは思っていますけど、どう言えばいいんだろう、感覚としては少し違うというか…。
安藤 うんうん、うまく言えないのですが、滑っても乗り切れるようにやっていく、みたいな気持ちなんですかね。
神谷 そうそう。「いや、今のはこういうの(笑い)だから」って言い切れるような温度感でずっとやっている感覚はあって…。この間、こういう話を東京にこにこちゃんの萩田くんとも話したんだけど、彼は「滑ったら嫌だ!」ってすごく言うんですよ。そりゃ、あれくらい全力のボケ精神でボケにいったらそうなるのが自然なんだろうけど…(笑)。アンパサンドの作品からもボケ精神は感じるけど、性質は全然違うものだなって思います。
安藤 今、話していてつくづく思ったのですが、私はそもそも「笑い」そのものを考えてないというか、「笑い」の発想で本を書くことを考えてないかもしれません。影響を受けているものもだいたい演劇だし、「笑い」を起点にしたことがないのかも。
神谷 なるほど!意識をして書いているわけでは全くないんですね。面白い。
安藤 そうなんですよ。戯曲として書いた時に「笑い」が生まれているだけで、「笑い」をデザインするとかは全くなくて。だから、「ここ、笑いの真ん中だな」とかそういうセオリーみたいなのは全然ないんです。
神谷 元々は俳優としてやってきて、台本を書こうと思ったのには何かきっかけがあったんですか?
安藤 俳優としての仕事が全くない時にべつに面白いと思っていない劇団のオーディションに行って落ちるって経験をしたんです。意味がなさすぎる行動…。
神谷 それは、迂闊に応募してしまったってこと?
安藤 何かに関わってないと!って、焦って。好きな劇団が限られている上にそのオーディションもしょっちゅうやっているわけじゃないから、面白いと思ってない団体に応募して、向こうも私を面白いと思ってなくて落ちるっていうすごく正当で不毛なことになった時に、「これだったら自分で書いた方がいいな」と。特別な能力がある人が書けるものだって思っていたし、自分が書けるとかは全く思っていなかったんですけど、こうなるくらいなら書こうと思ったんです。
――お二人ともその確立された世界観から書くべくして書く人々という印象があったのですが、そんな経緯があったとは!
安藤 書くことについて私が神谷さんに聞いてみたかったのは、テニスコートの脚本の進め方。あれってみんなで書いて作っているんですか?
神谷 長くやってきた分色々変化はしているんだけど、誰かしらが持ってきた違和感なり、感覚的なものをどういう形でコントにできるかをまず話すんです。それで設定を決めて3人で実践しながら作っていく、みたいな形が多くなりましたね。一旦そういう骨格というかお笑いの構造を作っていくんだけど、それが見え始めたところから、今度はズレさせるっていう構造に変わっていった感じです。ちゃんとしたコントを作る気がどんどんなくなっていったというか(笑)。
安藤 テニスコートのコントと画餅の作品って一緒なわけじゃないのに、どこか通じる雰囲気みたいなものがあるし、テニスコートのコントの中でも「これは絶対神谷さんじゃない人が書いたんだろうな」って思うことがあまりないというか…。その作家性みたいなものってどこからきているのかな、って思っていたんです。
神谷 なるほど。僕個人としては、画餅ではテニスコートとは違うことをかなり意図的にやっているつもりなんですけど、そのあたりの違いや接点について客観的に捉えたことはそういえばなかったかも。
安藤 今、話しながら思ったんですけど、どちらも神谷さんがキャストとして出ているから、神谷さんの雰囲気があって、その共通点で「全く違うもの」ってならないのかもしれないです。作品は違うけど、演者としての個性が接点になっているというか…。
神谷 それはめちゃくちゃある気がします。テニスコートでは僕は文字を起こす側にはあまり回らなかったんですけど、トーンは出ながら作っていくから、そこが共通点になっているのかもしれませんね。

稽古場で重視していること、新作への意気込み
――神谷さんの俳優としての魅力を物語るようなお話でもありますね。稽古の方法についてもお伺いしたいのですが、お二人が稽古場で大切にしているメソッドやセオリーがあればお聞かせください
神谷 俳優さんや座組みの雰囲気によって方法は変わりますね。毎回の手順としては、自分がその俳優さんたちの「人として面白さ」を探る作業から始まっているところかな。そこは、画餅をやる時ならではの方法なのかなって思います。「その人の面白さ」を見つけるために、書いてきたものを読んでもらうっていう作業があります。
安藤 へえ〜!それは具体的にはどういうことをやるんですか?
神谷 台本以前に何となくのイメージで書いてきた散文的なものを元にやり取りをしてもらったり、人を入れ替えてやってもらったり、はたまた稽古外で喋っている時に見えてきたものを取り入れたり…。悪くいうと、悠長ですよね(笑)。でも、「なんか今の面白かったぞ」っていう糸口みたいなものが見つかるのはすごく楽しい。そこから調整していくような感じですかね。安藤さんは稽古初日から台本がほぼ完本しているんですよね。
安藤 そうですね。稽古の中で内容が変わったりはするんですけど、台本は最初から最後まである状態で始めます。過程を見られるのが恥ずかしいので…。
神谷 へえ〜!ちなみに、それはどういう種類の恥ずかしさ?
安藤 「へえ、ここまでしか書けなかったんだ〜」「ふーん、こっから悩んでるんだね」みたいに思われたくないというか、そういうのを見られたくないんです。稽古が始まってから変える分には誰のせいか分からないからいいんですけど(笑)。台本が途中までしかできてないのは完全に自分のせいじゃないですか?だから恥ずかしい!
神谷 あははは!それはもう完全に脚本家としての感覚というか、気持ちですよね。元々俳優としてやってきて、自分で書いてみようって始めてそこまでなるのってすごい珍しいタイプな気がします。
安藤 そうかもしれないです。1本目か2本目を書いたときには、俳優より本を書く方がやりたくなっていたんですよね。
神谷 そこでガラッとり切り替わったんですね。面白いね。書き方とか稽古の進め方はどんな感じですか?
安藤 こういう話をしたいなっていう大枠がまずあって、キャストが決まって、この俳優さんたちだったらどうなるかな?っていうところで書き進めていく感じです。台本が最初からあるのはいいんですけど、小道具が異常に多かったり大きかったりするので大変みたいです。「小道具の稽古ばっかりやってる」って言われる…。
神谷 危険なドアとか首が伸びていくとか、人が消えていくとか魚になっちゃうとかね。あの数々の仕掛けを支えている小道具ですね(笑)。ドラマティックな山場にちゃんとそれが駆使されているし、見どころになっていますよね。
安藤 あの稽古が本当に大変で。徐々に減らしていきたいんですけど、基本的に「小道具でこういうのがやりたいな」っていうのから書いているところもあるので。そこに物語とかお話がついてくるみたいな感じで。
神谷 「これをやりたいけど、どうやったらできるかな」って仕掛けを考えるところからスタートしているんですね。面白そう。作ったことのないものができるのってやっぱり楽しいですから。画餅もそうしていきたいな。普通に考えたらできないことをどうやったら実現できるのかっていうところから探る。いや、面白そう!今度やってみます!
安藤 逆に私は神谷さんの観察眼から始まる創作に憧れたりもします。観察するっていうのは日常そのものを観察すること?それとも俳優さんを観察するっていうことなんでしょうか?
神谷 どっちもありますね。基本的には「違和感」が元になっていて、日常的な「あの時のあの感じって何なんだろう?」というところから発想を得ることもありますし、俳優さんを通じて面白さを発見することもあります。それを合わせて盛り込んでいくような感じです。
安藤 なるほど。私も小道具から徐々に離れていきたいので、神谷さんの創作の方法に近づいていこうかな。
――創作スタイルの違いと影響の交換、とても興味深いお話でした。お二人とも新作の上演が控えていますので、最後に見どころをそれぞれお聞かせ下さい
安藤 「何に影響を受けたんですか?」って聞いてくださることが最近何回かあったのですが、その度にあんまり上手く答えられなくて…。だから、これからは「ホラーに影響を受けました!」っていう方向でいこうかなって思って、最近は『リング』とか『着信あり』とかを積極的に見ていて、それらの影響が存分に発揮されている作品になりそうです。
神谷 後から影響を自ら受けにいくパターン、新しいですね(笑)。しかも、ホラー!
安藤 きっと、そう(ホラーに影響された作品)としか見えないですねって言われる。そんな作品になると思います!
神谷 僕はちょっとまだ着地点は見えてないのですが、今までしたことないことをやってみようと思っています。テアトロコントに出た時の作品を映像化できてなかったから、無理やり1日だけその演目と新作を2本立てでやるっていう日もあるんですよ。自分で言ってといてなんですけど、めちゃくちゃなこと言ったな、ちょっと無理あるなって正直思っていますが、がんばります!
安藤 新しい公演の形ですよね。その内容を見た時、「お、また神谷さんが仕掛けに行ったぞ!」と思いました。楽しみにしています。
神谷 あの、僕、アンパサンドの『サイは投げられた』の台本を買ったんですよ。それを机に置いていたんですけど、そこに印刷されているお馴染みのイラストの黒部分が何かの重みで押されて机に転写されたんです。なので、僕の机にはずっとあの顔があります。最後に聞きたいんだけど、あれってもしかして自画像?
安藤 違うんです!めちゃくちゃそう言われるんですけど。
神谷 安藤さんじゃないんだ。今、2年の謎が解けました!
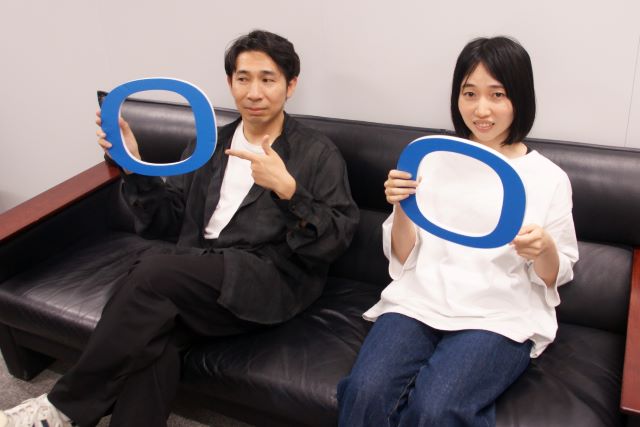
インタビュー・文/丘田ミイ子

