
ロックオペラシリーズ『大パルコ人』
待望の第5弾のテーマは“親バカ”
人気ドラマの脚本家として、話題の映画の監督として、そして個性的な俳優として、などなどジャンルを越え活躍の場を広げ続けている宮藤官九郎。彼が、所属する大人計画の本公演や、自らがその時々でやりたいことを表現する場として劇団内で行っている企画公演“ウーマンリブ”とは別に、PARCO劇場と組んで2009年から続けている“ロックオペラ”公演が『大パルコ人』シリーズだ。
第1弾のメカロックオペラ『R2C2~サイボーグなのでバンド辞めます!~』を皮切りに、2013年のバカロックオペラバカ『高校中パニック!小激突!!』、2016年のステキロックオペラ『サンバイザー兄弟』、2021年のマジロックオペラ『愛が世界を救います(ただし屁が出ます)』と続けてきた今シリーズ、その待望の第5弾はオカタイロックオペラ『雨の傍聴席、おんなは裸足…』だ。今回は離婚裁判を軸にした法廷劇で、テーマは“親バカ”になるという。キャストは阿部サダヲ、松たか子、峯田和伸、三宅弘城、荒川良々、黒崎煌代、少路勇介、よーかいくん、中井千聖、藤井隆と今回も豪華な顔ぶれが揃い、宮藤本人ももちろん出演する。
本格的な稽古にはまだ間があるタイミングで、まさに脚本執筆の真っ最中だという宮藤に作品のヒントを語ってもらった。
――阿部サダヲさんと松たか子さんの顔合わせは、ドラマでも夫婦役を演じられていたばかりのお二人となりますが
実はドラマよりもこの舞台のほうが先に決定していたんですけどね(笑)。まあ、内容的に全然違うものになるのでいいかと思って。そもそも今回はストーリーを考える前に、この二人の顔合わせは決まっていたんですよ。松さんとご一緒するのは劇団☆新感線に脚本を書いた『メタルマクベス』(2006年)以来ですが、とにかくお芝居も歌も素晴らしかったのでいつかまた一緒に何かやれたらなと思っていたんです。阿部くんとは大パルコ人では1作目以来になりますが、他の仕事もいろいろやっているので久しぶり感は特にないかな(笑)。そして、この二人の名前が出た時に“法廷モノ”がやりたいなと思ったんです。法廷って、ちょっと舞台装置っぽいじゃないですか。傍聴人たちはみんな同じ方向を見ているから、よけいにステージみたいですしね。そこに座っている判事とか書記官が楽器を弾き始めたら面白いなと思い、離婚裁判の話がいいかななどと考えて。法廷って本来なら人に言われたくないことやできれば内緒にしておきたいことまで、すべてが公になる場ですよね。相手のイヤな部分とか、暴露とか。それが歌詞になっていたら面白そうだと思いついたのが、たぶん3年くらい前だったと思います。
――ウーマンリブや他の公演でではなく、大パルコ人で法廷劇をやりたいと思ったのはどうしてですか?
大パルコ人では既にひと通りいろいろな芝居をやってきたので。実を言うと、大パルコ人は他の仕事よりも作業がしんどいんですよ。音楽、歌を入れなきゃいけないとなると、台本を書きながら歌詞を書かなきゃいけなくて、それは後回しにできない。その上でもちろん笑いも欲しい。物語も大事。やることがいつもより多いわけです。それでもやはり自分にとっての気持ちのいい正解という完成形にならないと、気持ち悪くて先に進めないのは他の作品とも同じで。そういう意味で、大パルコ人の台本はとても時間がかかるんです。もう第5弾ともなればそうなることはわかっていますから、別にビビってはいませんけどね(笑)。あと、大パルコ人はそれなりに未来の話になっていますけど、これまでのシリーズって一応全部繋がっているんですよ。つまり、これまで同じ世界線で4本作ってきているんです。これ、たぶん誰も気にしていないポイントだと思いますけど。
――それぞれ、バラバラのお話なんだと思っていました
関係ないようでいて、一応同じ世界線にしてあるんです。戦争が起こるという話から始まり、前回は戦争が起こった後の話になっていたりしたので。ま、誰もそこまで真面目に考えて観ていないんでしょうけど。
――スミマセンでした(笑)
それに渋谷の劇場でやっている時は渋谷が舞台でしたし、池袋の劇場の時には池袋が舞台になっていて。そういう、お客さんにとってはどうでもいいことを自分で勝手にルールみたいにしていたら、それが縛りみたいになってきちゃった。あと、これもみなさん全然気が付いてないと思いますが、舞台の設定がこれまで2044年、2022年、2033年、2055年という風に下二桁はゾロ目になっていたんです。
――そこもこだわりだったんですか?
でも誰も気にしていなさそうなので今回はやめて(笑)、ちょっと中途半端に2042年にしてみました。第1弾の『R2C2』の2年前、ということになります。あと毎回、自分にとって何か新しい要素を入れたいとも思っていて。ちなみに前回は“超能力”で、その前は“ヤクザの世界”だったり、“トラック野郎”でいこうとか“ブルースブラザーズ”にしようとか“学園モノ”をやろうとか……。そうやっていろいろやってきた中で、まだやっていないもの、これまでとはまたガラッと雰囲気が変わりそうなものはなんだろうと考えた時“法廷モノ”がいいなと思ったんです。
――ちなみに、宮藤さんは実際に法廷に行ったことはあるんですか?
何年か前に行きました。知らない人の内輪の事情について、まったく関係ない自分がいきなり聞けてしまうという状況がすごく面白くて、そのあとも何回か傍聴しに行っています。1日で3つの裁判を傍聴した時は、それぞれ短い時間でまったく違う案件で。法廷の雰囲気や、その知らない人たちの人生が垣間見えてしまうところが面白くて、嫌いじゃなかったですね。
――その経験も、この物語のきっかけになっている
そういうことですね。
――この大パルコ人シリーズの、ロックオペラならではの楽しい部分というと?
とにかく本番が楽しいです。毎回「このまま、ずっと終わらなきゃいいのになぁー」って思っています。最後はだいたい地方公演のステージで終わるから、そのたびに「ああ、もうこの曲は演奏しないんだなぁ」ってしみじみ思うし。バンドだったらライブをやるたびに演奏できますけど、劇中曲だとそういう機会もないので。役者陣に楽器を生演奏してもらうというのも、大変だけどすごく楽しい。だけど、本当はみなさんが楽器をやりたいですとは別に言っていないわけなので……。
――そこは、宮藤さんの独断でやってもらっているわけですか(笑)
いや、「やれるんだったら、やってほしい」という程度のお願いです。
――ということは、強制ではないんですか?
強制ではないです。だから、たとえば荒川くんとかは演奏していません(笑)。一応、ドラム、ベース、ギターは常にいて、今回はそこに加えてサックスとアコーディオンがいて。さらに必要な音が足りない場合は、音を打ち込みで用意してそれに合わせてバンドで演奏するようにしています。だから全部が全部、100%生演奏とは言えないんですけど。でも「へえ、役者がやってるんだ」とお客さんも思ってくださるだろうし、それは少し“底上げ”にも繋がるのかなとも思っています。
――シリーズが続くことで、たとえば少路さんのように何度も繰り返して同じ楽器に携わることで、演奏が上手くなっていくのも観ていて面白いですよね
そうですね。少路は最近、グループ魂のステージでもサックスを吹いているんで、どんどん上手くなっているんですよ。ここまで上手くなるのもおかしな話だとは思うんだけど。
――でも、ご本人も楽しそうです
楽しいだろうし、やれる曲もどんどん増やしていってて。実は譜面が読めないから、曲ごとに先生に一度演奏してもらい、それを聴いて吹いているんです。
――耳コピだったんですか、大変ですね
大変なんですけど、それなのにどんどん上手くなっているのが面白い。でもそう考えると、芝居のほうは、そこまで集中せずにできるくらいのものになっているのかも(笑)。つまり「楽器をやりながらでもできるでしょ、このくらいの芝居なら」みたいなところが自分の中にちょっとあるのかもしれないです。
――だからさっき“底上げ”って言葉を使ったんですね(笑)。生演奏をプラスすることも、サービス精神の一環だと
そうなのかもしれないです、一生懸命なところもやはり見せたいですからね。
――このシリーズが生まれた背景には、どんなことがあったのでしょうか?
「ロックオペラをやりたい」というところから、確かスタートしたんです。もともとは、グループ魂でそういうことをやっていたんですよ。でもライブハウスで、スタンディングしているお客さんの前で稽古した芝居を見せるっていうのは、あまり良くないなと気づいて。グループ魂はバンド然とした活動にシフトしました。とはいえ、あの感じは楽しかったよなぁと思い続けていたので、こうしてパルコさんと一緒にやろうという機会が生まれたわけです。そしてロックオペラと言うからにはミュージカルとはちょっと違うものにしたいということと、あと作曲を現役のバンドマン、ミュージシャンにお願いするということを、一応自分の中での決まりにしています。それで第3弾からはずっと怒髪天の上原子友康さんにお願いしていますが、これも意外とみんなやってないことなんじゃないかと思うんですよね。つまり劇伴音楽を作る方ではなく、ふだんはバンドで曲を作っている人がすべての劇中音楽を手がけるのは、珍しいんじゃないかなと。
――改めて、上原子さんの作られる曲に感じている魅力とは?
友康さんって引き出しがものすごくいっぱいある人で、ちょっとメタルみたいなのも得意だし、演歌みたいなものも得意だし。だから演劇に合うんじゃないかなと思ったんです。いろいろな音楽に精通していて、その上でやっているのが怒髪天なんだなということを前作、前前作の大パルコ人の音楽をやってもらってみて思ったんですよ。言い方を変えると、ここまでいろいろなことが出来るのに、なんで今まで怒髪天しかやっていなかったんだろう?というか(笑)。それと、ちゃんと笑いどころをわかってくださるところもいいですし、話をしていてもとても融通がきかせていただけるところもいいし。
――お仕事も、やりやすいんですね(笑)
とても劇的な、ドラマチックな曲を書いてくれるんです。だから、本来であれば友康さんじゃない感じの曲だからって他の方にお願いするよりは、友康さんにちょっと頑張ってもらったほうがいいなと思ってしまって。もはや、舞台上に出演していなくても、ほとんど毎回出ているメンバーと同じような存在になっていますね。
――また、今回大パルコ人初参加にして、これが初舞台でもある黒崎煌代さんについてもどういうところに期待されているか、お聞きしておきたいのですが
『さよなら ほやマン』という映画をたまたま観に行ったら、黒崎くんがすごく良かったんですよ。兄弟で、バカの弟の役だったんですけど、台本のセリフを言っているように見えなくて「この子、すごいなあ」って。その後で他の作品も観て「へえ、普通のお芝居もできるんだ!」と驚きました。
――あれは、演技だったんだ、と(笑)
そう、それで今回、峯田(和伸)くんの弟役にしたら組み合わせ的にちょっと面白いな、と考えたんです。しかも、峯田くんより賢く見える役ですから。ただし、これが初舞台だという点だけがちょっと僕には不安なんですよね。まあ、僕が不安なだけで、彼は不安じゃないと思いますが(笑)。
――なぜ不安なんですか?
いや、初舞台の人って大体、思いもよらないことを考えているものなので。「いつから、どこから、本気を出せばいいんですか?」って聞かれたりしますし。
――どういうことを聞かれるかは、稽古になってみないと読めないですしね
意外と、僕の作品が初舞台になる人って多いんですよ。で、あとになって「あの時、全然違うことを考えていたんだ!」ということが発覚するので。それはそれで面白いですけどね。
――「いつから本気出すんですか」というのは、つまり稽古だから、まだ本気を出しちゃいけないと思ったりしているんでしょうか?
そう思っている人もいますけど、僕らの芝居の場合は皆川(猿時)くんみたいに常に本気の人がいたりするから「あそこまで本気出さなきゃいけないの?」と心配になる人もいるみたいです。「別に、みんなあそこまで本気じゃなくてもいいんだよ」って、いつから言おうかなと思ってて。本気は、一回見せておいてくれればいいんですけどね。
――最初にそれを言ってあげておくと、お互いに助かるかもしれないですよ(笑)
そのほうがいいかもしれないですね。「早めに一回本気を出してくれれば、あとは本番でいいよ」って言っておくことにします(笑)。
――では最後に楽しみにしているお客様へ、一言いただけますか
ぜひ、楽しみにしてください!楽しむなとは言ってないので(笑)。僕は毎回「これが最後になるつもりで」と思ってやっているんですがそれには理由があって、つまり毎回ベストのキャスティングができていると本気で思っているからなんですね。その公演に対してのベストになるように、毎回全力で頑張っているわけです。今回も、もちろんそうしています。だからこそ欲が出ないというか、毎回これが最後でもいいやと思える。今回なんか特にそうですね。これだけのキャストが揃ったらもう次はないだろうというくらいの気持ちに、既に今、なっていますから(笑)。
インタビュー&文/田中里津子
Photo/村上宗一郎
スタイリスト/チヨ
※構成/月刊ローチケ編集部 10月15日号掲載分【ロングバージョン】
※写真は誌面と異なります
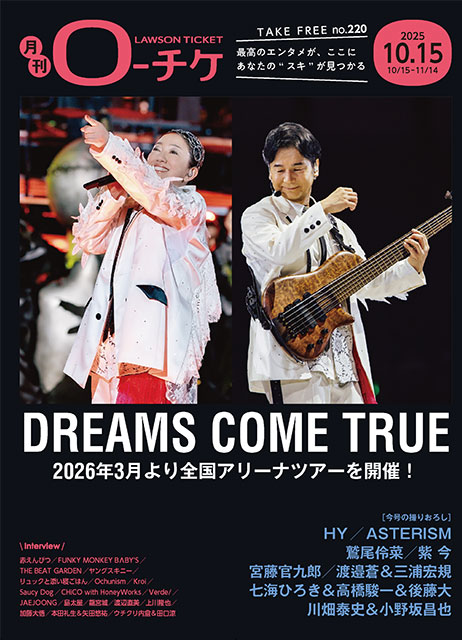
掲載誌面:月刊ローチケは毎月15日発行(無料)
ローソン・ミニストップ・HMVにて配布
【プロフィール】
宮藤官九郎
■クドウ カンクロウ
脚本家、監督、俳優と幅広く活躍。主な脚本作は「不適切にもほどがある!」「新宿野戦病院」など。


