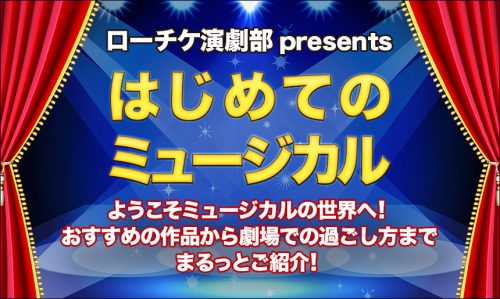年末にロンドン観劇旅行をした。ホリデーシーズンのウエストエンドは通常よりマチネ(昼公演)が多いため恐ろしく効率が良く、正味5日半の滞在でミュージカルを11本も観られてしまった。…さすがにちょっとお腹いっぱいになり、帰国後の観劇がはかどっていない。
●新たな息が吹き込まれた『シャボン玉』
そんなわけで、1月のオススメ公演として挙げた作品のうち、現時点で観られているのは『シャボン玉とんだ 宇宙(ソラ)までとんだ』のみ。主役級の俳優が脇役として多数出演する、ミュージカルファン必見の人気公演だったため、本サイトのメインターゲットであるミュージカル初心者にまではチケットが行き渡らなかっただろうと思う。また、運良くこの公演でミュージカルデビューを飾った読者がいたとしても、特に解説の必要は感じていないに違いない。日本人の日本人による日本人のための、非常に分かりやすく感動的な舞台だった。
そんな舞台となった大きな要因はやはり、豪華キャストにあると言って良いのではないだろうか。ミュージカルの申し子・井上芳雄と元宝塚歌劇団のトップ娘役・咲妃みゆという主演のふたりを、土居裕子や濱田めぐみら数々のミュージカルで主役を張ってきた名優たちが、それぞれに複数の役を生き生きと演じ分ける形で支えた。出演者の多くが、本作を1988年に生み出した劇団・音楽座の出身者か、本作を観劇したことがきっかけでミュージカルの道を志した俳優。力量のある俳優陣が、作品への大いなるリスペクトをもって舞台に立つと、物語にも音楽にも一層の説得力が生まれることを証明するような公演となった。
この公演でミュージカルに開眼したならば、次の一歩は気になった俳優の次回作で踏み出すもよし、日本オリジナル作品を中心に攻めていくもよし、または今も活動を続けている音楽座ミュージカルに足を運んでみるもよし。劇団の作品がプロデュース公演として上演される場合、賛否両論が起こることも多く、実際筆者も劇団側のファンだったりすると、豪華キャストのせいでチケットが取りにくくなることなどに不満を感じたりしないこともない。だが今回のような心あるプロデュース公演ならば、限られたファンだけのものになりがちな名作を広く世に知らしめる機会となると思わされ、歓迎していきたくなったのだった。 ●必見!ロンドンの『Six』と『&Juliet』
●必見!ロンドンの『Six』と『&Juliet』
一本分のレポートだけでコラムを終わらせるのもナンなので、年末にロンドンで観た作品についても少し。今回の主な渡航目的は、ロングラン35年目(!)を迎えて「新演出版」として再オープンしたばかりの、筆者のライフワーク的ミュージカル『レ・ミゼラブル』を観ることだった。だがこの新演出版、日本を含むロンドン以外の場所ではすでに2009年からたびたび上演されているバージョン。作品生誕の地であるロンドンについに上陸するにあたっては、何か大きな手直しが施されるのではないかと思っていたのだが、拍子抜けするほど観慣れた新演出版だった。それでももちろん感動したわけだが、詳細にレポートするほどのことはなかったので省略。それよりも、『Six the Musical』と『&Juliet』である。
『Six』は、日本で言えば徳川家康くらい誰でも知っている歴史上の人物であるヘンリー八世の、離縁されたり処刑されたりした6人の妻たちの物語。といっても時代劇の趣は皆無で、彼女たちが自らの身の上を、スパイスガールズばりに歌い踊りながら面白おかしく語るガールズパワーミュージカルだ。Kポップを思わせる楽曲と振付が耳にも目にも最高に心地良く、早く立ち上がって拍手をしたい衝動に最初から駆られ、体が疼く。鼻の穴を膨らませながら90分間その衝動に耐えていると、面白いだけじゃなくちゃんと時流にも乗った結末が待っていて大興奮&大感嘆!――という作品。この2月からブロードウェイでも開幕するなど、すでに人気は世界各地に広がっている。日本でも、主役級のミュージカル女優を6人集めることさえできれば大ヒット間違いなしなので、一刻も早く翻訳上演してほしい。
『&Juliet』は、シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」の結末に、シェイクスピアの妻がケチをつけるところから始まる後日譚。夫妻で物語を書き換えていくという枠組みの中で、実は死んでいなかったジュリエットがお仕着せではない自分主体の愛を探す劇中劇が進行する。…という粗筋からは想像もできない、面白すぎる展開が次から次へと起こって開いた口が塞がる暇がない上に、既成のポップスをちりばめた音楽も、オリジナリティあふれるキラキラでギラギラの装置・振付・衣裳・照明も震えるほど刺激的で、全部ひっくるめて奇跡!――という作品。こちらについては、その奇跡には劇場構造も含まれることや、ジュリエット役には相当なカリスマ性と歌唱力と若さを兼ね備えた俳優が不可欠なことなどから、日本での翻訳上演は個人的に諦めたので、ぜひロンドンを訪れて体験してほしい。
●本場ミュージカル観劇のススメ
ロンドンのウエストエンドとNYのブロードウェイは、ミュージカルを含む演劇の「本場」「聖地」と称されることも多い、世界最大の劇場街。どちらも、ミュージカル沼に足を踏み入れたならば一度は訪れて損はない場所だ。といっても、日本のミュージカルがダメだと言っているわけではない。ミュージカルの醍醐味のひとつは、感情が音楽に乗って飛んでくることにあると思っている筆者にとって、飛んできた感情の中身が100パーセント理解できる日本語のミュージカルは掛け替えなく尊いもの。にもかかわらず、ちょっと異常なほどのお金をつぎ込んで両聖地に足しげく通っているのは、それだけの魅力があるからなのだ。
分かりやすい魅力として、まずは劇場“街”であることが挙げられる。右を向いても左を向いても劇場!というワンダーランド状態は、日本では決して味わえないものと言えるだろう。また、日本で観た作品をむこうでも観ることで“究極のWキャスト比較”ができたり、むこうで最新作を観て「いつか日本で上演するなら…」と勝手にキャストを考える“妄想キャスティング”を楽しめたりするのも、本場観劇の大きな魅力。これらについては逆に、本場に住んでしまっていては味わえない、日本に根を張るミュージカルファンの特権だ。
そうして大枚をはたいて両ワンダーランドに定期的に赴き、究極のWキャスト比較や妄想キャスティングを楽しむこと四半世紀以上。最近では、分かりやすい魅力の陰にある構造的な違いにも目が向くようになってきた。構造的である以上、日本が本場と同じにはなり得ないことも、また同じになる必要のないこともあるだろう。例えば、俳優の声帯の強さや言語による響きの違いなど。だが一方では、ここは本場にもっと近づけるし、近づいたら日本のミュージカルがもっと面白くなる!と思う要素もあり、そのひとつがオーケストラピットの扱いだ。より多くのミュージカルファンが本場を訪れ、舞台の真下にオケピがあると臨場感が天と地ほどに違う!と訴える人数が増えれば何かが変わるかもしれないと信じて、これからも本場観劇は手を変え品を変え推していきたい筆者なのだった。
文/町田麻子