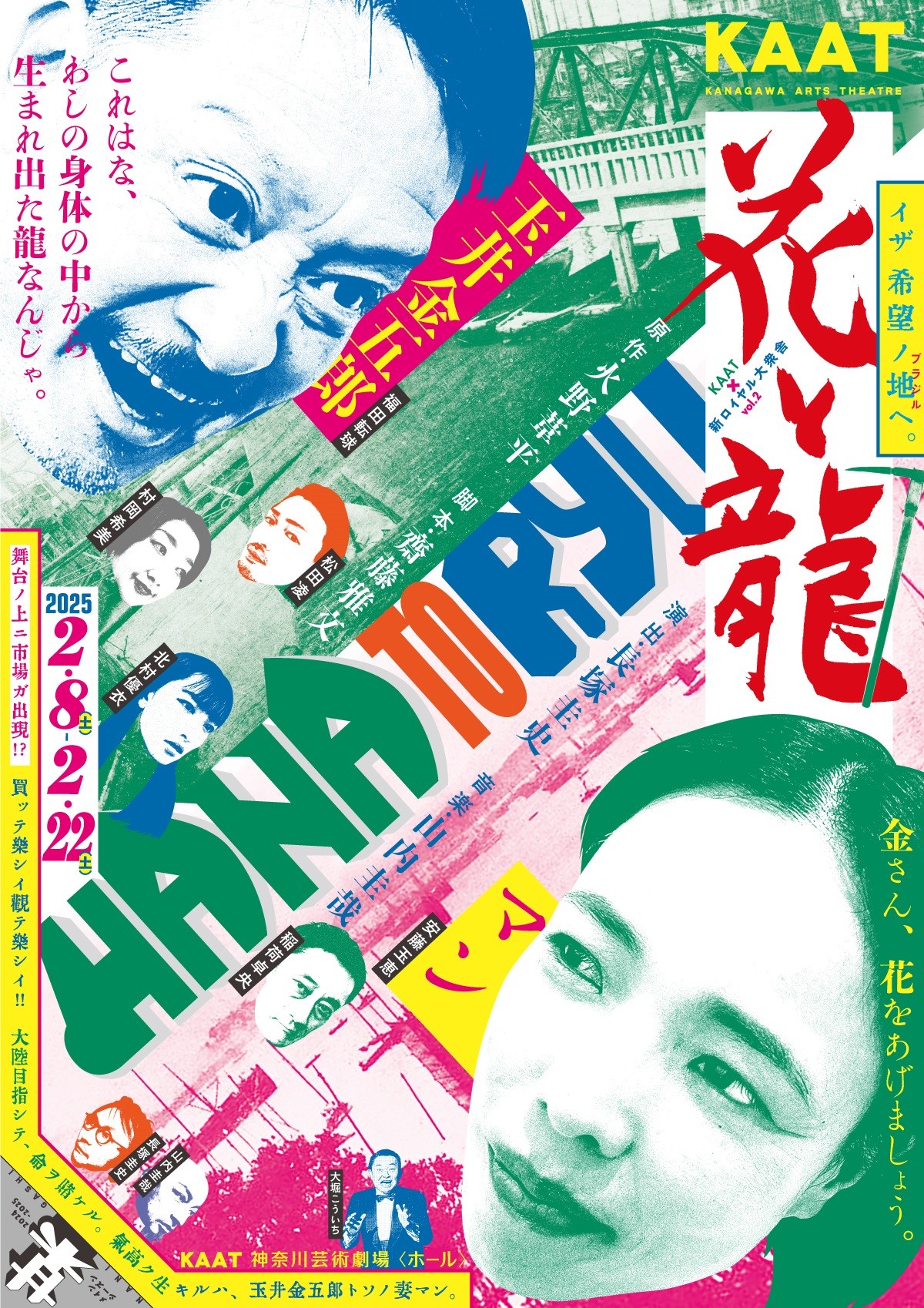――今回KAATと新ロイヤル大衆舎の皆様で作る公演に初めて参加するにあたり、オファーを聞いた時のお気持ちはいかがだったでしょうか
新ロイヤル大衆舎のこれまでの作品を観ていると、ちょっと変化球というか、通常ではない形も使いながら演劇の幅を広げようと活動されているチームだという印象がありましたので、そこに私も参加できるというのは、まずとても嬉しかったです。そして『花と龍』の原作小説を読んでみたら、私が演じるマンという女性がとても魅力的で。元気で強くて惚れ惚れするような、とてもカッコイイ人なので、素直に「やりたい!」と思いました。
――映像でもご覧になりましたか?
映像は最近、稽古に入る前の時点で観ました。高倉健さんや石原裕次郎さんが主演の映画だけでなく、ドラマ版もあって。作品によって金五郎さんの役もそれぞれ違いますし、マン役も全然違うので、自分の参考に、とかではなく、普通に面白く観てしまいました。
――そうやって観た過去の作品と今回の台本とでは、特色が違ったりするんでしょうか
エッセンスはまったく同じだと思います。原作小説が長編だったので、どのエピソードを使うのかなと思っていたら、私自身が読んでいて「ここ面白いな」と思ったところが台本になっていたので、それも嬉しかったです。
――安藤さんと、新ロイヤル大衆舎の4人とのつながりとしては
長塚さんは、大学の1年上の先輩でした。だからその頃から作品は観ていましたけど、劇団が違ったので接点はなかったんです。同じように小劇場で活動していたので、とても身近な存在ではあったのですが。だから不思議ですね。28年くらい経って、今回初めてご一緒するわけなので。大堀さんと山内さんとは共演したことがありますが、転球さんとは今回が初めまして、です。これまでお話したこともなかったんです。この4人の組合せがいろいろな意味でうまいこと、噛み合っているというか。誰かが何か言うと誰かが絶妙にツッコんだり、引き締めてくれたりするんです。
――バランスが良いんですね
本当にそう。グループというものは、4人がちょうどいいんですよって思えるくらいに(笑)。
――3人でも5人でもなく(笑)
4人がいいんです!すごく居心地がいいのはもちろんですが、決してだらっとしているのではなく、前に進めようとする力が強くて。あの4人についていけば大丈夫だろうという、信頼感がありますね。
――その中で唯一、初共演の転球さんと夫婦役を演じるわけですが
事前にお人柄を知らなかったことが、良かったようにも思います。お話したことも食事したこともないから、最初から金五郎として接しているんです。しかも、それで全然、違和感がないという(笑)。稽古場では私の隣の席に転球さんがいらっしゃるんですが、そこでお話している感じと舞台上で台詞を言っている感じが変わらないんです。だからもう私、ちょっと転球さんのことが好きになっています……!
――本当に恋してしまっている?(笑)
どうしましょうね(笑)。でも私がマンでいる限りは、つまり地方公演最終日の3月16日くらいまでの間は金五郎かつ転球さんが好き、ということです。いや、本当に素敵なんですよ、昔の話をするときの少年みたいなところも、本人の自覚はないけれど、ものすごくみんなに慕われていて頼りにされているところも、金五郎だし転球さんだと思います。わざわざ面白いことを言っているわけでもないのに、みんなが自然と寄ってくる感じや、話しかけたくなる感じも。きっと人の好さ、みたいなところがそもそもこの役と近いのかもしれませんね。
――そして安藤さん演じるマンは、どんな女性だと思われますか
マンは、すごく強いんです。そして思いやりと度胸があって、真っ直ぐで。魂がものすごく綺麗な感じがします。タバコを吸っているところも好きなんですよね。
――マンに共感できる部分とか、ご自分と重ねやすいところはあったりしますか
ちょっと心配性なところは、似ているかもしれません。悲しそうな顔をした人がいると「何かあったの?お腹痛いの?大丈夫?」って、すぐ声をかけるタイプなので(笑)。そういうところは似ているのかも、だけどそれ以外は共感というより、憧れに近いかな。ああいう女性になれたらカッコイイだろうなと思うので。それとね、実はマンさんの孫が、中村哲さんなんですよ。
――アフガニスタンなどで長年、人道支援をされていた方ですよね。そうだったんですか!
私、以前から哲さんの本を読んでいて、映画も観て、とても感動しました。
――今回の舞台出演の件とは関係なく?
全然関係なくファンだったので、今回、哲さんのおばあちゃんにあたるマンさんを演じられることも、喜びのひとつだったりします。もちろん、マンさんは自分の孫がそんな偉大な人間になるなんてことは知らなかったでしょうけどね。だけど、哲さんの本には「弱い人を助けなさいという気持ちは、おばあちゃんから影響を受けている」というようなことも書かれていたので。それを想うとすごくゾクゾクってしますし、背筋が正される気持ちにもなります。
――稽古場を覗いたら、舞台上に登場する屋台が用意されていたりして、すごくワクワクしました。KAATでは一部の席で飲食がOKになるそうですけど、現場は大変だろうなと思いながらも、お客さんとしては絶対楽しいだろうなと思っていて
本当ですか、それなら嬉しいですね。屋外ではなく、屋内の劇場で、ですからね。これってある意味、お相撲にも近いのではと思ったりして。お相撲を観戦する時に枡席で食べたり飲んだりできるのは、最高に面白いですから。でも、それはお相撲そのものが、どの場面でも面白いという信頼があるからこそで。私たちの舞台も、そういうものになれたらいいなと思います。目指せ、両国国技館!です(笑)。
――お客様にも楽しむ気、満々で来ていただけたら嬉しいですね。そして、改めて長塚さんの演出については、現時点ではどうお感じになっていますか
稽古で、各シーンを3~4回ずつ返しながら見てくれるのですが、今は探り探りなので、毎回芝居が変わるんです。すると、変えたところについて全部、意見を言ってくれるんです。ということは、すっごく見てくれているんだなと思えるので、とても安心できるというか。
――見てくれていることが確実にわかると、より信頼感が増しますね
そうなんです。しかも、役者と演出家って言葉のやりとりだけではない、もっと感覚的な面でのやりとりがあると思っているのですが。それが今、できている感じがします。その、根っこの感覚みたいなものが信用に繋がるし、大丈夫だと思えるとすごく楽になるんですよね。だから今回、もしかしたら自分が想定していた以上のマンになるかもしれないと思っていて。
――より高みにいけそうだ、と?
より、魅力的になったらいいですね(笑)
――ここで、新ロイヤル大衆舎のメンバー4人の魅力を、安藤さんから紹介していただきたいのですが
一人ずつですか?そうですねえ。まず、転球さんのことは本当に今、もはや好きなので盲目的になっています(笑)。
――愛が溢れちゃう?(笑)
そう、愛が溢れちゃっていますね。だけど、ああいう方はそもそも、人からは嫌われないでしょうね。誰からも愛される方だと思います。山内さんは、現時点ではお髭がピンクで、ちょっとこわもてですからかなりインパクトが強いんですが、その見た目とは裏腹の柔らかいハートの持ち主です。作曲やチラシやグッズのデザインをされていて、マルチなタレントを持っていらっしゃいます。そして、いつも周りを気遣ってくださる方だと思っています。長塚さんは、この4人の中で圧倒的に少年ですね。芸術家という点においては、すごいセンスだと思います。幼さみたいなものと芸術性って完全にイコールだと思うから。劇場のことを考える芸術監督であるという立場を理解してはいても、いざ作品を作るとなった時にはご自身のやりたいことを万遍なく発揮されている。私はそういう少年っぽさって、とてもいいことだと思うんです。初期衝動だから。こういうものを作りたい!とか、これが面白い!と思うことって大事ですからね。

――その熱をずっと持ち続けている
そういう意味では、アーティストとしても素晴らしいことだと思います。大堀さんは、なんであんなに面白いんですかね(笑)。喋っているだけでも可笑しいし、ドアを開けて舞台に出てきただけで、その瞬間みんな笑っているんですよ。そんなことあります?
――普通だったら、そんなことないですね(笑)
どういう生き物なんだろう?と、稽古場で毎回思っています。それが今回の大堀さんは人間の役だけじゃないですからね。猫も演じるんですよ。もう、ますます楽しみです。私は猫の大堀さんと一緒に芝居をする場面もあるので、楽しみで仕方がないです。「日本の演劇を明るく照らす」という、新ロイヤル大衆舎さんのキャッチフレーズがあって、皆さんのキャラクター的に冗談でおっしゃっているように思われそうですが、でも実際のところ本当にそうだと思っています。
――ありがとうございます、皆さんの魅力がとても伝わってきました(笑)。そして、今回の公演では<やさしい鑑賞回>という企画があることにも触れておきたいのですが
ぜひ、触れてください!
――2月19日(水)、さまざまな事情で観劇に不安のある方も気兼ねなく演劇鑑賞ができる回を設ける、とのことで。たとえば真っ暗になる暗転は行わず、大きい音や強い光が苦手な方のために全体の音量を下げたり照明プランを変えたりするそうですね
これまでコンサートなどではあったんですが、演劇ではまだ数少ないそうです。先日、1時間くらいかけて勉強会がありました。声を出したり身体を動かしてしまっても大丈夫ですし、上演途中でも出入りができますし。通常とはきっかけが変わったりするので、私たちもその回のための稽古があるんです。でもこうやって調整をしながら、チャレンジしてみることは大事だと思います。そして当日の様子や結果がどうだったかについては、おそらく日本中の劇場の人たちも聞きたいと思われるんじゃないでしょうか。本当に、この規模で実現できるのはすごいことですので、ぜひこの回にもご注目していただきたいと思っています。
取材・文/田中里津子