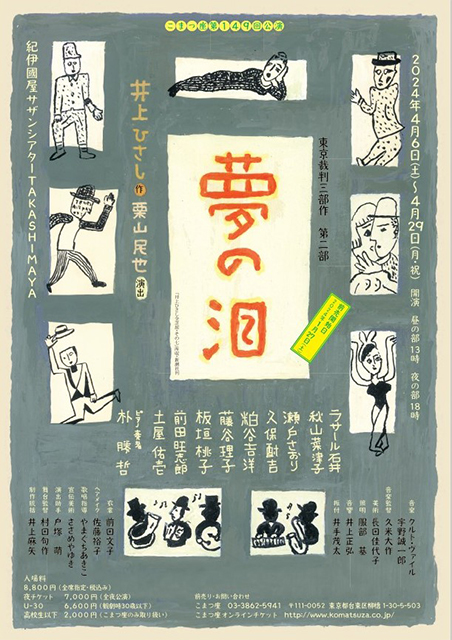井上ひさしが新国立劇場に書き下ろし、戦後の市井の人々の生活を通して戦争と東京裁判を見つめ直した「東京裁判三部作」。そのうちの『夢の泪』がこまつ座で初上演される。その中で、弁護士夫婦の娘・永子を演じる瀬戸さおりと、永子の幼馴染で在日朝鮮人二世の健を演じる前田旺志郎が顔を揃えた。新国立劇場でも今作の演出を手掛けた栗山民也の言葉から、そして井上ひさしの戯曲から、この若い世代が何を受け取りどう表現しようとしているのか。たっぷり話を聞いた。
──稽古の感想から聞かせてください
瀬戸 栗山さんの稽古はとても速いんです。一度やったあと、栗山さんから指示は出るんですけど、そのシーンを繰り返すことはなく次に進んでいく。だから、すごく集中力が必要ですし、次にそのシーンの稽古がきたときに、ちゃんとステップアップしているように自分でつくっていかなければいけなくて。今回もやっぱり過酷だなと思いながら稽古しています(笑)、どうですか?
前田 僕は栗山さんは初めてですけど、本当にむちゃくちゃ速くてポンポン進んでいきますし、指示の量がかなり多いんです。寝る直前まで復習・予習をしているんですけど全然時間が足りないくらいで、その指示の種類も、セリフの音のこと、動きのこと、その役の心情のことと、いろいろあって。それを自分で一本に繋いで一人の人物にしていくのが、楽しいけど大変だなと。
──その栗山さんが求めているものは、例えばどんなことですか
瀬戸 終戦直後の話なので、今の私たちにはない感覚がたくさんあるんです。戦争中とは価値観が180度変わった衝撃や、今日明日を生きることだけで精一杯だというのは、やっぱり自分たちにはなくて。とくに私が演じる永子は、コロッと変わった世の中や大人たちにたくさんの疑問を持ってそれを曖昧にしないから、「わからない」「なぜ」と大人に尋ねるたびに衝撃を受けていく。その一つひとつが本当にその場で受けた衝撃でないと栗山さんに見抜かれるので、もっともっと濃くしていかなきゃいけないなと思っています。
前田 僕が演じる健は二世の在日朝鮮人で、永子と幼馴染で同じ街で暮らしてきたけれども、ここが自分の母国ではないという違和感や、朝鮮に戻りたいという気持ちがあるので、ほかの皆さんとは佇まいや空気感、喋り方に、ちょっと異質な感じが出ないといけないというのが大きくあって。資料を読んで勉強はしてますけど、それを反芻して考えてセリフを言うのではなく、もっと深いところに落とし込んで体に染み付いた状態にして、セリフを言うと同時にそのイメージが広がるところまでいかなきゃなと、すごく思っています。
──幼馴染の永子と健は、お互いをどう思っているんですか
瀬戸 永子が転校してきたときに、「転校生をいじめたら許さないよ」と言ってくれた健ちゃんの一言がすごく心強くて、そばにいて頼りになる存在だと思っています。
前田 でも、永子に力になってもらっている部分もすごくある気がします。永子は、健を一人の人間としてフラットに見てくれている、日本っていう国と健をギリギリ繋ぎ止めてくれている人というか。だから感謝しているだろうし、永子ちゃんみたいな人がいることが希望というか、永子ちゃんがこれからの日本を背負っていると健が勝手に委ねているような、そんな存在だという気がしています。ただ、さおりさんが演じる永子って、めちゃくちゃ健気で真っ白な人で。その「なぜ」「わからない」って尋ねていくなかで絶望することもあるかもしれないっていう危うさが、さおりさんの永子にはあるんです。だから支えてもらいつつ、支えなきゃっていう面も、一緒にお芝居していてすごく感じていて。そこが永子っていう人をより魅力的にしているし。恋愛として好きというだけではない健が永子に抱いている思いは、僕の中にあるというより、さおりさんが演じる永子ちゃんの中にたくさんの答えがあるなって思っていますね。
瀬戸 でも私も、健ちゃんの目からいろんなものが伝わってくるなと感じています。もう、見透かされているんじゃないかっていうくらいまっすぐ私の目を見てくれるから、最初のシーンで健ちゃんから手紙を渡されて、お父さんに「それは恋文だよ」と言われてからは、ドキドキしすぎて健ちゃんの目が見られないんです(笑)。でも、まっすぐな目からいろんなものを感じるからこそ、永子は、健ちゃんが抱えているものをどうにかできないかって必死になるんだと思います。そのまっすぐさは健という役がそうさせているのか、もともと持っているものなのかわからないけど。
前田 (キリッと)もともとのものですね!
瀬戸 そうなんだ(笑)。いや本当に、目が素敵なんですよ。
──この作品には音楽もふんだんに盛り込まれています。歌で表現することについてはいかがですか
瀬戸 永子と健ちゃんの思い出を歌う曲もあって、栗山さんからは、歌として歌い上げるのではなく、二人の思い出や景色とちゃんと向き合って、それが言葉として出てくるように歌うんだと言われているんですけど。それがすごく難しくて。
前田 めちゃくちゃ難しいですよね。
瀬戸 ほかも素敵な曲ばかりだから歌い上げたくなっちゃうし、みんなで合わせたくなっちゃうんです。でも、栗山さんは、それぞれ違う立場の人間だから、それぞれの声がぶつかり合ってほしいとおっしゃっていて。「なるほど!」と思うんですけど難しい。
前田 やっぱり歌っちゃいますよね。僕、歌うことはすごく好きで、一番のストレス発散方法が歌うことで、家でもずっと歌っているんです。しかも、基本的にJ-POPを聴いて歌ってきたので、今回もどうしてもポップスっぽい歌い方になって、シャクってしまったり、変なビブラートが入ってしまうんですよね。「あかん、あかん」と思いながらも、稽古場でピアノが鳴るとリズムに乗ってしまうし(笑)。
瀬戸 危ない、危ない(笑)。
前田 そうなんです。あかんってわかってるんです。だから、ノらずにまっすぐ歌うっていうのをひたすら練習して、最近やっと、だいぶできるようになりました。
瀬戸 あと、二人で共通の思い出を持って、同じ景色を見るっていうことがまだできていないので、そこが濃くなればいいよね。
前田 いいですよね。それこそ「新橋ワルツ」っていう二人の曲は、(両手を大きく広げながら)ブワーッてやりたいですよね。
瀬戸 えっ、どういうこと(笑)?
前田 僕たちが見てる景色がブワーッと、大きなスクリーンに映るプロジェクションマッピングみたいに出たらいいなと思って。
瀬戸 なるほど。まだ小さいもんね。
前田 カーナビで観るテレビくらいだから、もっと大きくしたいなって。
瀬戸 今はまだ一生懸命息を合わせようとしている段階だから(笑)、お互いいろいろ感じ合ってね。
前田 いきたいですね。

──前田さんは初めて、瀬戸さんは三度目になる井上ひさし作品。その魅力をどこに感じておられますか
前田 どんな作品もそうではあるんですけど、一個一個のセリフを大切に言わなきゃいけないなということを、今まで以上に思わされています。それが井上さんのセリフのパワーなのか、健っていう人物を作る材料は全部ここにあるよと言われているというか、セリフが引っ張っていってくれる気がするんです。
瀬戸 一つひとつのセリフに力があるっていうのは、井上さんがたくさんのことを調べて考えてその言葉を選んでいらっしゃるからだと思うんです。だから、その言葉の裏に隠れているものをちゃんと見つけなきゃいけないし、私たちが鮮明に思い描いて届けなきゃいけないというのは、毎回思います。それで今回は、脚本を全部自分で書き出してみたんです。なぜここでこのセリフを言うのか、このセリフにどういう意味があるのか、確認するために。そうすると見えてきたこともあって。井上さんの本って、感情がどんどん動くし、コメディが入ったかと思えば次の瞬間シリアスにもなるし、バンバン切り替わっていくんですけど。そこが繋がって転がっていけばすごく面白くなるし、そこが井上さんの作品の魅力だなと思います。
──一人の人物の中が繋がって物語ができて、それがほかの人の物語と繋がって全体が出来上がっていくんですね。今回も、東京裁判を題材に、弁護士、将校クラブの歌手、GHQの日系二世の軍人など、いろんな立場の人間が出てきて物語を紡いでいきます。どんなものが届けばいいなと思われますか
前田 僕は23歳で今回の作品では若者代表みたいなものなんですけど、僕らの世代って本当に戦争のことを学んできてないなと思うんです。敗戦国だということは知っていても、そこで日本がほかの国や自国の国民に対してどういう過ちを犯してきたのか、やっぱり自分の国の過去をちゃんと知っておくべきだなと思います。劇中に、いい加減な法律を作らせないために国民が監視しなければいけないという話が出てくるんですけど、選挙に行くとか、政治的なことを考えることも大切だなと思うので、この『夢の泪』が、その入口になったらいいなと。でも、重いだけじゃないですから。笑って温かい気持ちになって、なのにすごく重いものが残るっていう、僕がこまつ座を観たときのあの感覚になってもらえたら、何か伝わるものがあるんじゃないかなと思っています。
瀬戸 本当にそのとおりだと思います。やっぱり、過去を知って考えるっていうことをしないと、未来のことも考えられないと思うので。答えが出なくていいから考えるっていうことをするきっかけになったらいいなと思いながら、私はいつもこまつ座さんの舞台に出ているんです。東京裁判って難しく思えるかもしれないですけど、井上さんが「むずかしいことをやさしく」とおっしゃっているように伝わりやすいように書かれていますし。永子が「なんで」「なんで」と考えて成長していくように、一緒に考えてもらえたらいいなと思います。
インタビュー・文/大内弓子
写真/ローチケ演劇部