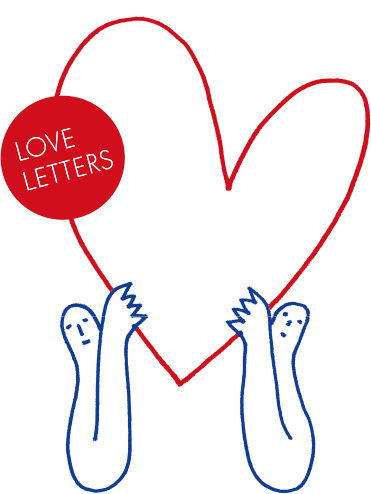これまでに日本では総勢475組が出演し、28年もの間、読み継がれてきた朗読劇『LOVE LETTERS』。1組のアメリカ人男女の50年に渡る手紙のやり取りを通じて、恋愛や人生について、観る者にさまざまなメッセージを投げかける作品だ。“役者同士の読み合わせは一度だけ”など、翻訳・演出家である青井陽治が編み出した手法が二代目演出家・藤田俊太郎に受け継がれ、役者の組み合わせによってまったく違った印象を与え続ける同作。11月14日よりスタートする『2018 Autumn Special』のトリを飾るコンビから、声優・アーティストとして注目を集める内田真礼に話を聞いた。
――役者やアーティスト、芸人などさまざまなキャストたちがその歴史を彩ってきた『LOVE LETTERS』。オファーが来たときは「運命的なものを感じた」という。
内田「これまで声優としてアニメなどの作品や、実写の作品でもお芝居をしてきましたが、朗読劇の世界は『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』に出させていただいて、今年初めて触れた分野です。舞台で人前に立って演じるということに興味もあったので、お話をいただいたときには率直に言って嬉しかったですし、ワクワクしました」
――自由奔放で束縛を嫌う女性・メリッサと、穏やかで内省的な男性・アンディー。2人が織り成すこの物語を内田はまだ観たことがなく、観客同様に新鮮な気持ちで台本に向き合った。
内田「海外のお話なので、最初は自分とは縁遠い感じがしていたんです。でも一度きりの稽古の中で、メリッサの体験がまるで自分のことのように思えました。彼らがやり取りしたお手紙には、心の中の痛いところを突かれるようなことがたくさん綴られているんですよね。物語の途中からは自分では経験したことのない時代や時間さえも、自分のことのように思えて…メリッサが年を重ねれば重ねるほど感じる焦りや、諦めにも近い気持ちまでもリアルに感じてしまって。なので、台本は何度も読みたいんですけど、読むのが怖いような(笑)。アンディーを演じる味方良介さんとは読み合わせで一度しかお会いしてないんですが、『どんな声だったかな』とか、その読み合わせのときにお話したことだとか、台本を読みながらいろんなことを思い返すんです。そういうことも含めて、手紙のやり取りで出来上がっていくストーリーがなんだか自分のことのように思えてきますね」

――若手舞台俳優のホープ・味方とは初共演になる。その印象を尋ねてみると…。
内田「すごく真面目でまっすぐな方という印象があります。朗読劇だと、お芝居をしている間は台本をずっと見ていて、最後の最後まで顔を見ることはないので、ずっと声だけを聴いている状態なんですね。アンディーという役柄のせいもあると思うんですが、とても声がストレートに響く方だなと。なおかつ、真面目すぎてちょっとからかいたくなるような(笑)、そんなイメージです」
――堅物のアンディーを常にからかうメリッサという役どころを彷彿させる、演者2人の関係性。同じ“演じる”ことを生業としながらも演技や作品に対するアプローチはかなり異なり、そこについても興味深く感じたという。
手紙を読み上げるだけでおのずと2人をめぐるさまざまな事情が浮かび上がってくる作品自体も唯一無二の魅力を放っているが、初代演出家・青井からバトンを受け取った藤田の演出法も独特だ。
内田「藤田さんが、まず(初代の演出家の)青井さんのメッセージを伝える使者のような感じで、時間をかけて『LOVE LETTERS』のストーリーを読み解いてくださるんですね。そうやって私たちのまっさらな台本に少しずつ、28年続く作品のエッセンスが受け継がれていく感じがして、感動しました。その一回で不思議と物語が頭の中に入ってきて、私とメリッサがなじんでくる気がしたというか…。演技のアドバイス的なことはあまりおっしゃらず、稽古が一度きりなので、台本をどれだけ読み込めるかが大事ですという言葉をいただきました。なので今は移動中にも台本を読んだりしています」
――声優として多忙をきわめる中で、時折実写作品やこういった舞台の仕事にもトライしてきた内田。それぞれの仕事での役へのアプローチに違いはあるのか聞いてみた。
内田「声優の場合は、共演の方々の声を聴きながら前のシーンなども見て、空気感を合わせていくお仕事なんですね。私は人の顔を見ながらやるお芝居も共演の方との距離を近く感じますし好きなので、実写や舞台のお仕事にご縁があれば今後もやってみたいなと思っています。マンガなどの原作があるキャラクターを演じる場合、そのイメージが関係者の方やファンの方の中にもあるので、最大限そこに寄り添っていく努力をします。でもそういった設定がない今回のような役柄の場合は、私の演じるメリッサが正解なので、そこに素直に集中できるという違いもありますね」
――役作りを通して見えてきたメリッサとアンディーのキャラクター像には、共感できる部分も多いと語る。
内田「メリッサは本当に自由奔放で、女性として理解できるところが多い人。女性にもいろんなタイプがいますけど、人生を自由に生きた女性だからこその“生き急ぎ感”については特に『わかるなあ』と思いますね。じっくりタイミングを待って何かをなすタイプではなく、瞬間瞬間を切り取って生きているような感じの人だったのかもしれないなって。女性はわりと感情の揺れ幅が大きいので、そういう意味で本当に女性らしい人だなと思います。一方のアンディーは、女性の気持ちがわかってない人(笑)。アンディーが別の女性と結婚して、メリッサからプレゼントをもらったときの手紙には本当に腹が立ちました。『メリッサを何だと思ってるの?』って、もう台本のページをめくるのもイヤになって、そこでまたメリッサの気持ちが痛いほどわかるんですよ。」

――そしてこの約50年という長きに渡るメリッサとアンディーのやり取りの中で、印象的に感じたシーンとは…?
内田「2人がささいなことでやりあってケンカするシーンがあるんですけど、そこは手紙なのに直接しゃべっているくらいの勢いがあるので、2人の心の距離が縮まる感じが楽しいです。アンディーのメッセージを読んでいるだけで『もう、何よ!』『いつまでしゃべってるんだろう…』って、私までイライラしてきちゃったり(笑)。2人の感情が出ているシーンには共感できる部分が多いですね。逆に晩年のメリッサのお酒に溺れていく様子が、お酒をあまり飲まない私にとってはまだ想像でしかないので、研究したいところです。そこまで行きついてしまう心理状態というのは、もしかしたら私よりも上の世代の方ならではの悩みを抱えた末でなのかもしれませんし、私がまだ知りえない部分だと思うので…飲みながら台本を読んでみたらわかるのかもしれないなと考えたり、悩み中です」
――作品中でも「手紙は滅びゆくアート」という表現があるが、現在では珍しくなってしまった、手紙を交わすという行為を通じてつながっていたアンディーとメリッサ。小学生のころから携帯に親しみ、手紙を書くという経験がほとんどなかったという内田は、そんな2人の関係をどんな風に捉えているのだろうか。
内田「今はたとえばゲームでキャラクターを介して旅に出かけたり、キャラクター同士で会話をしたりしますけど、2人にとってはそういう手段が手紙だったと思うんです。だから実際そばにいていつでも会えるような関係だったら、2人がどうなっていたかわからないなと思う部分はあります。でもこの手紙を通してのやり取りがとにかく歯がゆくて、もどかしいんですよね。メリッサは本当は電話で話すのが好きな人なので、『アンディー、もう電話すればいいじゃん!』って、私も台本を読みながらずっと思っていました(笑)。でもアンディー側から見ても、ティーンの頃に他の男の子とキスしちゃったりする奔放なメリッサに、きっと不満があったと思うんですよ。稽古の中でも『女子って…』『男子って…』みたいな議論があったんですが、そんな男女のすれ違い方が老若男女、国も飛び越えて共感できるものだからこそ、この物語がたくさんの人を魅了してきたんだと感じます」
――演劇好きにとってはバイブル的な作品である『LOVE LETTERS』だが、普段演劇にあまりなじみのない人にも「ぜひ見届けて欲しい」と語る。
内田「個人的には『サンシャイン劇場に行くなら、やっぱりおしゃれしないと!』って、ちっちゃいバッグを持って、赤いリップ塗って、行っちゃいそうなんですけど(笑)。おそらく読者の方々もそうではないかと思うんですが、この作品は普段通りの気持ちで構えずに観ていただくのがいいと思うんです。何気なく席に腰掛けたら、いつの間にかアンディーとメリッサが隣に寄り添っていて、心にぐっと刺さる言葉があって…。この2時間の間に、メリッサという女性が輝ける時間を作って、ここに彼女が存在したんだよということをしっかり伝えていけたらと思います」
取材・文/古知屋ジュン
撮影/ローソンチケット
【プロフィール】
内田真礼
■ウチダ マアヤ 1989年、東京都生まれ。2009年に声優デビュー。2012年に主演を務めた『さんかれあ』(散華礼弥役)、『中二病でも恋がしたい!』(小鳥遊六花役)などで注目を集める。2014年に第8回声優アワード新人女優賞を受賞し、以降も多数の作品で活躍中。2014年にソロアーティストとしてもデビューを果たし、2019年1月1日には初の日本武道館公演を控えている。