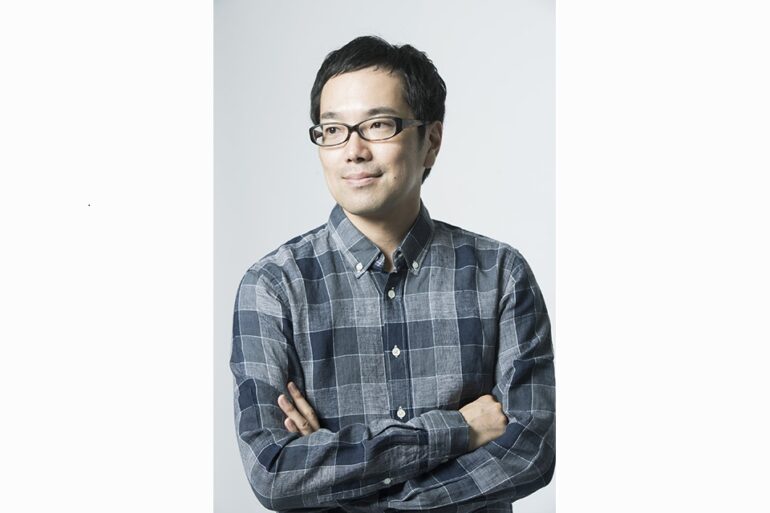
撮影/平岩亨
KAAT キッズ・プログラム 2023 『さいごの1つ前』が7月21日(金)にKAAT神奈川芸術劇場<大スタジオ>で開幕する。天国と地獄の分かれ道で起きる出来事を描いた本作は、劇作家・演出家の松井周と、俳優の白石加代子が子供たちと“ともに”つくりあげる作品で、2022年8月に初演された。出演者は全員続投で、白石をはじめ、久保井研、薬丸翔、湯川ひなが顔を揃える。
稽古が始まったばかりのタイミングで、松井周に話を聞いた。
撮影/宮川舞子
テーマは「死」がよかった
――『さいごの1つ前』は昨年8月に初演され、今回は再演となりますが、初演ではどんな手応えがありましたか?
僕の作品至上一番いい後味というか。観た方がなにかすごく爽やかな、ポジティブな印象を持って帰ってくださったのかなと思います。『おもしろかった』ってみなさんおっしゃっていたのがすごくうれしかったです。
――とはいえただ明るいわけじゃなく、内容は死を描いていたりもしますよね
もともとこの作品は2020年にやろうとしていて、コロナで中止になってしまったのですが、そのときに書いた戯曲は大変暗い、濃厚に“死”を感じさせる、寂しい感じだったんですよ。だけどコロナ禍を経験して、『いや、そうじゃないな』と思いました。そういう暗い方向じゃなくて、もっと普通に明るいものが観たいって。でもやっぱりテーマは『死』がいいと思ったので、じゃあどうやったら明るくなるのかなと考えていきました。あとは稽古場でも、白石加代子さんと久保井研さんというベテラン俳優のおふたりが、なんだかあっけらかんとしたような、ある意味ドライな感じでいてくださって。もしかしたらちょっと臆病になっていた若者も、ふたりの陽気さに影響されて楽しくなっていったんですね。そういう雰囲気も作品に反映されたような気もします。
――ちなみにテーマは「死」がよかったのはどうしてだったのでしょうか?
子供の頃に絶対に考えたことあるベスト10のひとつに『死んだらどうなるんだろう』というのがあると思ったんです。だから実は親しみやすいテーマになるんじゃないかと以前から思っていました。
演劇を、おもしろい遊びだと思ってほしい
――今回、再演だから変化させたいことはありますか?
僕は再演するときにものすごく変えちゃったりするんですけど、この作品は初演とあまり変わらないです。もともとお客さんとやりとりするところがあって、毎日スリリングな作品でもありますしね(笑)。
――お稽古が始まって3日くらい(※取材時)だそうですが、いかがですか?
めちゃくちゃおもしろいです。なにがおもしろいのかなと考えると、やっぱり俳優4人がすごく楽しんでくださっているからだと思いました。一度できたものをなぞろうとしていなくて、その場その場でのことを楽しもうとしている雰囲気がある。このままいくといいなと思っています。あとちょうど今日、すごく素朴な芝居だなと思いました。アナログな人のふるまいがおもしろい。ドジをしちゃうとか、なにかをこわがっているとか、懐かしい記憶の中で踊り出すとか、そういうものを白石さんが一回転することでふっと表現しただけでも、なんか笑えるし感動するんですよね。
――白石さんに対して、失礼ながら「かわいいな」って気持ちにさせられることが何度もありました。
わかります。僕も思いました。白石さんは笑い上戸で気さくで、時々少女で、時々おばあちゃんで、時々きびしい先輩だったりもします。そういうものが舞台上に出ている感じがして、それがいいなと思います。久保井さんも薬丸さんも湯川さんも、自分の“別の側面”みたいなものをちゃんと出してきてくれていて、それだけでもうおもしろいなと思っています。
――白石さんが客席と掛け合いをするとき、私は客席と舞台上の世界が同じ世界線にあるとすっかり信じ込んだと言いますか。初めてお芝居を観たわけでもないのにこんなピュアな気持ちになれるの!?ってくらい純度の高い錯覚を体験しました
ああ、それは圧倒的に白石さんのピュアさが作用しているんだと思います。白石さんじゃない方がああいう感じで客席とコミュニケーションを取ろうとすると、もう少し客席に『参加しようか、しまいか』というような緊張感が走ると思うんです。でも白石さんはそこを超えてきます。あれは不思議ですよね。
――はい、本当に
やっぱりすごい人だなと改めて思います。前回、実は僕もそこは半信半疑でした。観客がそんなふうにピュアに受け取るなんてことは絶対ないだろうというような気持ちがあった。なので稽古場では、シミュレーションを何度もしました。『こういう言葉をかけられたらちょっと緊張するんじゃないか』とか『こういう言葉なら緩むんじゃないか』とか。そこは考えましたね。
――子供たちにどんなものを届けたいと思ったのでしょうか?
演劇のハードルを下げたいと思いました。“演劇”というと構えて観てしまうってあると思うんです。作品だから声を出しちゃいけないとか、じっとしてなきゃいけないとか、きょろきょろしちゃダメだとか。でも僕は、そういうふうに触れるんじゃなくて、遊びの延長のように受け取ってほしいと思います。目の前に喋ってる人たちがいて、遊びをしているから、『遊びの一員としてそこにいてほしいんだけど』みたいな。演劇って“ごっこ遊び”なんですよね。それが原点だし、実は最終目標でもある。その中にある一番おもしろいところって、誰かになってみたり戻ってみたりが簡単にできることだから。子供たちにはそこに触れてもらって、『僕も、私も、できるかも』って思ってほしい。言ってみれば演劇に勧誘したいんです。“おもしろい遊び”として演劇を捉えて、入って来てほしいと思っています。
肩ひじ張らずに観てもらうために
――初演も今回も上演に先駆けて、松井さんと美術・衣裳の長峰麻貴さんがファシリテーターを務め、地域の小学生を対象とした創作ワークショップが行われました。子供たちに「すてきな地獄」を描いてもらい、その絵は実際に舞台上に登場していましたね
前回、初めてこういう試みをしたので、最初は、すてきな地獄なんて考えてくれるかな?と思っていたんですけど、みんな遊びみたいな感じで次々と絵にしてくれました。それを舞台上に出すっていうのも、最初は(作品とは違う空気を持つ絵が出てくることで)集中力が途切れるんじゃないかなと思ったんですよ。でも逆でしたね。『ちょっと脱線もしますけど、それはそれで楽しんでくださいね』『わかったよ』っていうひとつのコミュニケーションの手続きができたのかなという気がします。
――出演者のみなさんが、舞台上で絵を見て語り合っている時間はとても和やかでした
そのパート、ゆるゆるだったでしょう?(笑)僕から『なにを話すか考えないでほしい』『グダグダでいい』と伝えて、やってもらいました。あのゆるゆる感は、客席の緊張を取ったと思いますし、こうやって作品の最初のほうで、『この作品には、演劇だけじゃなくてこういう時間もあるよ』みたいなことを“幅”として提示できたから、観ている側も『じゃあ肩ひじ張らずに観ていいんだ』と思ってくれたんじゃないかなと思っています。
――子供たちが遠慮なくコミュニケーションに参加できる空気ができたんですね
はい。これは『客席を信じる』という言い方もできると思いました。
遊べることはぜんぶ遊んでパワーアップしたい
――初演を拝見して、松井さんにうかがいたいなと思ったことがありまして。それは薬丸翔さん演じるエリート青年のミチロウが、天国に行くために審査される「最高の思い出」として挙げたものが地位や名誉で、それでは天国の扉は開かなかった。そのアリナシの境目ってどのように考えられたのでしょうか?
子供向けにつくるからといって、教訓や道徳めいていたりするような作品はつくりたくないという気持ちは大前提としてあるのですが、『たくさんの名声だったり良い肩書だったり、そういう基準で判断して、自分を天国にふさわしいと思ってしまうあさはかさは、天国は見抜いている』というような表現を入れたくなるのは、やっぱりどこかで現実の世界とリンクさせたいという気持ちがあるからだと思います。ただそういう価値観を断罪したいわけではないんです。彼はその環境の中で一生懸命やったかもしれないですしね。でもそれでも、『最高の思い出』っていうのは、自分を離れて巨大になってしまった基準で計ろうとするのではなく、自分基準であることが大事なんじゃないかな、それは自分の身体とかその半径数メートルから感じることなんじゃないかな、というのはなんとなく思っています。
――ああ、私もそう思います
自分でちゃんと把握していたり理解している範囲からいろんなものを考えていくほうが、生きていて楽しいんじゃないかなっていうのはありますね。
――ありがとうございます。では最後に、これから開幕までにこの作品をどうつくっていきたいと思われていますか?
遊べることはぜんぶ遊んで、どんどんパワーアップしたいです。一番の目的は、子供たちが参加したくてむずむずするような……“ひっぱり”っていうのかな、それを舞台上で起こすことです。それってさっき話した『素朴なこと』だと思うんですよ。ずっこけたら笑っちゃうみたいな、そういうシンプルなおもしろさを追求していきたいです。
撮影/宮川舞子
取材・文/中川實穂




