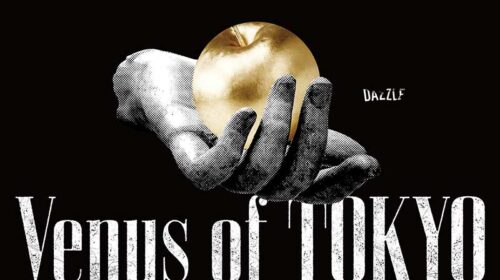あなた次第で物語は変幻自在!
DAZZLEが贈る没入型ステージを体感しよう!
東京・お台場のヴィーナスフォート内で絶賛上演中の「Venus of TOKYO」が大きな話題となっている。ステージは演者と観客が同居する「秘密クラブ」。各部屋を移動していく登場人物を観客自らが追い、同時多発的に起こっているストーリーを体感する。イマーシブシアターと呼ばれる舞台でいったい何が行われているのか?公演を主催するダンスカンパニーDAZZLEの飯塚浩一郎さんに話を聞いた。
――公演開始から5ヶ月、日本初の常設イマーシブシアターとして多くのリピーターを生み出しています。
飯塚「コロナ禍で大変ななか、多くのお客さまに来ていただけているのは嬉しいです。イマーシブシアターは本当に体験しないとわからないことがいっぱいあるので、一度、足を運んで欲しいですね。」
――イマーシブシアターっていったい何?と思われる方もいると思います。客席がなく、廃病院やビル一棟、ホテルなどの施設内全体を舞台とし、様々な部屋やパフォーマンスを、お客さん自身が自分の足で巡り、物語に参加する舞台という認識でいいですか?
飯塚「通常の舞台作品はステージと客席が分かれていますが、イマーシブシアターではお客さんも演者と同じ空間に存在し、作品のなかに“没入”してもらいます。つまり、登場人物たちのやり取りを目の前で、同じ空間で体感できるということです。傍観者ではなく当事者意識を持ったまま観劇するのは新鮮な体験だと思います。」
――観客はお台場のヴィーナスフォート奥にある秘密クラブ「VOID」に入店することで、『Venus of TOKYO』の世界に足を踏み入れることになります。演出のひとつとして、観客もオークションの参加者のひとりになるので、ドレスコードで黒い服を着用することが推奨されていたりもするので、危険な場所に入っていく背徳感がありますね。
飯塚「場所はヴィーナスフォートの一番奥。「正面が入り口じゃないんですね」という声もありますが、あえて裏口を使う演出になっています。」
――大きなストーリーとしては、秘密クラブ「VOID」で催されるオークションに、ミロのビーナスにまつわる“ある品物”が出品される。それを狙って贋作家や富豪、医師といった人物たちの思惑が交錯する……とはいえ、特定の主人公がいるわけではないんですよね?
飯塚「イマーシブシアターは10人の出演者がいたら、10人が90分間、その世界を生きているので、誰の人生をお客さまが切り取るかで物語の捉え方も変わります。例えば医師を追いかけた人は、彼が隠れて行った企みを知ることができますが、それを見ていない人は次のシーンの見え方も違う。一方で、写真家を追った人は医師の裏の顔は知らなくても、盗賊が何をやっていたかは知っている。お客さまがどのような場面を追ってきたかでラストシーンの捉え方も違ってくるのが面白いところです。」
――ということはカップルで観に行っても、同じストーリーではないわけですね?
飯塚「大筋のストーリーはどなたでもわかるように作っていますが、入場したときに別々のテーブルに案内されるので、おのずと視点は変わります。特定の人物を最初から最後まで追いかければ、その人物が主人公になりますからね。それぞれの登場人物が複雑に絡み合い、関係しあっているのでひとつの物語だけが描かれているわけではないんです。」
――『Venus of TOKYO』はDAZZLEオリジナルの作品ですよね?既存の物語ではなく、未知の物語だからこそのドキドキ感を持って作品世界に入るのは大きいと思います。
飯塚「オリジナル作品へのこだわりはあります。海外で成功しているイマーシブシアターは、マクベスや不思議の国のアリスをベースにしています。事前に共通理解を持っていたほうが作りやすいですし、お客さんも理解しやすいのだと思います。我々はオリジナルでやることで、お客さんに何が始まり、どう展開するか分からない体験をして貰おうと思いました。それは大きな挑戦でもありますが。」
――飯塚さんは医師役として出演されています。医師を主人公として観ることもできるんですよね?
飯塚「医師は権謀術数を巡らせている知能犯的な人です。実は他の人に知られていない計画を動かしていて、それは作中では完全には描かれていませんが、医師だけを追っている人にはそれがなんなのかわかってくると思います。内面が読み取りにくい役なので、謎解きのしがいがある人物だと思います。」
――複雑な役ですね。
飯塚「医師を追う人はサスペンスとかミステリーとして見えるかもしれませんね。一方で違う人物を追うと、ヒューマンドラマやラブロマンス、コメディに見えたりすることもあると思います。」
――同時多発的にストーリーが展開しているということは、出演している役者陣も90分間、出ずっぱりで踊り続けているということです。
飯塚「通常の演劇は時間軸を移動させたり、登場人物がいなくなることで別の展開を見せることができますが、本作の場合は90分間、お客さんも演者も同じ時間を体験するので、切迫感も共有することになります。登場人物たちと同じ時間が進んでいく感覚は他の演劇ではあまりない体験だと思います。」
――時間が過ぎていくので、自分がどこに行って良いのか、判断力を迫られるのも緊張感がありますね。
飯塚「私もニューヨークのイマーシブシアターを何本か観ましたが、切迫感は常にあります。自分が見ていない場所で何か起きているんじゃないか?という焦燥感は感じました。あのリアリティはイマーシブシアターじゃないと体感できないなと思います。実際に踊り、演じ続けるのは大変ですが(笑)。」
――飯塚さんが感じるイマーシブシアターの魅力とは?
飯塚「演者としてだと、物語と同じ世界観にお客さんがいるというのが大きいですね。「舞台と客席」という距離があるとできない、目の動き、小さい動きでお客さんに影響を与えることができる。ちょっとしたことで感情が表現できるのは演者として大きな魅力だと思います。お客さんの反応次第で次の動きを変えられるところも自分がその作品のなかで生きていることを感じられ、イマーシブシアターならではの魅力だと思います。」
――今回、演者さんもお客さんもマスクをしているわけですが、マスクがあることでコミュニケーションができなくなるのではなくて、逆にアイコンタクトで通じ合う場面があったりして、新鮮でした。
飯塚「セリフもないので、アイコンタクトと身体の動きだけでコミュニケーションをとっているのですが、その緊張感はやっぱり凄いものがあります。お客さんがどう動くかで私たちの動きも変わるし、演者の組み合わせでも感覚が変わっていく。本当にそこで起きている事件、やり取りがいい意味での緊張感を生み出して、お客さんにも伝わるのではないでしょうか。」
――観客に与えられている自由度も高いですよね?秘密クラブ内を探索したり、オークションに参加することもできます。故に小道具の場所が変わっていたり、お客さんの立ち位置がバラバラだったり、演者さんたちはどう対応しているのですか?
飯塚「臨機応変にとしか言えないですね(笑)。道具やお客さんの数や位置によって、動きが大きなものになったり、小さなものになったり。何度も観ている方はその差異も楽しまれていると思います。」
――5感で楽しむという点では視覚・聴覚・味覚・嗅覚・触覚とすべての感覚を使いますね。なかでも味覚と嗅覚はあっと驚かされました。
飯塚「作中で登場するステーキやパンケーキを本物にして、実際にそれを隣接するダイナーで食べられるようにしたり、香りに関しても香水ブランド「サノマ(çanoma)」の香水クリエイター渡辺裕太氏にプロデュースして貰っています。香りと記憶の結びつきは強いものがあって、家に帰ってから思い出したりとか、数年後に同じ香りを嗅いでふと思い出したりとか、そういうことをしていただけると嬉しいなと思います。」
――飯塚さんはダンサーとしてだけでなく、クリエイティブ・ディレクターとしても携わっていらっしゃいます。ストーリー以外の見どころは?
飯塚「まず、『Venus of TOKYO』を世界に誇れるイマーシブシアターにしたいという思いがあったので、東京で活躍しているクリエイターの方たちに声をかけて参加して貰いました。」
――美術、衣装、音楽、香り、確かに凄いクリエイターが集まっています。特に会場内に仕掛けられているデジタルギミックは見逃せないですね。
飯塚「もともと私がwhateverというクリエイティブ会社に所属していて、デジタル技術を取り入れたイマーシブシアターをやりたいとは思っていたんです。ただ、剥き出しのデジタル技術だけを入れるとテクノロジー自慢のようになり浮いてしまいます。作品のなかでどう機能するのか?というのを今作では脚本の段階からクリエイターたちと話し合って作っていきました。」
――人間の目には見えないけども、“あるもの”を通すと見えるとか、作品世界にハマるギミックも見逃せません。
飯塚「プレミアムチケットを購入した方に渡されるグラスがあり、特別なものを見ることができます。デジタル演出も目に見える部分はもちろん、タイミングや安定性なども緻密に設計・制作されているので、ゼロから一緒に作れる環境だからこその演出だなと思います。」
――演者の方たちが身に纏う衣装も素敵でした。
飯塚「ファッションブランド“DRESSEDUNDRESSED”のデザイナー北澤武志さんに、空間にふさわしい衣装でありながら、それぞれの役割が記号として見えているもの、というお願いで制作して貰いました。イマーシブシアターはお客さんが近くにいるので、いわゆる舞台衣装のような遠くから見ることを前提とした衣装だと嘘に見えてしまうことがある。服として仕立てがちゃんとしていつつ、動きやすいというものを作って貰いました。」
――“DRESSEDUNDRESSED”のファッションショーとしても楽しめるかもしれませんね。
飯塚「そうですね、そんな感覚を覚えるシーンもあると思います。」
――1日3公演ありますが、そのうちの夜の部はオンラインでも配信されているんですね?
飯塚「オンラインは監視者というカメラを持っている役を作り、その監視者にTwitterを通じて指示を出せる仕組みになっています。オンライン上の指示次第でその日の動きが変わるので、その回しかない展開が見られるわけです。会場にいない人が、現場で起きていることに介入できる感覚は他のエンターテインメントではなかなかないと思うので面白いと思います。リアルで参加している方も不確定要素が増えることで、予定調和ではない体験ができるのではないでしょうか。」
――会場であるヴィーナスフォートが来年3月末での閉館が決まっています。この先、2度と同じ場所で公演が行われることがないと思うと、一回でも多く見たくなります。
飯塚「通常、ロングラン公演は基本的に内容を変えないものだと思いますけど、作り手側もダンサーなので、やっていく中で「こうした方がいいのではないか」ということが出てきて、どんどん変えたくなってくるんです。ダンスはもちろん、曲も変えています。演者の経験値も含め、どんどんよくなっている手応えがありますね。」
――曲も替えちゃうんですか?
飯塚「替えますね。」
――ますます何度も通いたくなっちゃいます(笑)。リピーターが多いのも納得です。
飯塚「ライブ感、一期一会の感覚というのはイマーシブシアターの重要な要素だと思います。次の回を見たらまた違うことが起きていたりしますからね。ひとりで来て楽しむのもいいですし、複数人で来られて観劇が終わった後に「私はこのシーンを見たよ」とか、「あ、それ私見てない」とか、ご友人同士で盛り上がっていただくのも良いと思います。オンライン版はアーカイブも24時間あるので、買っておいて、自分が追いかけなかった人物のシーンを見たり、「あ、私、ここにいる」と数時間前の自分を楽しむこともできます。お客さんそれぞれの楽しみ方を見つけていただけると嬉しいです。」
インタビュー・文/高畠正人
Photo/村上宗一郎
※構成/月刊ローチケ編集部 11月15日号より転載

掲載誌面:月刊ローチケは毎月15日発行(無料)
ローソン・ミニストップ・HMVにて配布
【プロフィール】
DAZZLE
■ダズル 96年結成。「すべてのカテゴリーに属し、属さない曖昧な眩さ」をスローガンに掲げ、独創性に富んだ作品を生み出し続けるダンスカンパニー。ストリートダンスとコンテンポラリーダンスを融合させた、世界で唯一つのオリジナルダンススタイルを生み出す。