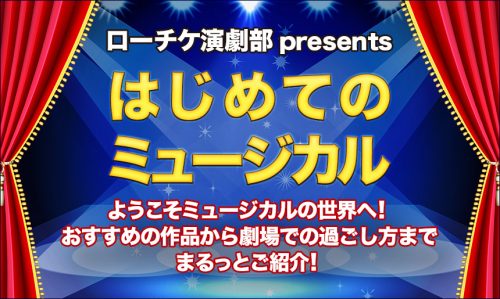ミュージカルを構成する諸要素は、大きく「①脚本・音楽」と「②その他」に分類できる。誕生した瞬間はもちろん全要素が一体化しているが、別の地に輸出されたりリバイバルされたりした時に残るのは往々にして①のみで、②に関しては刷新されることが多いという意味だ。という前提の上で、今月は8~9月上演のミュージカルを振り返ってみたい。
●不朽の名作、『シカゴ』と『WSS』
1975年初演の『シカゴ』に1957年初演の『ウエスト・サイド・ストーリー(以下WSS)』と、長い歴史を持つブロードウェイミュージカルが相次いで来日を果たした。共通点は、どちらもリバイバル版でありながら、②のうちの一要素であるはずの「振付」が初演版を踏襲していること。ボブ・フォッシー(『シカゴ』演出・振付家)とジェローム・ロビンス(『WSS』演出・振付家)の振付がそれだけ強烈で、①と切っても切り離せないことの証だろう。 違いは、『シカゴ』が1996年にブロードウェイで生まれて以来、日本でも様々なキャストによって上演されているウォルター・ボビー演出版だったのに対し、『WSS』はIHIステージアラウンド東京という特殊な劇場に合わせて新たな演出が施された“世界初演版”であること。だがどちらにしても、過去に何度も上演されている作品ではあるため、長いことミュージカルファンをやっている筆者のような者にとっては、『シカゴ』は過去の別キャストと、『WSS』は過去の別演出版と“観比べる”という視点での鑑賞となった。
違いは、『シカゴ』が1996年にブロードウェイで生まれて以来、日本でも様々なキャストによって上演されているウォルター・ボビー演出版だったのに対し、『WSS』はIHIステージアラウンド東京という特殊な劇場に合わせて新たな演出が施された“世界初演版”であること。だがどちらにしても、過去に何度も上演されている作品ではあるため、長いことミュージカルファンをやっている筆者のような者にとっては、『シカゴ』は過去の別キャストと、『WSS』は過去の別演出版と“観比べる”という視点での鑑賞となった。
そうなると、好みの問題によって色々と言いたいことも出てきてしまうのだが、今回はじめてこの作品を観た人はやはり、まずは脚本・音楽・振付の力に圧倒されたのではないだろうか。気に入ったのなら、今度は同じクリエイターの別の作品を観てみてほしい。そうして道を広げていった先にはきっと、歯がゆくも楽しい“観比べ地獄”があなたを待っている。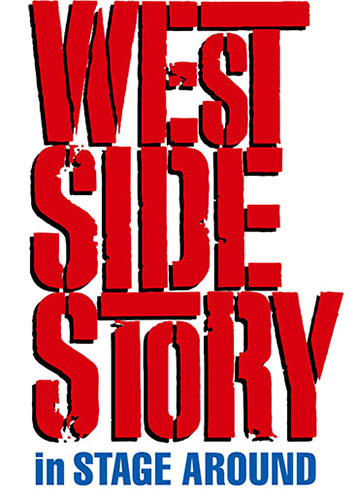 ●『ペテン師』『若草』に見る演出家の開花
●『ペテン師』『若草』に見る演出家の開花
ブロードウェイミュージカルの日本語版が製作される際、最新作は②も含めて踏襲される「レプリカ版」、比較的古い作品は日本の演出家が①のみを使う「日本オリジナル版」として上演されることが多い。ひと昔前は、後者を成功に導ける演出家といえば宮本亜門と小池修一郎くらいしかいなかったような気がするが、近年では随分と増えてきた。上演中の『ペテン師と詐欺師』は福田雄一の、『リトル・ウィメン~若草物語』は小林香の演出だ。 福田は今や、映像監督として飛ぶ鳥を落とす勢いだが、実はブロードウェイにも定期的に訪れているほどのミュージカル好き。独自のコメディセンス、映像業界で培った文脈、そしてあふれるミュージカル愛が存分に生かされた彼の作品は、好きな人にはたまらない「福田ワールド」だ。一方の小林は、自分の個性を打ち出すというより、作品に即した丁寧な演出で演者の良さを引き出すタイプ。コメディ色の強い『ペテン師』が福田に、物語をじっくり見せる必要のある『若草』が小林に任されたのは納得で、選択肢の多さが心強い。
福田は今や、映像監督として飛ぶ鳥を落とす勢いだが、実はブロードウェイにも定期的に訪れているほどのミュージカル好き。独自のコメディセンス、映像業界で培った文脈、そしてあふれるミュージカル愛が存分に生かされた彼の作品は、好きな人にはたまらない「福田ワールド」だ。一方の小林は、自分の個性を打ち出すというより、作品に即した丁寧な演出で演者の良さを引き出すタイプ。コメディ色の強い『ペテン師』が福田に、物語をじっくり見せる必要のある『若草』が小林に任されたのは納得で、選択肢の多さが心強い。 初観劇からミュージカルの道を広げていくにあたり、日本のファンは役者を足掛かりにすることが多いように見受けられるが、筆者のオススメは前述の通りクリエイター。そして演出家は、脚本家、音楽家、振付家と同じくらい、あるいはそれ以上に“自分好み”を見つけやすいクリエイターだ。『ペテン師』に笑ったのなら福田の、『若草』に泣いたのなら小林の次回作から広げていくのも一つの手と言えるだろう。
初観劇からミュージカルの道を広げていくにあたり、日本のファンは役者を足掛かりにすることが多いように見受けられるが、筆者のオススメは前述の通りクリエイター。そして演出家は、脚本家、音楽家、振付家と同じくらい、あるいはそれ以上に“自分好み”を見つけやすいクリエイターだ。『ペテン師』に笑ったのなら福田の、『若草』に泣いたのなら小林の次回作から広げていくのも一つの手と言えるだろう。
●日本オリジナルの意欲作
最後に、①からして日本で作ってしまおうという「日本オリジナルミュージカル」について。手間も予算もかかるため製作が盛んとは決して言えず、またどんなものが出来上がるのか初日を迎えるまで分からないため事前にオススメすることもなかなか難しい(ゆえにこのサイトでもオススメしそびれた)のだが、8~9月には三つの意欲作が上演された。
鈴木聡が作・演出を手がけ、稲垣吾郎が主演した『君の輝く夜に~FREE TIME, SHOW TIME~』は、大人なキャスト4名の魅力をとにかく最大限にまで引き出すのだ、というコンセプトが明確。上田一豪作・演出の『フリーダ・カーロ』は、日本オリジナルミュージカル=ダサいというイメージを覆すセンスの良さと、小澤時史による音楽のクオリティの高さが光った。横山清崇脚本・演出の『人生のピース』は逆に、ダサくたっていいじゃないか!日本人なんだから等身大の日本人を描こうよ!という姿勢に貫かれており、筆者的には非常に好感触。こちらの音楽も小澤時史が手がけており、彼の今後にも期待が高まった。 日本とアメリカではミュージカルの歴史に大きな違いがあるし、なにせブロードウェイは世界の中心地であるからして、いくら意欲作だからといって日本のオリジナル作品がブロードウェイ作品並みに良く出来ていることはまずない。それでも筆者は、日本人が生み出した日本人の肌感覚に合う作品がいつか観たいし、そのためにはまずは様々な挑戦がなされなくてはならないと信じているので、今後も意欲作は出来るだけ取り上げていきたい。
日本とアメリカではミュージカルの歴史に大きな違いがあるし、なにせブロードウェイは世界の中心地であるからして、いくら意欲作だからといって日本のオリジナル作品がブロードウェイ作品並みに良く出来ていることはまずない。それでも筆者は、日本人が生み出した日本人の肌感覚に合う作品がいつか観たいし、そのためにはまずは様々な挑戦がなされなくてはならないと信じているので、今後も意欲作は出来るだけ取り上げていきたい。
文/町田麻子