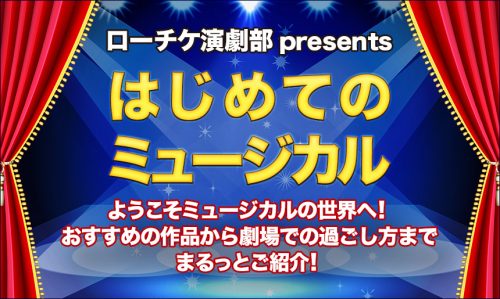先の1か月は総じて、(概ね)誰が観ても楽しめるような“王道”ミュージカルがなかったように思う。何をもって“王道”とするかというのは、ほかのジャンルと同様ミュージカルにおいても人それぞれだが、筆者的には「この作品を観た上でミュージカルが好きじゃないって言われたら私はもう潔く諦めるよ!」と気持ちよく言える作品ということだ。
●ミュージカル?ショー?『ボディガード』来日公演
世界最大の劇場街であるブロードウェイやウエストエンドでヒットした作品というのは、やはり“王道”である可能性が高い。しかも海外キャストによる公演は、日本人が急に歌い出すことには抵抗を覚える、というミュージカル初心者にも勧めやすい。その意味で、ウエストエンド作品の来日公演である『ボディガード』はそうなる可能性を秘めていたのだが、少々様子が違っていた。物語よりもビジュアルよりも何よりも、ホイットニー・ヒューストンの楽曲をコンサート形式で見せることに重きを置いた、ショーのような作りだったのだ。
もちろんそれはそれで、歌ウマ海外キャストのパフォーマンスを存分に楽しみたい向きには十分な見応えがあっただろう。だが、ミュージカルには脚本とサウンドとビジュアルが融合した総合芸術であることを何より求めたい筆者には、やはり物足りなさが否めなかった。とはいえ、ウエストエンドではヒットしたがブロードウェイには行かなかった事実を考えると、それは予想できたことでもある。ブロードウェイは、ウエストエンド以上に商業化された劇場街。それがこれほどの知名度を持つコンテンツを迎え入れなかったということは、誰が観ても楽しめる“王道”ミュージカルではないと踏んだからに違いない。
というわけで、もし今回筆者と同じように感じたなら、次はぜひ両方の劇場街でヒットした作品を。そして反対に、迫力のパフォーマンスに感動したなら、来年3月に上演される日本キャスト版に注目してほしい。同じ作品とはいえ別の演出家が手がけるので、きっと違う見せ方をしてくるはずで、観比べることでミュージカルの新たな地平が見えてくるだろう。 ●浦井健治が描いた演劇性の高い『ヘドウィグ』
●浦井健治が描いた演劇性の高い『ヘドウィグ』
『ヘドウィグ・アンド・アングリーインチ』は、オフ・ブロードウェイで生まれた後にウエストエンドでもブロードウェイでもヒットを記録しているが、また別の意味で“王道”とはちょっと違う気がする作品。そのヒットを主に支えているのが、観光気分で観て「楽しかった!」と言って帰る層ではなく、“ヘドヘッド”と呼ばれる熱狂的なファンだからだ。実際、メッセージ性の強い内容をライブ形式で綴っていく作風は、オフ・ブロードウェイ生まれということもあり、一般的なミュージカルとはかなり異なっている。
そんな作品であるがゆえに、海外でも日本でも強烈な個性を持つ俳優が主演することが多かったが、今回はそれこそ“王道”ミュージカル俳優である浦井健治がヘドウィグ役を務めた。彼の俳優としての誠実さゆえに、舞台はやはり従来の『ヘドウィグ』とはひと味違う演劇性の高いものとなったが、だからといって作品の特殊性が薄れることはなかったのもまたその誠実さゆえ。喉の使い方と歌唱法をガラリと変えた浦井が、女王蜂のアヴちゃんやロックミュージシャンたちと共に、ギュンギュンのロックミュージカルを描き出した。
時には総立ちになって手を突き上げながら観るような、こうしたライブ感を気に入ったのなら、次もぜひロックミュージカルを。メッセージ性の強さを気に入ったのなら、オフ・ブロードウェイのような小さな場所から始まり“伝説”と化していった作品を。そして浦井健治に魅せられたのなら、彼の次回作から広げていくことをオススメしたい。 ●『怪人と探偵』と『sign』が見せてくれた可能性
●『怪人と探偵』と『sign』が見せてくれた可能性
日本オリジナルミュージカルは、未だ試行錯誤の時期。よって“王道”であることは稀であり、はじめてのミュージカルに選ぶには勇気が要るが、その分すべてが“意欲作”ではあるので、少しでも日本ミュージカル界の将来を思うならぜひ応援してほしいジャンルだ。森雪之丞が脚本・作詞・楽曲プロデュースを、白井晃が演出を手がけた『怪人と探偵』は、両名とキャストの熱い思いが隅々まで行き渡った、意欲作中の意欲作という印象。特に最後の畳みかけにはゾクゾクさせられるものがあり、ブラッシュアップしての再演を望みたい。 『怪人と探偵』がオン・ブロードウェイ風の大作なら、ミュージカル座の『a song cycle sign』はオフ・ブロードウェイ風の小品。実際“ソングサイクル”というのはオフで流行している形式で、「ある一つのテーマを中心としつつ、1曲で1話が完結するオムニバスストーリーを集め、1本の作品にまとめたもの」(公演パンフより)だ。その形式を日本に持ち込んだこと、オフと同じように若手ソングライターの活躍の場として活用していることはもちろん、その形式を脚本・作詞・作曲・演出の藤倉梓とキャスト陣がすっかり自分の手中に収めて日本人らしい作品としているところに、何より驚かされたし頼もしさを覚えた。
『怪人と探偵』がオン・ブロードウェイ風の大作なら、ミュージカル座の『a song cycle sign』はオフ・ブロードウェイ風の小品。実際“ソングサイクル”というのはオフで流行している形式で、「ある一つのテーマを中心としつつ、1曲で1話が完結するオムニバスストーリーを集め、1本の作品にまとめたもの」(公演パンフより)だ。その形式を日本に持ち込んだこと、オフと同じように若手ソングライターの活躍の場として活用していることはもちろん、その形式を脚本・作詞・作曲・演出の藤倉梓とキャスト陣がすっかり自分の手中に収めて日本人らしい作品としているところに、何より驚かされたし頼もしさを覚えた。
森雪之丞のような他ジャンル出身の大御所が大作ミュージカル製作に乗り出してくれることと同じくらい、小さな頃からミュージカルに親しんでいる若手クリエイターがその感性で小品を創作することは尊いと思う。このうえ必要なのは、そうした才能たちの協働ではないだろうか。オンもオフもまとめて一つのコミュニティ、オフからオンへの昇格は日常茶飯事なブロードウェイのように、日本ミュージカル界でも多方面の才能が、劇団や製作会社の垣根を超えた創作活動をもっともっとしていってくれることを願ってやまない。
文/町田麻子