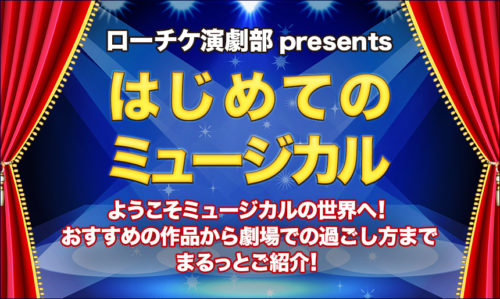2022年の『ハリー・ポッター』(※ミュージカルではない)の情報が解禁されて、あまりの早さにひぇ~と思っていたら、2021年の情報なんかは普通にどんどん解禁され始めて、つくづく演劇業界とは鬼に笑われるジャンルだなあなどと思う今日この頃。そんな中、ここでは変わらずマイペースに、1月終盤から2月にかけて観たミュージカルを振り返る。
●『デスノート』と『フランケン』の再演
大ヒット漫画をブロードウェイの人気作曲家フランク・ワイルドホーン、日本を代表する演出家の栗山民也ら本気の布陣でミュージカル化した『デスノート』と、主要キャスト全員が二役に扮するというトリッキーな趣向を持つ韓国発の『フランケンシュタイン』。年初の日本ミュージカル界を賑わせた2作はどちらも再演で、再演というのは基本的に、初演が好評だったから企画されるもの。つまりは作品のクオリティがある程度保証されているということなので、ミュージカルデビュー作を選ぶ際にはぜひ一つの指標にしていただきたい。
だが一方で、初演で固定ファンがつき、初心者を寄せ付けない空気が生まれがちなのもまた、再演もののサガ。筆者にとっては『フランケンシュタイン』がそうで、初演も今回もそれなりに楽しみはしたが熱狂するほどではなかったため、周囲のノリについていけず少々肩身の狭い思いをした。人間には好みというものがあって、思うにこの作品は、想像力が豊かで深読みするのが好きな層に向いている。それだけの話なので、この作品に熱狂できなかったからといって、熱狂する周囲やミュージカル自体に距離を感じる必要は皆無。そういう向きには、例えばだが、よりストーリーに現実味のある作品で。そして逆に、本作でミュージカルに開眼した向きには、同じ韓国発の作品などで二歩目を踏み出すことをお勧めしたい。 『デスノート』は再々演だが、オール新キャストだったこともあり、初心者を寄せ付けない空気というのはなかったように思う。むしろ、浦井健治、柿澤勇人、小池徹平、濱田めぐみら主役級が顔を揃えたことでファン必見感があった初演より、初舞台の新人(甲斐翔真)を含む今回のほうが、原作きっかけで興味を持った初心者が足を運びやすかったのではないだろうか。非常に演劇的な作品ゆえに、原作を忠実に再現した2.5次元的ビジュアルや、スペクタクルなブロードウェイ的ミュージカルを期待した向きには、物足りなさもあったかもしれない。だが、とかく作品よりも役者で観る文化がある日本において、オリジナルミュージカルが“作品力”で勝負に出た心意気は、きっと万人に伝わったことだろう。
『デスノート』は再々演だが、オール新キャストだったこともあり、初心者を寄せ付けない空気というのはなかったように思う。むしろ、浦井健治、柿澤勇人、小池徹平、濱田めぐみら主役級が顔を揃えたことでファン必見感があった初演より、初舞台の新人(甲斐翔真)を含む今回のほうが、原作きっかけで興味を持った初心者が足を運びやすかったのではないだろうか。非常に演劇的な作品ゆえに、原作を忠実に再現した2.5次元的ビジュアルや、スペクタクルなブロードウェイ的ミュージカルを期待した向きには、物足りなさもあったかもしれない。だが、とかく作品よりも役者で観る文化がある日本において、オリジナルミュージカルが“作品力”で勝負に出た心意気は、きっと万人に伝わったことだろう。
●異例の『チェス』、定番の『ドリガ』
ミュージカルは観てみたいけど、日本人が急に歌い出すことにはやっぱりちょっと抵抗がある、あるいは日本人の歌唱力に不安がある――。1月終盤から2月にかけては、そんな層の入門編としてぴったりな原語ミュージカルも2本上演された。通常“来日ミュージカル”というところをあえて“原語”としたのは、うち1本が海外スターを主役に据えてはいるものの、日本人キャストとともに日本だけで上演するという異例の形を取っていたから。ABBAのメンバーが音楽を手がけた難曲ぞろいの作品に、ラミン・カリムルー、サマンサ・バークス、佐藤隆紀らが挑んだ『CHESS THE MUSICAL』である。
カリムルーとバークスは共に、ミュージカルの本場ブロードウェイとウエストエンドを股にかけて活躍するホンマモンのスター。圧倒的な歌唱力に加えて演技力と華も備えた二人が、コンサートではなくミュージカルの場で、役として歌う姿が観られたこの公演は間違いなく貴重だった。よって、ミュージカルと銘打つにはあまりにもコンサート風の演出や、日本人キャストがわざわざ英語で歌うことに疑問を覚えた筆者のようなひねくれ者は、そう多くないだろう。だがもしおられたなら、言いたいことはただ一つ。二歩目はぜひ本場へ!
もう1本の『ドリームガールズ』は、今回で4度目の来日となる人気作。元々はブロードウェイで生まれた作品だが、来日を重ねているのは劇場ではなくブラックミュージックの殿堂アポロシアターで初演されたバージョンなため、これまたちょっとコンサート風の演出だ。そうつまり、ミュージカルを愛し過ぎる筆者にはやはり物足りなさがあり、観劇したのは初来日以来だったのだが、今回はストーリーに開眼させられた。ショービジネスの光と影というメインテーマの裏に、女性の自立という現代性あふれるサブテーマが隠されていることに、改めて気付かされたのだ。10年も間を空けて再び観ると、社会状況や自分自身の変化によって、同じ作品が違って見えてくるのもまたミュージカルの面白さかもしれない。
●ミュージカル?音楽劇?
最後に、2月に何やら花盛りの様相を呈していた“音楽劇”の話題を少し。ミュージカルと音楽劇との境は曖昧で、人によって定義が異なるため、主催者側(主に演出家)の定義によって音楽劇と銘打たれているけれども、私の定義ではこれはミュージカル、みたいなことやその逆はよくある。筆者の定義はどうでもいいし、そもそも自分がどっちと捉えるかは観るまで分からないことなので、本サイトでは基本的に、主催者側によって“ミュージカル”と銘打たれているものだけを紹介するようにしている。
しているのだが、2月はうっかり、「日本オリジナル」欄が寂しいという理由で『星の王子さま』だけ謎に入れてしまった。実際に観てみたらおっしゃる通りの音楽劇で、これを入れるなら『天保十二年のシェイクスピア』『ねじまき鳥クロニクル』『春母夏母秋母冬母』も入れるべきだったと反省中。つまりどれもおっしゃる通りの音楽劇だったわけだが、それは筆者がそう捉えたというだけで、4作ともミュージカルだと感じた人もいることだろう。 どうでもいいはずの筆者の定義を少しだけ披露させていただくと、“脚本と楽曲”のセットが根幹にあり、それ以外の要素が“演出”の範疇に入るのがミュージカルで、脚本も楽曲も装置も衣裳も振付も照明もすべて“演出”の一要素として一直線上にあるのが音楽劇、という感じ。ついでに言うと、“脚本”が単体で根幹にあるのがストレートプレイ…ではあるのだが、結局のところやっぱりカテゴリーなんてどうでも良くて、ミュージカルなら何でも好きなわけでも、音楽劇やストレートプレイにはすべからく興味がないというわけでもない。自分好みかそうじゃないかが観るまで分からないから、舞台沼は深いのである。
どうでもいいはずの筆者の定義を少しだけ披露させていただくと、“脚本と楽曲”のセットが根幹にあり、それ以外の要素が“演出”の範疇に入るのがミュージカルで、脚本も楽曲も装置も衣裳も振付も照明もすべて“演出”の一要素として一直線上にあるのが音楽劇、という感じ。ついでに言うと、“脚本”が単体で根幹にあるのがストレートプレイ…ではあるのだが、結局のところやっぱりカテゴリーなんてどうでも良くて、ミュージカルなら何でも好きなわけでも、音楽劇やストレートプレイにはすべからく興味がないというわけでもない。自分好みかそうじゃないかが観るまで分からないから、舞台沼は深いのである。
文/町田麻子