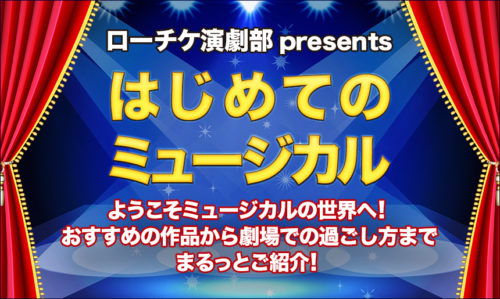皆さんご存知の事情により何か月も休載していたが、しれっといつも通り、先月のミュージカル公演を振り返ってみる。それが可能なくらい、11月の日本ミュージカル界は“元通り”の様相だった。いやもちろん、裏にはとんでもない努力と苦労があったはずで、リスクと隣り合わせであることも忘れてはならない。ならないが、観ている間は忘れられてしまうほど、コロナ前と変わらぬ熱演が各所で繰り広げられた11月だった。
初めて観たかった『ナイン』
ブロードウェイと日本での初演がそれぞれ、1996年と1998年の『RENT』、2001年と2005年の『プロデューサーズ』、2003年(正確には1982年版というのもあるのだが)と2004年の『ナイン』。3作品ともどちらの初演も観ていることに、自分がミュージカルおたくとして思いのほか“古参”になってきていることを思い知さられるラインナップでもあった11月だが、前にも観ていることが必ずしも良いほうに作用するとは限らない。初めてだったらきっともっと純粋に楽しめただろうなあ…と思うことも当然あるわけで、筆者にとっては『ナイン』がそうだった。
というのも、2003年にアントニオ・バンデラス主演で、2004年に福井貴一主演で、同じデヴィッド・ルヴォーの演出により上演された『ナイン』があまりにも好き過ぎたのだ。当時の筆者の感性はまだ若くピチピチで、しかも思い出というのは美化されるのが常。さらにこの作品の場合、当時はずっと年上の“イケオジ”に見えて憧れた主人公が、自分と完全に同世代になり現実味を帯び過ぎてしまった40歳という設定だ。そこにきて今回の藤田俊太郎演出・城田優主演版は、ところどころ英語詞のまま歌われたり映像が多用されるなど、受け入れるにはピチピチの感性が必要であろうと思われる斬新な舞台だった。
もちろん、実年齢より少し上のイタリア人映画監督グイドに扮した城田優は惚れ惚れするほどイイ男だったし、取り囲む女優陣は日本ミュージカル界全体の成長を実感させるに十分な百花繚乱ぶりだったし、何よりモーリー・イェストンの音楽の色褪せぬ美しさには何度もゾクゾクさせられた。それでもやはり、己の中で美化されたルヴォー版の記憶に邪魔をされ、心底酔うことはできなかった悲しき古参おたくの筆者なのだった。

古参的『RENT』『プロデューサーズ』観劇記
一方、『RENT』は四半世紀の観劇歴の中で初めてと言っていいくらい、今回はすごく胸に響いた。高校生時分に初めて観た時から、「なんかスゴいものを観た」という衝撃は確かにあり、だからこそその後も何度も観ているわけだが、何度観てもレントヘッズと呼ばれる熱狂的ファンのようには感情移入できずにいた作品。“今を生きる”若者たちの群像劇という性格上、若い時に共感できなければ永遠にできないだろうと思っていたが、今回はキャストの熱演に後押しされて自分まで今を生きたくなってしまった(『RENT』はキャストに陽性者が出て16日以降の公演が中止に。皆様のご快復をお祈りします。)。初観劇はいつだって貴重な一方で、観続けることで至れる境地もある、それがロングランミュージカルの面白さ。

『プロデューサーズ』の場合は、“観続ける”というよりも“観比べる”ことでその真価を確認できたという感じ。トニー賞12部門受賞という、いまだ破られていない大記録を持つ大ヒットミュージカルだが、大学生時分に初めて観た時は実は、「確かにもんのすごく贅沢で華やかで面白いけど、そこまで画期的な作品か…?」と思わなくもなかった。それはおそらくアメリカの“国民的”ミュージカルだからで、人種ネタや下ネタをあっけらかんと笑い飛ばすこの作品の真の画期性はきっと、アメリカで生活していなければ分からない。そして筆者は、アメリカで生活はしていない。
そんな作品を今回は、コメディ界のヒットメーカー福田雄一が新たに演出。基本的にはブロードウェイ版を踏襲しているのだが、キャスティングにもう滲み出ている“福田色”(井上芳雄、吉沢亮、佐藤二朗ら)が、アメリカの“国民的”なあれこれを補完するような役割を果たす。今思えば2005年の井ノ原快彦・長野博主演版もそうで、日本に根付いた“ジャニーズ色”や“福田色”が加わることで、日本の観客が作品に距離を感じることなく、“自分の作品”として楽しめるようになるのだ。そして距離さえなくなれば、作品が元々持つ贅沢さ、華やかさ、面白さがより一層際立ってくる。かくして筆者は、一周回ってスーザン・ストローマン(オリジナル演出・振付)やっぱ天才だな!と唸らされたのだった。

妄想が膨らむ『ビューティフル』
11月のもう一つの大作『ビューティフル』は、2014年にブロードウェイで生まれ、日本では2017年に初演された作品の、ほぼ同じキャストによる再演。キャロル・キングの半生を彼女自身の楽曲によって綴る作品で、著名なアーティストの物語を本人の楽曲で紡ぐ「バイオ(伝記)・ミュージカル」と称されるこのジャンルには、ほかにも成功作が数多い。ザ・フォーシーズンズが主人公の『ジャージー・ボーイズ』がその代表例で、共通するのは“音楽という営みの尊さ”が前面に出ている点。素晴らしい楽曲が、それが生み出された背景とともに次々と登場するのだからもう、観ている間中「はぁ尊い」と思い続けるしかない。
今回の『ビューティフル』も、それはもうバカみたいに尊い尊い思い続けながら観たわけだが、バイオ・ミュージカルの成功作を観るたびに思うことがもう一つある。それは、日本のアーティストが主人公のバイオ・ミュージカルがあったらどんなに尊いだろう…!ということ。名前は知ってるけど楽曲をちゃんと聴いたことはなく、ミュージカルに登場するヒット曲のうち元々知ってたのは3曲くらい?なキャロル・キングやザ・フォーシーズンズでもこんなに尊いのだから、出てくる楽曲出てくる楽曲に馴染みがあって、本人にも思い入れがあるアーティストだったら――例えば安室奈美恵ミュージカルだったら!――、もう尊すぎて卒倒するレベルなんじゃないかと妄想が膨らんでしまうのだ。
『ビューティフル』について、決してブロードウェイの常連とは言えないクリエイティブ陣が生み出していることが気になって調べたことがあるのだが、どうやらミュージカル化を思いついたのはキャロル・キングのレコード会社側。彼らがまず、楽曲の使用許可を簡単には出さないことで有名なアーティストを口説き落とした実績のある地方劇場のプロデューサーに声をかけ、そのプロデューサーが無事キングも口説き落とした上でクリエイティブ陣を集め、ミュージカル化に漕ぎつけたらしい。そうつまり、ヒットミュージカルの仕掛け人が必ずしも大物プロデューサー――日本で言えば大手演劇製作会社――である必要はないわけだ。日本ミュージカル界が音楽業界を巻き込んでますます発展し、ひいては尊い尊い安室奈美恵ミュージカルをいつか生み出すことを、引き続き妄想してやまない。