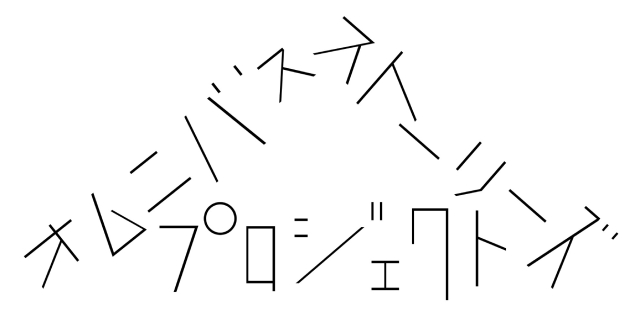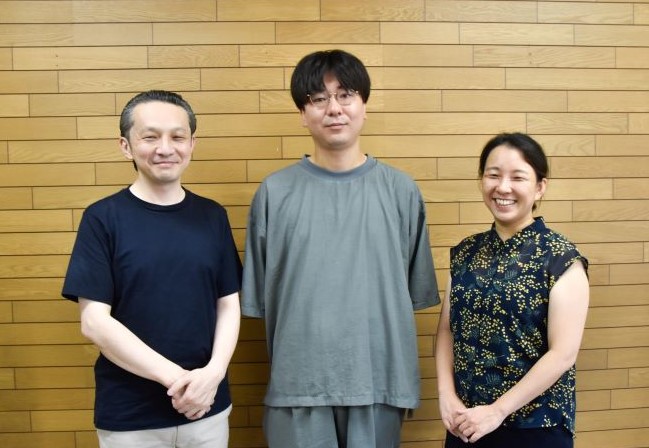
写真左から)長島確、三浦直之、河合千佳
新しい“演劇のキット”をつくる、その誕生を目撃する公演に──
50人以上のキャラクターが登場するオムニバス・ストーリーを三浦直之(ロロ)が手掛ける。(カタログ版)と銘打たれた作品は、東京芸術祭 2023にて10月7日(土)~15日(日)に上演される。
キャラクターのプロフィールはすでにWEBで公開されており、それらをもとに俳優たちと舞台を作るというのだが……。創作にあたって用意されているのは、【氏名】【年齢】【エピソード】が記された各キャラクターの300字程度のプロフィール、そして1キャラクターにつき1ページの台本のみ。「物語未満」からはじまる創作は、これからの演劇を変える新たな“演劇キット”になるかもしれない。
三浦と、この企画の立ち上げから伴走する東京芸術祭の長島確、河合千佳の3人に、本作について伺った。
戯曲を書かずに、舞台をつくる。(カタログ版)とは?
──タイトルにもあるようにこの公演は(カタログ版)ということで、一風変わった企画です。いったいどんな企画なのか、まずことの起こりから聞かせてください
三浦 そもそも僕が「今、戯曲を書くのがきついんです」と言っていて、(長島)確さんから「では戯曲を書かずに、登場人物のプロフィールをたくさん作るところから創作していったらどうだろう?」と提案をいただいたのが始まりだった気がします。
長島 そうですね。しかもスケジュールがパンパンだったんですよね。
三浦 はい。すでに2023年に豊岡の大学と四国の大学で作品を作ることが決まっていたので、新しいものを書き下ろすのはちょっと難しい、と。
長島 三浦さんの“書けない病”のようなものはよくわかっているので……。
三浦 (笑)。
長島 ただの新作書き下ろしは絶対に無理だけれど、すでに決まっている豊岡や四国の大学と連動させていただいてご一緒できるなら嬉しいことでした。むしろ、カンパニー単独ではできないような作品を、リスクも含めて芸術祭で担えればと。
河合 三浦さんは“書けない病”というのがありつつも(笑)、「新しいフェーズに行きたい」「大人の物語も描きたい」と仰っていたので、一緒にどんなチャレンジができるかを考えました。その時にこだわったことは「ロロとしての公演でなくて良い」ということ。ロロ名義でも三浦さん名義でもよいので、アーティストやカンパニーのキャリアにとってどういう機会になるのかを大事にしました。私たちは公演をプロデュースしたいわけではなくて、ご本人たちが培ってきた強さや良さを大切にしたいので。
──三浦さんやロロの良さが活かせるような企画を一緒に考えていかれた?
長島 そうですね。ただ、これまでは芸術祭のディレクターとして、アーティストへの圧にならないようできるだけ作品の中に介入しないように意図してきました。ところが、だんだん「あれ、案外僕たちって力が強くないかも。あんまり影響力ないかも」と思うようになってきた。
三浦 (笑)。
河合 「透明になって稽古場にいられるかも」って(笑)。
長島 僕も河合ももともとはアーティストと一緒に創作する仕事をしてきた人間です。自分たちのバックグラウンドを封印してまで距離を取ることって、芸術祭にとっても作品にとっても良いことなんだろうかと、年々疑問を持つようになっていて。「もっと作品のなかに入ってみても大丈夫かな?」と思って関わっているのが今回です。
三浦 ありがたいですよ。いろいろお話聞かせてくれたり、稽古場に来てくださることは。僕がテキストを書かず、かつ参加者の当事者性も扱わないクリエーションの形はどういうものだろうと、確さんたちとお話しました。また、フィクションであることは大事にしたかった。そこで、架空のプロフィールを作ることにしたんです。
──すでにネットで、300文字ほどのキャラクタープロフィールが数十人ぶん公開されていますね
三浦 はい。まずイメージしていたのが、江國香織さんの『去年の雪』という小説です。100人以上の登場人物の短いエピソードが連なって、ひとつの物語に集結していくわけでもなく、断片が浮かんでは消えてたまに響き合う。読み終えた後に外に出ると、街を歩いている人たちの輪郭がクッキリして見えるような感動があって……こういう演劇を作りたかった。
もうひとつ、書いている最中によく読んでいたのが、上坂あゆ美さんの『老人ホームで死ぬほどモテたい』という歌集と、リディア・デイヴィスの『ほとんど記憶のない女』という数ページのエピソードをまとめた短編集で、そういう余白があるような構成にしたいと思っていました。
──登場人物のプロフィールを書いた後、どうやって戯曲を書かずに作品づくりをしていくんですか?
三浦 それは悩みました。ワークショップをやってみたり、プロフィールをもとに人物の一代記を作ってみたりして方向性が見えてきたのは、俳優が役や物語をふくらませていけないかということでした。
たとえば豊岡の大学では、僕の書いた架空のプロフィールのうち4人を学生がピックアップして、それぞれの一代記をみんなで作って、そのうちのどの場面を作品にするかを選び、最後のシーンを僕が書く、という作り方を半年ほどかけてしています。つまり僕のオリジナルの言葉があって、それを学生たちが膨らませて自分たちの物語を作り、その物語を見てまた僕が物語を膨らませていく。言葉の受け渡しみたいなことが起きていて面白い。
とはいえ、東京芸術祭は1ヶ月ちょっとの稽古期間で作るので、違う作り方をしないといけない。そのため今回は、プロフィールだけでなく1~3ページくらいの短いテキストを書きました。これをもとに創作をして、公演ではたくさんの登場人物全員が出てくる短いエピソードを見せることで、キャラクターやこの企画自体の自己紹介ができたらいいなと思っています。
──だから(カタログ版)なんですね!いろんなキャラクターを見ることができる
三浦 はい。これから先、このキャラクターたちはいろんな所で出てくるでしょうし、そのうちに誰か一人に焦点を当ててひとつの作品を作ることもあるかもしれません。
長島 期待として、ロロにとって「いつ高シリーズ」(※ある高校を舞台にした連作群像劇。高校演劇の条件である一作60分以内で上演できる)の次の大事な企画になれるんじゃないかなと思っています。この「カタログ」は、俳優たちも参加して物語をつくっていける”演劇キット”になるんじゃないかな。いろんな人に使ってもらえるカスタマイズ可能なキットの開発をしている感覚です。
これができると、どんなカンパニーでも自分たちの人数や性別や年齢に合った戯曲を作ることができる。授業でも、学生の人数にピッタリ合った既存の戯曲を探すのって大変じゃないですか。これならば、豊岡(兵庫)や四国でもどうとでも対応できます。
三浦 実はもうひとつ、今年、いわきアリオス(福島・いわき芸術文化交流館)でも僕の作品を別の方が演出してくださるんです。そこではこのカタログをもとに「どうやってもいいですよ」と言っています。今後、いろんな場所でそういう広がり方をしていくといいなと思っています。
50人のプロフィール。今まで書いたことのない人物像が生まれたらいい
──まず50人ぶんのプロフィールを作ったということですが、プロフィールはどうやって生まれているんですか?
三浦 最初に、(河合)千佳さんや確さんが出会った人についてのお話を聞いたりしました。というのも僕は、オフィスや役所に縁がなくて、舞台のロケーションとして設定できないんですよ。ディテールが全然想像できない。そういうコンプレックスがあって偏ったシチュエーションになることが多いから、そうじゃない場所を描けるようになりたいということを僕からお伝えしたこともあって、おふたりがいろんなエピソードを提供してくださいました。
河合 そうでしたね。三浦さんとお話をするうちにキャラクターを考える時の思考のクセがあるんだなと感じて、じゃあ今回は今までにない人物の作り方を一緒にやってみましょう、ということで、三浦さんが出会ったことのない人物像も取り入れてバリエーションを増やせたらなと。
三浦 もともと記号的にキャラクターを配置していくことが多いんです。たとえば「歩く」というモチーフのキャラクターがいたら「どんな人と出会ったらいいんだろう」と考えて、反対側に「待つ」人を置く。「歩く人の親友はどんな人だろう」と考えて、歩く人は水平移動だから親友には「垂直移動」の人を置く。ただ、記号的に考えることの限界については最近すごく感じています。
それはキャスティングにも繋がっていて、「こういう記号のキャラにはこういう俳優が合いそうだ」と感じる自分の持つこのバイアスって何なんだろう……と考えるとどんどんわからなくなって書けなくなっていく。もっと自由になりたくて、確さんと千佳さんにいろいろ相談をしていました。
長島 記号的に書いている、という話を聞いてびっくりしました。そんな図式的な作り方とは見えないくらい消化されて、今までの作品は描かれていたので。あと、ヨーロッパ中世の道徳劇みたいだなと思いました。当時の道徳劇は、「愛」や「正直」や「嫉妬」のような観念を人物化している。それに似ているなって。
ただ、それはすごく苦しい道だったのだとも思ってしまいました。なぜかというと、そうやって頭で考えていると、インプットが足りなくなって、アウトプットができなくなってしまうだろうから。そのやり方を続けていたら書けなくなっても当然ですよ。この”書けない病”を治すには、当たり外れを問わないインプットが必要だと思って、河合と僕が持っている「こんな人がいる」「こんな人がいた」「こんなことがあった」というエピソードをどんどん三浦さんに投げちゃいました。もちろん、その中から何をどう使うのかは作家である三浦さんが決めることですが。
三浦 それによって、新しくいただいた情報と、これまでの経験が重なってきていると思います。というのも最近、書きあがったものを読んだ演出助手の中村未希に「初期のロロっぽいバカバカしいものから、「いつ高」の会話っぽいものや、『Every Body feat. フランケンシュタイン』(※東京芸術祭 2021で上演)みたいなどろっとした重いものまで全部入ってる」と言われて納得しました。そういう、今までやってきた色々なバリエーションを書きたいなとは、自分自身でも思っています。
──ロロの(カタログ版)にもなっているんですね
三浦 そうですね。僕はこれまではどうしても、僕が摂取してきたサブカルチャーなどの感覚で舞台を作ってきている。でも、もう少し遠いものを作れるようになりたいんです。豊岡の学生たちが50代のキャラクターを選んで、それを演じるために親世代にリサーチをしてエピソードを膨らませている様子からはすごく刺激をもらえます。「親のこんな話は今まで聞いたことがない」と嬉しそうに話してくれたのがすごく嬉しかったです。あと、豊岡出身のキャラクターについて、僕が知らなかった豊岡の街の歴史がエピソードに反映されているのもすごく面白いですね。
長島 面白いですね。選択肢があるので自分と近い世代のキャラクターを演じるかと思いきや、あえて全然違う世代のキャラクターを演じることもある。そうすると、親や知り合いにバブル時代のことを取材していくことにもなったりして、三浦さんが思いもしないようなエピソードが生まれていく。なんだか不思議なことをやっていて、いいなと思います。
脚本をもとに稽古するのではなく、セットリストやマトリックスを作ってみた
──稽古を進めていく中で、構想段階からの変化はありましたか?
三浦 出演者のみなさんから出てくるエピソードをどう繋いでいくかについては、かなり試行錯誤しました。江國香織さんの小説や海外の短編集のような感覚になる舞台を作りたいけれど、やっぱり読書の体験と演劇の体験は違う。全体としてどういう時間を作れるかを意識して、稽古場では、セットリスト作りのワークショップをしたりしました。シーンごとのセットリストを作って、そのなかで欲しいシーンを選んで順番を決めて、各セットリストにタイトルをつけたりします。それぞれ違うシーンの繋ぎ方をしてくれるのですごく面白いですね。
ほかにも、みんなでマトリックスを作りました。縦軸、横軸がなにを意味するのかを自分で決めて、そこにエピソードを配置していく。そうすると、みんなが各シーンについてどう思っているかの共有にもなります。ただ演じるだけではない稽古の時間が面白いですね。
河合 稽古を見学させていただいて思ったのは「ショートケース(短編)がいっぱい並んでいる作品ではないんだな」ということです。三浦さんは「街の人たちの空気を描きたい」というようなことを言われていて、だからある人間関係がずっと描かれるんじゃなくて、街に住んでいる色んな人たちの色んな面がちょこちょこ見えて、街が立ち上がっていく。それがいい。その時間を生きている人たちがたくさんいて、ちょっとすれ違うような空気がある。ひょっとしたらあの人物とあの人物は近いところに住んでいるのかもしれない、とか、会話は交わさなくても同じ空気を吸っているのかもしれない、と感じる瞬間があります。(カタログ版)と言っても目録ではなく、ひとつの街、ひとつの作品になっています。
三浦 そのために美術も衣装も挑戦しています。シーンごとにまったく違う空間がどんどん登場するので、たとえば白一色や黒一色といった変化に対応しやすいシンプルな衣装や美術もありえるんですが、そうではないアプローチになっています。
──50のキャラクターを、50人ではなく6人で演じることは小説ではできないことですね
三浦 いろんな役を演じるので、俳優さん達のいろんな面が見られるのも楽しいですね。あと、みなさん、時間の量をたくさん抱えられる方々なのも良いです。ひとつのエピソードが短いと2分くらいしかないので、そこに描かれていない時間の量みたいなものがたくさん伝わるといい。それができる俳優さん達です。
──新たな挑戦となる企画ですが、その先にどういうことがしたいのか、今後の展望や希望を聞きたいです
三浦 最近よく思っていることとして、僕は初期の頃の作品を「ボーイミーツガール」と自分でも言っていたんですが、今は反省の気持ちが強くある。僕自身が男性欲望従属的なカルチャーをとても摂取してきた自覚があるし、先入観もあります。それをどう変えていこうかと、この数年ずっと考えています。
ただ、僕自身が気づいていないだけで、初期の作品のなかにも「ボーイミーツガール」ではない要素があるんじゃないか。『フランケンシュタイン』でいえば、自分では「暴力が書けない」と思っていたけれど、実はこれまで書いたもののなかに暴力が描かれているんじゃないか……。そう思うようになって、自分で自分にフレームをつけてしまうことで、自分を狭めていたかもしれないと気づきました。だから今は、自分の枠組みを決めない新しいものを描いていけたらいいなと考えています。過去の自分の戯曲を批判するなら、もっともっと過去の自分の戯曲を大事に深く読めるようになりたいですね。
河合 そういうコンプレックスがあるというのは驚きであり、発見でした。三浦さんがボーイミーツガール以外のことや暴力が書けないとは思っていなかったので、今回の作品もみんなが良い人なわけじゃなくて、全員じゃないけど悲しいことや、怒りや、情けなさを抱えている。それはこれまでの作品の蓄積ですし、三浦さんが客観的に過去の作品をとらえようとしているから描けているんだと思います。
また、カンパニーのみなさんも「とりあえず作品を完成させなきゃ!」とならずに、作品や座組に対する信頼関係を大事にしているので、一緒に良い作品ができていることが私としても嬉しいです。
長島 そうですね。僕と河合の今年のプログラミングのテーマとして「人との協働をどう考えるか」というものがある。この作品でも、そこに意識がある方たちが集まっていて、とても良い創作ができているので、公演が楽しみです。
インタビュー・文・撮影/河野桃子