
子役時代に十八世中村勘三郎に声をかけられ、小学五年生の時に決心し中村屋の“部屋子”となった中村鶴松。中村勘九郎、七之助を“兄”と慕う鶴松も、今や中村屋一門の主要メンバーとして欠かせない存在になった。それだけでなく外部の舞台や映像作品など歌舞伎以外のジャンルまで活躍の場を大きく広げ、その成長ぶりに改めて注目が集まっている。
その鶴松が“自主公演”である『鶴明会(かくめいかい)』を立ち上げたのが、2022年のこと。『高坏』と『春興鏡獅子』を上演し多くの観客を集めて大好評だったこの初回から3年、満を持しての第二回公演が決定した。今回は古典の名作中の名作『仮名手本忠臣蔵』より『五段目 山崎街鉄砲渡しの場/二つ玉の場』と『六段目 与市兵衛内勘平腹切の場』、また十八世中村勘三郎から六代目勘九郎に受け継がれた舞踊『雨乞狐』、この二演目に挑戦する。
7月下旬に都内にて取材会が行われ、鶴松がこの自主公演に賭ける想い、演目の見どころなどを熱く語ってくれた。
――今回、二度目の自主公演をこの演目でやることにした経緯を教えてください。
まず、2022年に第一回鶴明会をやった時には、ボリューム的にはかなりのスケール感になってしまい、でもせっかく初めてやる自主公演でしたから、とにかくその時点でやりたい演目のトップ2を選ばせていただいたんです。『鏡獅子』は、僕が人生で一番やりたかった演目で、それと一緒にやるなら何かなと考えて、ヘンな言い方ですがメインを『鏡獅子』にして、サブとして『高坏』という組み合わせにしたんですね。そういう意味では今回は、自分の中ではどちらもメインに思える演目なのですが、でも思いついたものはやろう!ということで選ばせていただきました。どちらかというと先に『雨乞狐』のほうをやると決めていて、『仮名手本忠臣蔵』の『五、六段目』に関しては最後まで悩みました。特に歌舞伎役者にとってみたら怖い演目で、おいそれと自分からやりたいと言えるようなものではないですから。勘九郎の兄も今年3月に歌舞伎座で勘平を演じていまして、その姿を見れば見るほどやっぱりやりたくなった、というのが正直な気持ちです。逆に、もしかしたらやりたくなくなるかと思ったんですよ。こんなのできないやとか、自分にはまだまだ手が届かないと思うかもしれないと予想していたんですけれども、むしろプラス思考になれて「よし、自分もやってやる!」と決心することができました。まだどうなるかはわかりませんが、なんとかして勘九郎の兄を超える勘平を作り上げたい!と今は思っています。
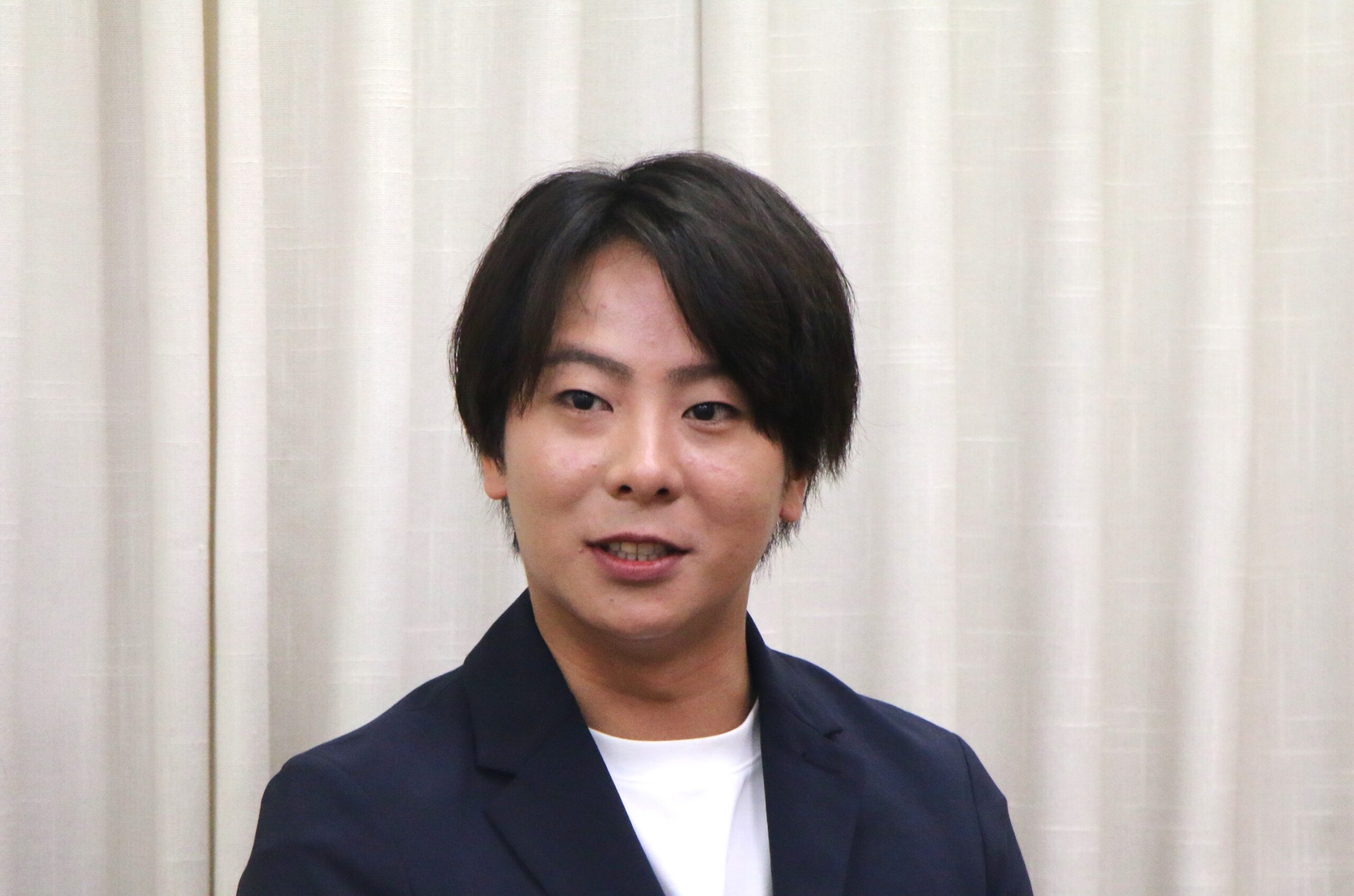
――勘九郎さんからは、どんな言葉をかけていただいていますか。
いや「もうバカなんじゃないの?」としか、言われないです(笑)。というのも、実は『雨乞狐』は勘九郎の兄が膝の靭帯を切ったいわくつきの演目でもあって、本当に体力的にしんどいらしくて。七之助の兄も代役で一度やられているんですが、周りのお弟子さんたちが「あんなに疲れている七之助さんは見たことがない」と今でも言っているくらい、大変にボリューム感のある舞踊なんです。『五、六段目』の勘平も、勘九郎の兄が言うには終わった後に肉体的にも精神的にもグッタリして何もする気が起きなくなるほどの役だというのに「その後に『雨乞狐』を踊るだなんて、本当にバカだとしか言えないよ」と笑われました。
――その勘平役は、たとえばどういうところがハードなのでしょうか。
勘平は、歌舞伎役者にとってはおそらく死ぬまで追求し続けるような役であり、晩年になればなるほど味が出てきたり、いろんなことが理解できるようになる役だとも思います。また、演じられた方々がよくおっしゃるのは「仕事が多い」ということ。ここで小道具をあそこに入れて、とかここの台詞までにあれを移動させてとか、芝居をしながらやるべきことが多いんですよね。まだ僕もやってみないとわからないことばかりですが。だから若いがゆえの良さって、こういう役にはあまりないのかもしれないなんて思っていたんですけれども今回は、いや、そんなこともないなと思い直しまして。特に勘平という人物は29歳で、僕と実年齢が同じなんです。昔とは年齢の感覚って違うのかもしれませんし、これから勘九郎の兄に見てもらいながら役を作っていきますので、今、自分が思っている勘平像は違うと言われるかもしれませんが(笑)、それでもお客さん一人一人に届けられる熱、若いがゆえのパワーというものもきっと出せるだろうと思うので、ぜひそこを見せられたら、と。ちなみに勘九郎の兄が演じていた勘平は、お父さん、勘三郎さんよりもどこか冷静な勘平に見えた気がするんです。この勘平さんという人は本当に可哀想な人で、父を殺してしまったと思ったり、仇討ちに加われなかったりすることは、きっと地獄にいくような心持ちだったと思うので、そんなところも僕自身としてはリアルさを追求してみたいと思っています。それがもしかしたらやってみてうるさかったり、目障りな芝居になってしまう恐れもまだありますが。でも前回の鶴明会でやってみて感じたのは、自分が熱量を持って死ぬ気で舞台に上がっていれば、たとえ下手でもお客様には絶対に伝わるんだということだったんですね。ですから今回は、本当に追い込まれて追い込まれていったた末に自ら腹を切ってしまう、その瞬間の絶望した勘平というものを出来る限りリアルにお見せできたらと考えています。

――『雨乞狐』という舞踊についての魅力も、教えてください。
これは、どうして上演する機会が少ないんだろうと不思議に思うくらい、非常に面白い演目なんです。勘九郎の兄が演じた時、僕はまだ子供で提灯役で出演した経験があるんですけれども鮮明に記憶に残っていて。あの時の兄の姿がめちゃくちゃカッコ良くて、毎日、終演後に一緒に劇場のお風呂に入っては、踊りのコツや演目の面白さを聞いて、子供ながらに「めっちゃ面白い、この踊り!」と思っていたんです。だけどよくよく話を聞くと、本当に身体的負担がものすごい演目らしいんですよね。なので、一カ月公演ではなく数日間だけの公演でやるものだ、とも言われていまして。でも今回の、提灯役を含めた六役早替りというのは歌舞伎ファンではない方が観ても単純に楽しめるでしょうし、なにしろとにかく曲が素晴らしいですしね。踊りは前半、中盤、後半に分けられるんですが、まず前半はダイナミックでアクロバティック、日本舞踊というよりちょっと器械体操みたいな面もあり、中盤が一番難しいと思うんですけどしっとりと踊りで、役者としての表現力が求められてきます。そして最後にまた派手でダイナミックな踊りになるという、この構成もいいんですよ。まさにこれは、若い時にしかできない演目だとも思うので今のうちに、1日2回公演はちょっと未知の領域ですけどなんとかがんばってやりとげたいと思っています。
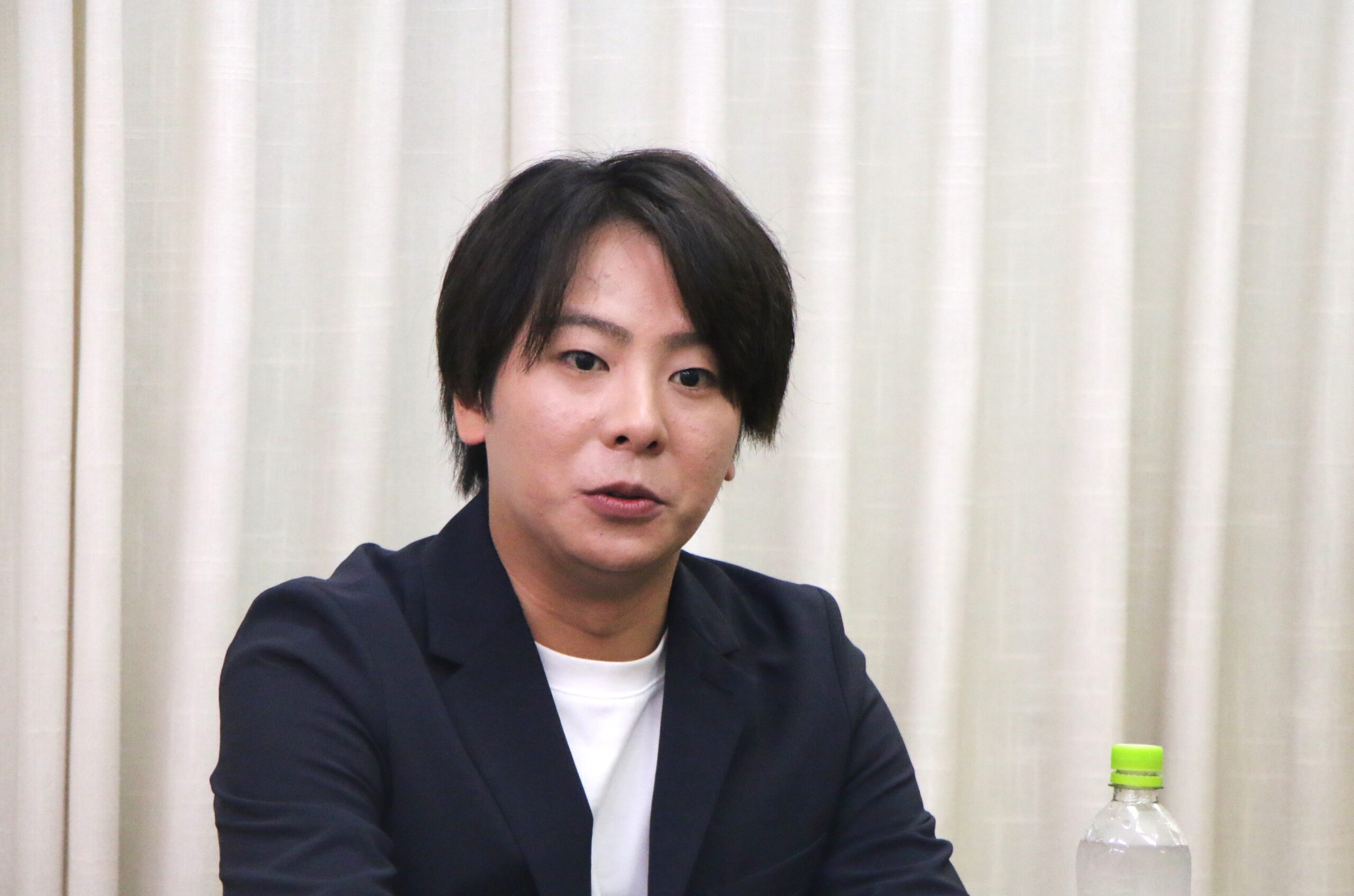
――今回は共演者も、かなり豪華な方が揃いますね。
僕が思う、最強メンバーを揃えました(笑)。勘九郎の兄が定九郎を演じてくれるというのも、大きいですよね。莟玉くんは、お互いに部屋子の頃からずっと共に切磋琢磨してきた仲間なんです。中学と高校も同じ学校で、彼は梅玉さんの養子となって本当に素敵な役者さんになられていますけど、部屋子という立場の大変さ、苦しさ、悔しさをよくわかっている関係性で。今回は、初めての女房役ですね。ふだんはなかなか共演する機会が少ないんですが、今年1月の浅草歌舞伎で久しぶりに共演し、いろいろ話もできて、こうしてこの会への出演も快く引き受けてくださいました。福之助くん、歌之助くんは言わずもがな、子供の頃からずっと中村座などでも一緒にやってきた仲ですし、彼らがやっている自主公演『神谷町小歌舞伎』にも出させていただいて「鶴松くんが自主公演をやるなら、もちろん出るよ」と言ってくれていたので。お父様の芝翫さんにお電話した時も「別に気を遣わなくていいから自主公演は好きにやりなさい」とおっしゃってくださいました。さらに梅花さん、歌女之丞さん、精四郎さんももちろん、もうみなさんやっぱり勘三郎さんというどでかいスーパースターの背中を見て、育ってきた方たちですからね。このメンバーなら同じ方向を目指して『五、六段目』を一緒に作り上げてくれるだろうと思っています。僕自身は、これまで勘平みたいな役を演じた経験がないので、本当にドキドキで(笑)。もう、できるだけ周りを固めておこうと思い、乗れる船には乗らせてもらおうということで、このベストメンバーにお願いした次第です。
――歌舞伎座での興行に行くのと、こうした自主公演とでは、もしかしたらお客様の心持ちとしては少しハードルの高さを感じられるかもしれません。でもぜひとも気軽にこの自主公演にも足を運んでいただきたいと思いますので、鶴松さんから何かお誘いの言葉をいただけますか。
いや、今だったら映画『国宝』を観た方は全員、この公演を観に来ていただきたいです!(笑)
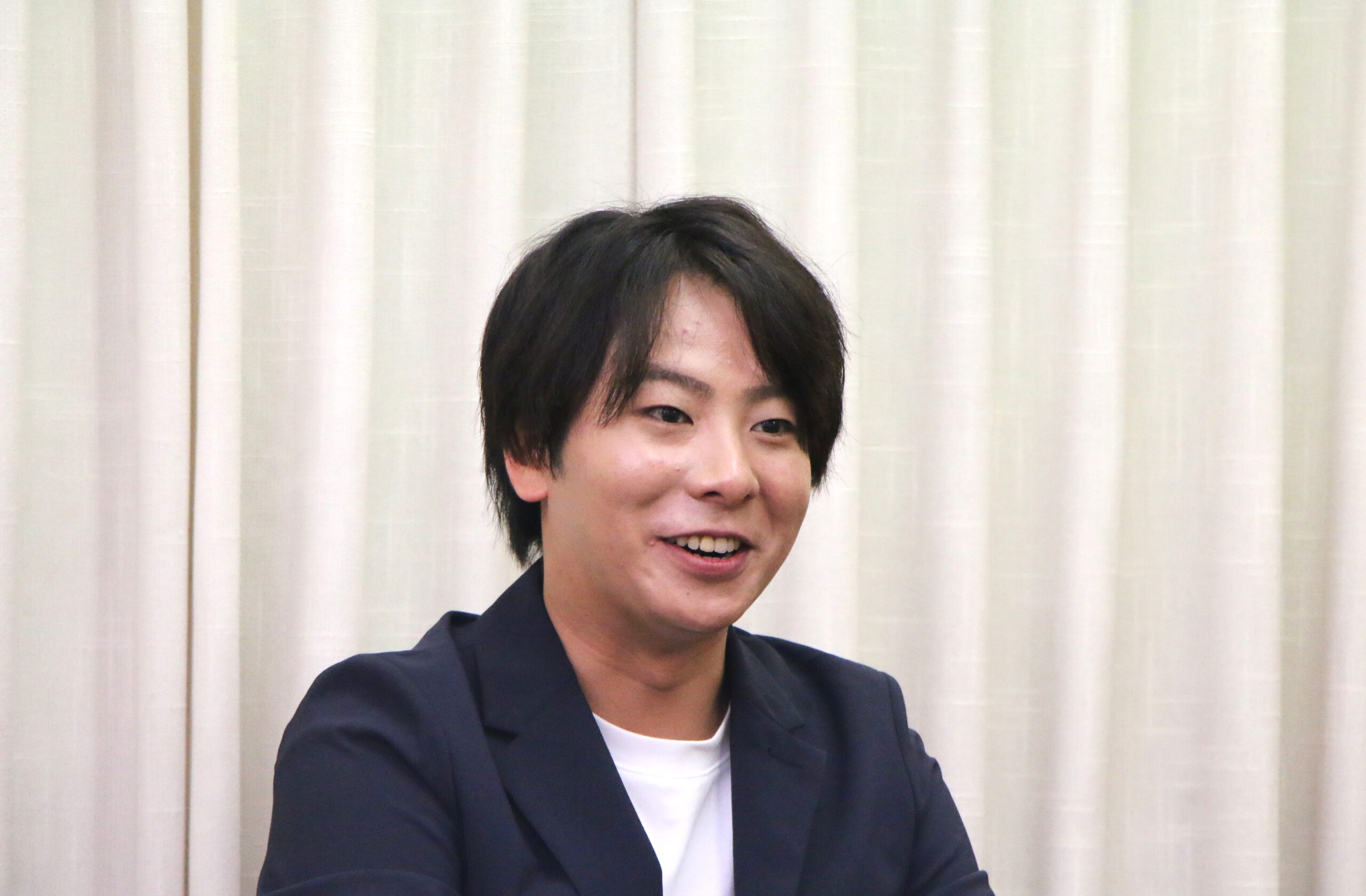
――確かに、そうですよね!
特に僕の場合は主人公の喜久雄と同じような立場なので、どこに行っても『国宝』の話をされるんですよ。違う点があるとすれば、任侠の家出身じゃないところですが(笑)。
――やはり『国宝』をご覧になって、思うところは。
もちろん、たくさんありました。言われたことがある台詞や、経験したことがある場面だらけで、いろいろなことが心に刺さって苦しい気持ちにもなりました、まあ、あそこまで苦しくなったのはこの世の中で僕だけでしょうけど。手が震えて化粧できないとか、ああいう瞬間もめちゃめちゃわかる~!と思いましたし。そして映画を観ながら、次回の『鶴明会』では『道成寺』と『鷺娘』をやろうかな、とも思いました(笑)。そうやって、まさに今がチャンスだと思いながらも、でも怖いのは映画を観た方が実際に歌舞伎をご覧になって、そこで「やっぱり歌舞伎は難しいんだな、もういいや」と思われてしまうこと。それについては僕らだけじゃなく、全歌舞伎役者が危機感を抱かなければいけないことだとも思いますけれどね。そのためにも毎回劇場まで足を運んで高いチケットを買っていただき、観てくださっているお客様を一人でも多く味方につけながら、さらに未来のお客様もどんどん積極的に増やしていかないといけないなと思っています。
取材・文:田中里津子


